座談会

長谷川 直樹 先生
慶應義塾大学医学部
感染症学教室
教授
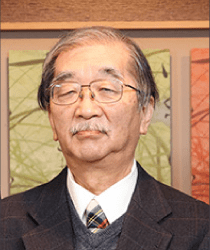
倉島 篤行 先生
公益財団法人結核予防会
複十字病院
臨床研究アドバイザー

森本 耕三 先生
公益財団法人結核予防会
複十字病院
呼吸器センター(呼吸器内科)医長
近年日本では肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)の患者が急増し、日常診療のなかでも遭遇する機会が増えています。一方で、肺NTM症の診断は困難な面が多く、さらに治療が長期間におよぶことから、専門医とプライマリ・ケア医の連携が不可欠と言えます。そこで今回、非結核性抗酸菌症研究コンソーシアム(NTM-JRC)のメンバーであり、日々肺NTM症の診療や研究、普及・啓発活動に取り組まれている先生方をお招きし、肺NTM症診療の現状や今後の課題を中心にお話を伺いました。
(座談会開催日:2020年10月18日、開催場所:ザ・キャピトルホテル東急(東京赤坂))
01|肺NTM症の
早期診断における課題
司会一般的に早期診断・早期治療の重要性が言われるなかで、肺NTM症の早期診断には課題が多いと聞きます。まずその理由について教えていただけますか。
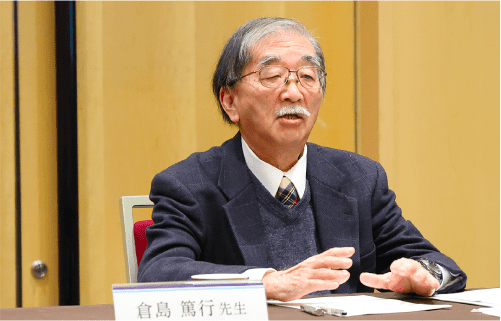
倉島一つには疾患の認知度の問題です。一般の方には「非結核性」という名称から「何か難しい病気」という印象が先行し、正確な情報が伝わりづらいようです。さらにインターネット上に流れる不確かな情報を信じてしまう方もいます。またこの疾患には患者会がなく、患者が自分と同じ疾患を経験している人の情報を得にくい状況にあります。当院では何度か市民講座を開いてきましたが、その際に疾患の正しい情報を求める声を多くいただいたことがNTM-JRC設立のきっかけにもなっています。
長谷川医療者側の認知度はというと、近年は医学部の教育にNTM症が組み込まれたり、国家試験でも取り上げられるようになったため、若手医師や医学部生には浸透してきたと思います。したがって、今現場におられる先生方がどの程度認識しているのかが重要です。患者の受診のきっかけは、症状がある場合、あるいは症状はないものの検診で指摘された場合の主に2パターンがありますが、いずれも担当の医師がこの疾患を頭に浮かべ、いかに実際の診断に結びつけられるかどうかです。最終的には患者から菌が検出されるか否かが診断の一番重要なポイントで、喀痰検査に行きつけるかどうかが重要です。
司会最初のステップが必ずしも専門医の受診ではないのですね。
長谷川はい。受診のきっかけになる症状の一つとして血痰がありますが、これも数日続くと言うよりも大抵は1日で治まってしまいます。プライマリの先生には、肺NTM症の患者数が増加し稀な疾患でないことや受診きっかけなどを知っていただき、受診時に画像検査を実施したり、画像検査で所見を認めた場合には痰が出なくても患者に容器をお渡しし、「とにかく痰が出たら持ってきてください」という形で喀痰検査までつなげていただくことが早期診断の要となります。
森本プライマリの先生に求められるのは、患者の受診きっかけによらず「疑い」を持つかだと思います。疑いがあれば疾患に関する患者教育ができますので、これらの先生方には患者に教育の手がかりを提供するという点で期待したいです。
02|検査・診断における日本の特徴
司会検査にも課題はありますか。
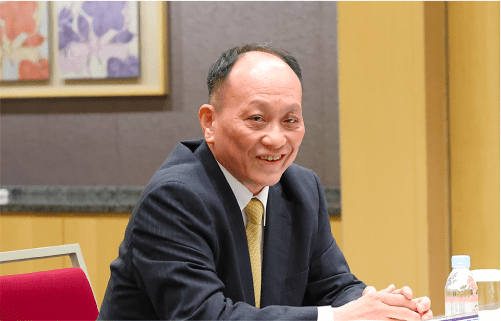
長谷川基本的に抗酸菌の検査は、菌そのものを同定する検査と、菌に対する抗体の有無を調べる検査があります。菌の同定には患者に痰を出していただき、その中の生きた菌、あるいは菌の欠片を見つけることが必要です。抗体検査は日本で研究が進んでいる方法で、現在、保険診療で行うことができます。クリニックなどでも抗体検査は可能だと思いますので、まずスクリーニング検査として実施していただくのが良いかもしれません。例えば血痰がある患者では抗体検査を行いつつ喀痰採取用の容器をお渡しし、採取できたときに持ってきていただくという流れができると良いですね。喀痰の採取は難しく、どうしても唾液を出してしまう方もおりますが、それでは正しく診断はできません。このように課題はあるものの、まずは良い検体、特に咳と一緒に喉の奥にあるものを出していただければ、次のステップに進むことができます。
司会今のお話は、確定診断ができない場合の対応にもつながりますね。
倉島そうですね。同じ抗酸菌症でも、結核では菌を1回検出できれば確定診断になりますが、この疾患は1回だけでは確定できないため、診断にはどうしても経過をみる必要が出てきます。ただ、肺NTM症はそれほど激しい疾患ではないため、高熱が出ることもなく、重症になるまでは咳や痰で生活上困ることもありません。したがってこの疾患を疑う場合、軽症であれば原則3ヵ月に1度受診していただき、その間に2回以上菌が検出されれば確定1)となります。

森本ちなみに診断に菌を2回以上検出する1)というのは海外の診断基準2)と共通ですが、日本と海外では大きく異なる点もあります。それは海外では診断に症状が必要2)であるのに対し、日本では症状の有無を問わない1)点です。日本の場合、無症状でも検診で早期に指摘される方が多く、実は進行しているケースもあるため、症状の有無にこだわらず画像と菌の確認で診断することになっています。
倉島日本は単位面積当たりのCT台数が世界トップで3)、近年は、肺癌早期発見にはCT検査の役割は評価されていますが、検診にもCTを使う国はまずありません。CT検査は費用自体が高額で、保険が適用されるシステムがない国のほうが多いのです。日本は地域の検診でもCT検査が含まれ、無症状でもみつかる例が非常に多く、診断基準のなかに症状を入れるのは日本の現状に合わないと考えられます。
03|治療の現状と継続における課題
司会続いて治療について、特に肺MAC症についてお話を伺います。標準治療があるものの、課題も多いそうですが、具体的にどういった点が挙げられるでしょうか。
森本現在の標準治療は1990年代に主に米国で提唱された治療法で、リファンピシン、エタンブトール、クラリスロマイシンの3剤併用療法です。これは1980年代にAIDSによる播種性MAC症が問題となり確立された治療法で、現在も同じ3剤治療が続いています。このうちマクロライド系のクラリスロマイシンがキードラッグで、現在我々はこの薬剤の使用に非常に気を遣っています。というのも、マクロライド系の薬剤は風邪や気管支炎などでも処方されることがありますが、単剤で使用すると耐性化することがあるのです。マクロライド耐性になると予後不良になることも知られており、マクロライド耐性の肺MAC症患者を対象とした海外の後ろ向き調査では、85%の患者が予後不良で、耐性出現後の5年死亡率が47%と報告されています図14)。また標準治療による副作用の多くは回復するものの、患者によって遷延するケースもあるため、いかに副作用を少なく長期的にこの3剤を使っていくのかが重要です。
司会先ほど経過観察が数ヵ月単位というお話でしたが、治療も長い目でみる必要があるのでしょうか。
森本そうですね。標準的な治療期間は、治療開始後に菌の陰性化を確認してから1年というのが国際的な基準です図25)。ただ効果がそれほど十分とはいえず、副作用リスクのある薬剤を長期間服用し続ける必要があるため、現在の標準治療は問題が多いのは事実です。また当院は専門病院のため、副作用や治療抵抗性となって紹介いただくことが多いのですが、進行してからでは治療効果が得にくくなります。また、いつ悪化するかもわからないため、無症状の方や日常生活に支障がない方でも定期的に画像検査が必要です。肺MAC症患者は一般人に比べQOLがかなり障害されているとの報告もありますので6)、軽症・中等症のうちに治療を開始し、長期的にみていくことが重要でしょう。一方、治療終了後も環境中の菌からの再感染や肺に残存していた菌が再度増殖して起こる再燃のリスクが高いことがわかっており、特に結節・気管支拡張型では、抗菌治療後の再発例のうち75%は再感染であったとの報告もあります7)。
司会再感染の予防のために何か環境で注意することはありますか。
倉島肺NTM症は結核とは違い、排菌している人と一緒に暮らすなどの接触があってもかかりません。一般的に原因菌は水中や土壌に生息しており、例えば24時間循環型の風呂のフィルターは菌量が多く、以前より浴室が感染源と考えられる事例が多く知られています。土壌の場合、特に園芸で使う腐葉土などは菌量が多いことが知られています。このように身近な環境中に生息しているため、再発を防ぐには回避することがかなり重要です。ただ身近に存在するといっても、菌を浴びた人すべてがこの疾患になるわけではありません。まだ完全に解明されてはいませんが、宿主背景という遺伝子多型や他の要素、この疾患になりやすい要素を持つ人がおり、同じ環境に住んでいても、例えば奥さんが肺MAC症になっても旦那さんはならないということがあります。
図1
マクロライド耐性肺MAC症患者の
治療アウトカム(海外データ)
対象・方法:2002〜2014年にソウルの大規模総合病院でマクロライド耐性肺MAC症と診断された34例の診療記録を後ろ向きに調査し、臨床的特性や治療アウトカムを評価した。
Moon SM, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2016; 60(11): 6758-6765. より作成
04|期待される
プライマリ・ケア医の役割
司会ここまで伺ったお話から、肺NTM症の診療にはプライマリ・ケア医との連携がより一層求められるかと思いますが、専門医との役割分担についてはどのようにお考えでしょうか。
倉島現時点で、当院では紹介患者の菌の同定、1年ごとに受診いただき治療内容の確認・変更をするなどの対応を、プライマリの先生にはその間の処方をお願いするなどの連携を多くの患者で行っています。
長谷川実臨床において疾患をしっかり理解されているプライマリの先生は多くないと思いますが、患者数を考慮すれば専門医だけで全患者を診療するのは不可能ですので、より経験を持った先生を増やすことが重要だと思います。何かあれば必ず相談できる体制をつくり、専門医とプライマリ・ケア医が共通認識を持って治療を進めていく形が必要でしょう。また倉島先生がおっしゃったように、プライマリの先生には処方や、できれば患者の受診ごとに喀痰の採取をお願いし、一方で専門医には年1回を目安に受診いただきフォローする、といった役割分担を作ることも重要だと思います。
森本プライマリの先生にとって、この疾患の診療は難しい面も多いのは確かですが、特に呼吸器科の先生や感染症の診療経験の多い先生とは連携して診療していきたいと考えています。とにかく一緒にこの疾患を診る仲間を増やしたいという思いが強いです。一方で地域によっては呼吸器専門医が乏しいなどの事情もありますが、そういった地域の患者さんをプライマリの先生方と一緒に診ていきたいと考えています。NTM-JRCの取り組みも含め疾患を知っていただき、「我々も診ますよ」という先生が増えることを期待しています。
司会今の「仲間を増やしたい」というお言葉が、肺NTM症の患者数の多さや、疾患理解が医師、患者ともにあまり高くないという現状を表しているように改めて感じました。疾患理解や治療法の進展とともに、プライマリ・ケアの先生方が患者を専門医につなぐ橋渡しとしてさらに活躍されることを期待し、本会を終了したいと思います。本日はありがとうございました。
今回、NTR-JRCの先生方を中心に肺NTM症の診療用の資材図3を複数監修されたとのことで、資材に込めた思いを一言ずつお聞きしました
倉島患者説明用の資材は、例えば標準治療について「治療するならこういう形の治療が望ましい」というものを提起しており、この疾患についてあまり詳しくない先生でも正しい情報が患者に説明できるような流れになっています。
森本それぞれ呼吸器専門以外の一般内科の先生と患者との知識や情報の共有をサポートする資材になっていると思います。
長谷川治療以外にも、疾患について現時点でわかっていること、わからないことも含めた一般的な事実を示しています。患者にはこれらの資材を使ってお話しいただくと良いと思いますし、医療者側が共通認識として最低限備えておくべき正しい情報も含まれていますので、ぜひ活用していただきたいです。