座談会
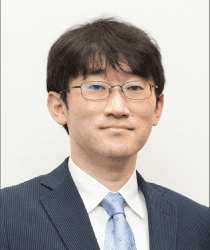
森本 耕三 先生
公益財団法人結核予防会
複十字病院 呼吸器センター
(呼吸器内科)医長

小川 賢二 先生
独立行政法人 国立病院機構
東名古屋病院
副院長(現 医療顧問)
呼吸器内科

㆗川 拓 先生
独立行政法人 国立病院機構
東名古屋病院 第一呼吸器内科医長
(現 統括診療部長)
近年日本では肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)の患者が急増しており、プライマリ・ケア医も含めた診療への取り組みが求められています。一方で、肺NTM症の治療期間は年単位と長く決定的な治療法もないことから、患者の治療継続へのモチベーション維持も重要となります。そこで今回、日々肺NTM症の診療に取り組まれている専門の先生方をお招きし、肺NTM症の診療のポイントとともに、患者が前向きに治療に取り組むためのコミュニケーションの工夫などを伺いました。
(座談会開催日:2020年11月6日、開催場所:
名古屋 JRゲートタワー カンファレンス)
01|肺NTM症をめぐる現状
司会近年肺NTM症が増加しているそうですが、まずはこの理由について教えていただけますか。
中川肺NTM症は結核のように全例報告をしないこともあり、長らく正確な患者数が分かっていませんでした。2014年の全国調査で、結核を上回る罹患率であることが明らかとなり1)、世界的にみても特にアジア、日本で増加しています。これには疾患の認知が進み、疑わしい症例への積極的なCT検査が実施されるようになったことや、検査法の進歩の影響があると思われますが、このほかにも何か増加する要因があると推測されるものの、現時点では分かっていないというのが実情です。
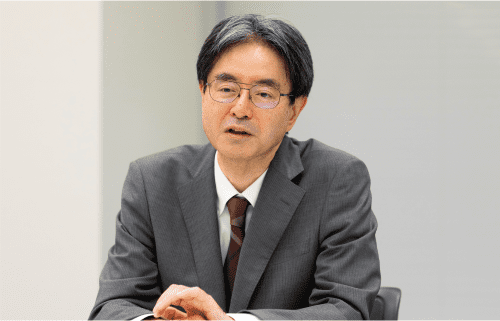
小川中川先生が今おっしゃったように、認知度の上昇や診断技術の向上が背景にはあると思います。しかしそれだけでは説明がつかず、現在環境因子や宿主因子に関して、例えば東アジアの人種の特定の遺伝子に何か問題がないか、環境中の菌量と感染の関連などについて研究が進められていますが、結局のところ明らかな因子は分かっていません。現時点では幾つかの異常が重なることで、肺NTM症の病態が起こると考えられています図12-4)。
森本そのほか特に日本では、高齢化や健診システムの整備、また、風呂文化も推測されています5, 6)。
司会何か患者さんに特性はありますか。
中川女性の、特に中高年の閉経後の方に多いため、女性ホルモンとの関連も仮説としてはありますが、根本的になぜ女性に多いかという点も分かっていません。
森本結核の治療期間が半年程度であるのに対し、この疾患は経過観察の方がおり、治療期間が長いうえに治療終了後も再感染することがあるため、患者さんがどんどん累積します。その結果、罹患率以上に有病率の急激な増加がみられるようになりました。最近はマスメディアが取り上げて下さる機会も増えましたので、今後さらに認知が広がることを期待しています。
図1
肺NTM症の有病率を
上昇させると考えられる要因
02|早期発見・診断のポイント
司会肺NTM症の患者数が増加し、プライマリの先生方も診療機会が増えていると聞きます。症状や患者背景からこの疾患を疑うポイントを教えていただけますか。
小川まずこの疾患には特異的な症状がありません。一般的には咳や痰を訴える方が多く、1日に何回か咳き込む、痰が数日に1回出るといった症状が慢性的に続きます。喘息をはじめアレルギー疾患で慢性的に咳や痰が出る方もおり、鑑別診断として同じ症状がいくつか挙がるのですが、疑うという意味ではまず鑑別診断の1つに挙げることが重要でしょう。なかでも黄色や茶色がかった痰が慢性的に続いている場合は、必ず胸部X線検査と喀痰検査で確認する必要があります。
また、肺NTM症のリスク因子として気管支拡張症やリウマチ性疾患などはよく知られており表17)、特にリウマチ性疾患は、生物学的製剤やステロイドなど免疫抑制作用のある薬剤を使用していることもあるため、既往歴についてもしっかり確認が必要です。このほか、肺NTM症の原因菌は水中や土壌中に多いことが知られているため表22, 8)、例えば家庭菜園をしている、部屋の中に観葉植物があるなどの生活歴についても私は確認しています。
森本今のお話に加え、中高年の痩せている女性に多い疾患ですので、そういう方で咳や痰を訴える方は、特に積極的に疑ってよいと思います。一方、検診の胸部X線検査で異常が指摘されるものの、検査所見として「炎症性変化」や「要観察」と表現されていることがあります。検診は主に癌の早期発見を目的としていることもあり、検診指摘があっても「癌でなければ大丈夫」と受診につながらないケースもあるため、肺NTM症診断のための検査につなげることが重要です。
中川我々は非専門の先生方に向けた診療サポートツールを複数作成しています図2。問診のポイントや確定診断に必要な検査など診療に必要な情報を解説したものや、疑い例や診断された患者さんへの説明に使用できる冊子などもありますので、ぜひ活用いただきたいです。
表1
肺NTM症の
宿主感受性に関連するリスク因子
Prevots DR, Marras TK. Clin Chest Med. 2015; 36(1): 13-34.
表2
NTMの生息環境の例
03|治療における課題
司会肺NTM症は、診断されたからといって必ずしも治療を行うわけではないのですね。
森本はい。どの方にどのタイミングで治療を開始するのかという点は非常に重要です。国内外のガイドラインでは、空洞形成を伴う場合や塗抹肺菌量が多い場合、血痰・喀痰症状を呈する場合、病変範囲が広い場合は治療開始が推奨されています9, 10)。ただし空洞形成があると予後不良に陥りやすいため11)、実際には空洞形成が起こる前に治療を開始する方が望ましいと考えています。
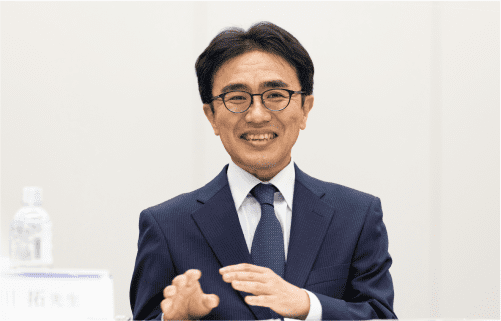
中川空洞があっても限局している場合には、手術による切除と薬物療法の併用で病勢コントロールが良好となるケースも多いのですが、空洞があちこちにできると手術ができなくなります。空洞があるにも関わらず経過観察をしているケースが散見されますが、これは積極的に治療が必要な患者さんです。
小川なかには診断後数年間治療をしなくても、画像上で軽い影の出現と消失を繰り返す方もいますが、実際は徐々に進行し、10年単位でみると多くの方で診断当初に比べ病変が広がっています。気がついたら悪化していたということにならないよう診断後は経過観察を十分に行い、治療開始のタイミングを見誤らないことが非常に重要です。治療開始の目安としては、例えば無症状の方に自覚症状が出始めたとき、もともと症状が軽い方でも症状自体の頻度が上がったり咳や痰以外に倦怠感が出てきたり、今まで通りの食事で体重が減少する、さらに血痰や息切れ症状が出るなど一段階上の症状悪化があれば、必ず一度検査確認が必要です。プライマリの先生のなかには、経過観察のみで治療経験が少ない方もいらっしゃると思いますが、自覚症状や胸部X線検査で悪化を認めた場合は専門医に相談していただくのがよいと思います。
司会一方、治療を行うにも薬剤の選択肢に限りがあるそうですね。
森本最近までこの疾患の重要性や薬物療法の困難さが伝わらず、新薬開発につながっていなかったというのが実情です。現在の標準治療は1990年代後半に確立されたものですが、高齢患者の場合は若年患者のようには服用できないケースや、合併症による他剤との相互作用で注意する点も多く、治療開始に躊躇する場面もあります。ただ、標準治療が難しい場合も薬剤の量を調節するなどして、病勢抑制や症状緩和を目的とした治療を行うべき場面は多々経験します。
小川そうですね。現在の標準治療は決定的な治療法ではありませんが、できるだけQOLを落とさず今まで通りの生活を継続するためにも、年齢にかかわらず行う価値は十分あると考えます。
04|患者コミュニケーションの
重要性
司会患者さんによっては十何年という長期間の治療が続くそうですが、患者さんの治療へのモチベーションを維持するために何か心がけていることはありますか。
小川1つは患者さんの立場に立つということです。外来診療は非常に忙しく、1人の患者さんにゆっくり時間をかけるのが難しいのですが、患者さんは疾患の正しい情報を求めて来院しているわけで、きちんとした説明がないと、もやもやが残るのですね。したがって、じっくり説明が必要だという場合は、例えば初診時に時間が足りなくても次回の予約受診では時間を十分に確保して説明する、紹介受診も初回はセカンドオピニオンという形で1時間取るなどすると、患者さんやご家族の納得が得られやすいと思います。
中川セカンドオピニオンで、今の治療がベストで追加治療はないというケースもありますが、1時間話すとそれだけで「こんなに話してもらったのは初めてだ」と納得する方は確かにいらっしゃいますね。
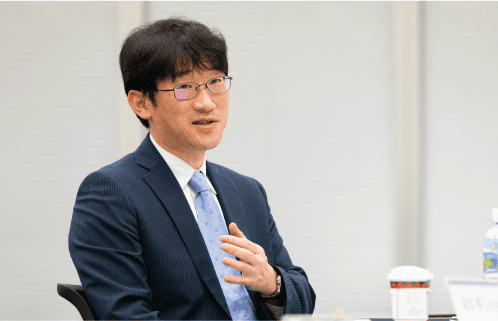
森本1回の診療で全て説明するのは難しいため、患者さんには少しずつ段階的に理解していただくことを心がけています。病名と一般的な知識から始まり、次に進行する可能性があること、その次の段階で治療内容や経過などを説明します。幸いこの疾患は急激に進行することが少ないため、徐々に理解をしていただきつつ、理解が深まった頃と治療開始のタイミングが重なるとよいですね。特に遠方から来院される方には、まずはセカンドオピニオンで詳しく説明する時間があると、その後がスムーズだと思います。患者さんは疾患そのものを知らないがために不安というところがあると思いますので、こちらからも積極的に説明するようにしています。
司会この疾患ならではの大変さでもある一方で、基本的には緩徐に進行するからこそ、患者さんに段階を踏んで向き合っていくこともできるわけですね。
小川結局のところ、患者さんに言いたいことを言っていただき、丁寧に対応するのが一番ではないでしょうか。実際患者さんと話す内容の多くが疾患と無関係で、疾患の話はほんの少しというパターンの方がいるというのは他の先生方も経験されることと思います。それでも会話することによって患者さんの満足感が得られ、次の受診へのモチベーションになるのではと考えています。
05|今後の肺NTM症診療への期待
司会それでは最後に、プライマリの先生との連携も含め、今後の展望についてはいかがでしょうか。
中川現状では、経過観察を専門医や呼吸器内科医が行っているケースが多いと思いますので、今後プライマリの先生に疾患自体の認識がより広がることを期待します。例えば検査の間隔にしても、CTは被曝の問題もあり、個々の患者さんの考えや重症度によって工夫が必要ですので、治療機会を逃さないタイミングで紹介いただけるような関係が今後構築できたらよいと思います。
森本呼吸器内科の先生や一般病院の先生方とは連携ができていると思います。一方、プライマリの先生には新型コロナウイルス感染症の影響もあり、喀痰検査は頼みづらいといった難しい面もありますが、信頼関係を築き、現実的な良い関係を築いていきたいです。
小川プライマリの先生にこの疾患が浸透しない1つの理由は、決定的な治療法がないということにもあると思います。「治る」と言い切れないために、患者さんに対してどうしても説明がしづらいのですね。そういう面でも、我々は決定的な治療法の開発を非常に期待しているところです。
司会最新の肺NTM症の治療や研究状況について知る機会の1つとして、次回2021年度の日本結核・非結核性抗酸菌症学会総会・学術講演会についてもご紹介いただけますか。
小川はい。テーマは「抗酸菌症マネジメントのUP TO DATE~基礎・臨床研究の成果を臨床現場に活かし、適切な医療を目指す~」です。結核は長年の懸念事項であった多剤耐性菌に対する新薬の登場により、ほとんど治療可能となったのに対し、肺NTM症の治療は途上段階にあります。我々のグループは決定的な治療薬の開発を目指して菌の病原因子研究を継続していますが、宿主因子研究や日常診療を含めて、今後の肺NTM症診療には全く新しい考え方でのアプローチも重要だと考えています。本講演会では、治療のブレークスルーとなるUP TO DATEな研究情報をぜひ議論していただきたいと願っています。
司会本日は、肺NTM症の解説だけではなく、患者コミュニケーションにも重点を置いたお話を伺いました。先生方が医師と患者以前に人と人として向き合い、患者さんの心をほぐすことに意識を向けられていらっしゃることに、一患者になり得る立場としてとても心強く感じました。本日はありがとうございました。