座談会

田尾 義昭 先生
独立行政法人 国立病院機構
福岡東医療センター
呼吸器内科 部長
(現 呼吸器感染部長)

若松 謙太郎 先生
独立行政法人 国立病院機構
大牟田病院 呼吸器内科
臨床研究部長

藤田 昌樹 先生
福岡大学医学部
呼吸器内科学 教授、診療部長
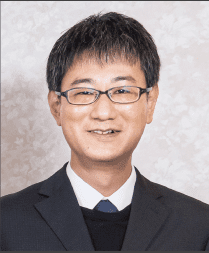
原田 英治 先生
九州大学病院 呼吸器科 助教
非結核性抗酸菌症(肺NTM症)は、近年国内外で患者が急増しているにもかかわらず疾患の認知度が低く、早期診断や治療、患者コミュニケーションなどに様々な課題があると言います。今回、福岡県で肺NTM症診療に取組まれている先生方をお招きし、肺NTM症診療の実情や福岡地区での取組み、今後の展望などを伺いました。
(座談会開催日:2020年12月12日、開催場所:
ANAクラウンプラザホテル福岡)
01|国内における肺NTM症の現状
司会近年国内では肺NTM症が増加していると聞きます。まずはこの背景について教えていただけますか。
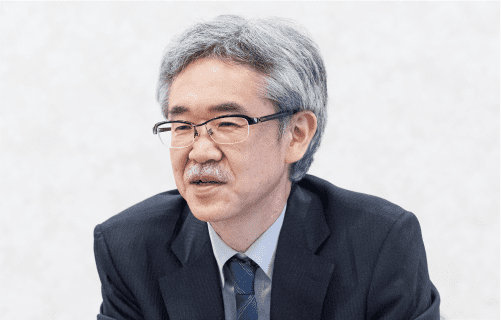
藤田肺NTM症は2000年頃から少しずつ増加し、特に2010年以降急激に増加しています図11)。この理由は、疾患概念やCTの画像所見が徐々に周知され診断機会が増えたこと、世界的に欧米各国や途上国でも増加していることから、結核の減少や世界の環境変化などが可能性として言われていますが、結局よく分かっていません。中高年女性の痩せ型の方、閉経後の女性に多く、性ホルモンとの関連も指摘されています。また、患者さんの増加に伴って重症者も増えており、2019年の国内肺NTM症の年間死者数は1,076人と報告されています図23)。
若松当院は重症の患者さんが多く、約10年で肺NTM症患者150名中20~30名が亡くなっています。高齢者が多いため年齢の影響もありますが、実際にこれだけの方が亡くなっているのです。
田尾この疾患は高齢患者さんが多い分、年齢に加え合併症などの影響も大きく、純粋に肺NTM症による死亡ではない可能性はありますが、死亡する方は多い印象です。
司会このように死に至る疾患である一方で、ほとんどの一般の方は疾患名すら知らないと思います。疾患認知が進まないのはなぜでしょうか。
藤田やはり「肺非結核性抗酸菌症」という疾患名が分かりづらく、浸透しないのではないでしょうか。たとえば呼吸器疾患のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)も世界的に見ると第3位の死亡者数4)であるにもかかわらず、認知が進んでいません。いずれも名称自体の問題と呼吸器学会を含め我々専門医の努力不足があるようにも思います。
図1
本邦における肺NTM症罹患率の
年次推移1)(1980〜2014年)
試験概要:日本呼吸器学会認定施設・関連施設(884施設)を対象に、2014年 1~3月の肺NTM症および結核の新規診断数を調査するアンケートを実施した。肺NTM症罹患率は、厚生労働省結核発生動向調査をもとに、アンケート回答における結核患者数に対する肺NTM症患者数の割合から推定した。
図2
本邦におけるNTM症
死亡数の推移(2005〜2019年)
02|肺NTM症を疑うポイントと
治療開始の目安
司会肺NTM症は発見されにくいと聞きますが、先生方が疑うポイントを教えてください。
藤田中高年の女性で咳や痰が慢性的に続き、胸部X線検査で疑わしい影がある場合や、検診で異常を指摘された方で肺の左右ともに影がある場合に、積極的に疑います。左右どちらか一方の場合もありますが、両肺に病巣ができやすい印象があります。3週間以上続く咳は要注意ですし、8週間以上続く場合は受診していただくのがよいでしょう。
若松症状に加えて、痩せた女性で比較的生活習慣がよく几帳面、神経質な方でしょうか。この疾患は気管支が拡張するため、血痰が出る方も疑います。
司会原因菌が風呂場や水回りに多いと聞きますので、むしろ几帳面な方はかかりにくい印象があります。
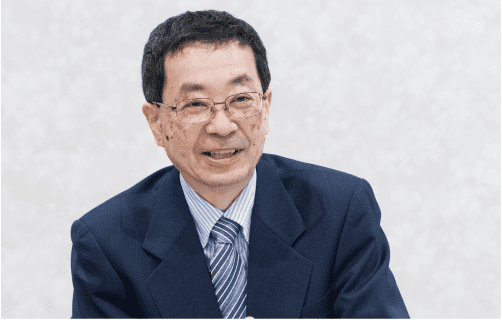
田尾風呂場ではシャワーのミストを吸い込む可能性がありますが、実はシャワーヘッドまでしっかり洗浄している方が少ないのですね。患者さんへの疾患説明の際に必ず風呂場の話をしますが、なるべくシャワーヘッドも掃除する、できない場合は掃除の際に勢いよくシャワーを流さないこと、必ず換気をして終了後しっかり乾燥することを伝えています。
原田原因菌は土壌中にもおり、ガーデニングや家庭菜園をする患者さんを何度か経験したため、趣味についても問診で確認しますね。
司会診断後経過観察となった場合、その後、治療の開始はどのように判断しますか。
田尾症状表15)を繰り返す方、血痰や微熱が出るようになった方、数ヵ月単位でも体重減少を認める場合は進行を疑います。一方、検診で指摘された方などはほとんどが無症状で、痰が出ず喀痰検査に苦労し、結局経過観察となります。ただ画像所見で明らかに肺NTM症を疑う場合は、少なくとも半年に1回はフォローしながら、症状の程度に応じて治療導入を検討します。
藤田私も微熱や体重減少に注意しつつ、血痰が出る方は即治療開始を考慮します。また胸部X線検査を定期的に実施し、特に肺MAC症で空洞病変を認める場合は治療開始の目安にしています図36-8)。ただし若い方には積極的に治療を行うものの、80歳以上の高齢の方では明らかな悪化を認めない限り積極的には治療しません。
原田経過観察では定期的に喀痰検査を実施しています。咳や痰が増えて痰の中の菌量が増加してきた場合も治療を検討します。
図3
肺MAC症の治療開始時期の
考え方フローチャート
03|治療における
患者コミュニケーションの課題
司会診断が確定しても、必ずしも治療するわけではないという点で、患者さんとの向き合い方が難しいように感じます。
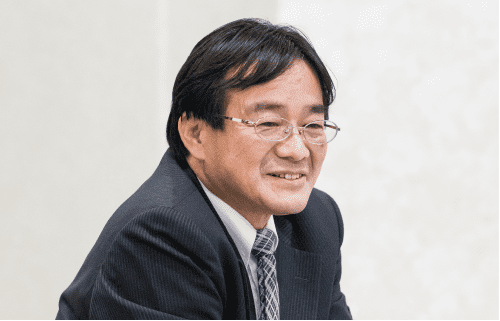
若松実際、標準治療薬はあるものの完治が難しい点は大きな課題です。個々の患者さんで様々な経過をたどるため、診断後すぐに治療とならないケースが多いですし、患者さんも画像所見の異常で紹介された方、症状の悪化で受診した方、開業の先生から治療が必要と紹介されるものの、治療が長期にわたることや薬剤の副作用に対し非常に不安に感じている方など様々です。患者さんにどう向き合うのかが非常に重要で、ご家族の協力も必要です。私は治療について、完治を目指すのではなくQOLの改善を目指すという説明をしています。たとえばこの疾患の患者さんは栄養摂取量が低い方が多いのですが、BMIや栄養摂取量の低値は予後不良との関連が分かっており9)、多職種で介入し患者さんの立場に立って治療することが重要だと思います。
田尾治療導入時にお話しする内容が最も重要です。患者さんのQOLを低下させる症状が出てきた際に、治療によって進行が止まる可能性がある、副作用にも十分注意する、という点を説明し、納得を得て治療を始めるのが実際のところではないでしょうか。自分の家族ならこの治療を勧めますよ、と説明することもあります。
原田「治らない」と言うとショックが大きいですが、たとえば高血圧や糖尿病ならそこまでショックを受けないと思います。そう考えると、この疾患も高血圧や糖尿病と同様に長くつき合っていきましょう、とお伝えすることで納得を得やすいのではないでしょうか。
若松私は、1回の診療ではなく何回かに分けて、繰り返しご家族にも一緒に話すようにしています。
原田この疾患は一般的に進行が緩やかなため、受診のたびに少しずつ話をしながら、患者さんの納得を得たうえで治療をすることができます。抗菌薬を1年以上服用するのは患者さんにとってかなりのストレスです。特に無症状の方には、年単位で少しずつ進行するという話をして納得を得るようにしています。その時納得されなくても、症状の出現や画像所見で悪化を認めた場合は検査結果を見せて説明すると、治療を希望する方が多い印象です。
藤田この疾患は患者さんと話をすること自体が治療だと考えています。当院には、他の病院で治療を勧められセカンドオピニオンとして受診される方もいますが、なかには治療しなくても大丈夫と言って欲しくて、ずっとドクターショッピングをしている方がいます。こういう方はご自身で治療しないと決めているため、数ヵ月おきに経過観察を続けます。ただ、当院が大学病院だからかもしれませんが、受診して話をすること自体が安心感につながっているようです。
原田患者さんとの信頼関係を築いていくことが大事で、関係が築けていれば治療を検討するタイミングで説明した際に納得を得やすいと思います。
04|福岡地区における
肺NTM症診療の連携と課題
司会ところで福岡では肺NTM症治療の連携を行っているそうですね。
藤田はい。一つは肺NTM症のレジストリとして福岡での症例、菌、画像を前向きに集めて検討するもので、肺MAC症は現在症例登録期間と追跡が終了し解析中です。また肺M.abscessus症も現在症例を集めている最中です。肺M.abscessus症は九州・沖縄で多く、進行が早く難治です表210-12)。さらに一般的にNTMはヒトからヒトに感染しませんが、M.abscessusは海外報告でヒトからヒトに感染する可能性が示唆されており13)、その真偽と肺M.abscessus症の治療法をこの研究で明らかにしたいと考えています。一方プライマリ・ケア医との連携という点では、基本的に通常の治療は開業の先生にお願いし、重症例は大学や専門施設で診る流れを作りたいと考えているところです。
田尾当院も開業の先生に参加いただく勉強会を年に数回実施しており、疾患・病態などの説明と連携を心がけています。
司会プライマリ・ケアの先生との連携に課題はありますか。
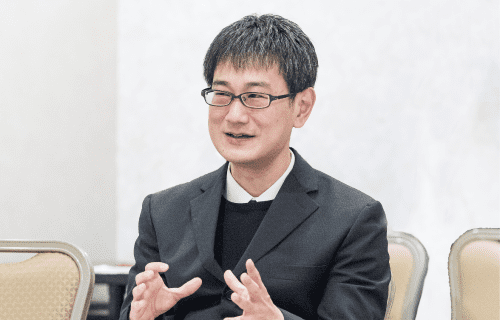
原田たとえば重症例で注射による治療を週2回、3ヵ月程度継続することがあり、毎回当院への受診が困難な方は、開業の先生に注射を依頼することがあります。患者さんのご自宅近くのなるべく呼吸器科や感染症の専門医と連携する形をとっていますが、なかには疾患の認知度の低さや専門医でないと難しいという理由で治療拒否されることもあり、結果的に当院をずっと受診している患者さんも多いのが実情です。
若松開業の先生が使い慣れない薬剤もあるため、当院のような専門施設で治療を導入してある程度軌道に乗ったときに、お願いするのは難しい面もあります。
田尾治療が数年続く場合、そのまま専門施設での治療を希望する患者さんは少なくありません。受診頻度を徐々に減らし、開業の先生を紹介して処方をお願いする、当院では半年ごとに経過を診るといった対応をする方もいますが多くはないですね。
藤田肺NTM症は画一的な治療で治療成績が得られる疾患ではありません。大まかな方針のもとオーダーメイドのような治療で全人的にサポートする必要があり、本来は開業の先生向きの疾患だと思います。また大学病院や専門施設とプライマリ・ケアにはそれぞれの役割分担もあるため、連携を進めつつ、患者さんにも専門施設でなくとも十分治療が可能だと理解いただく必要があるでしょう。
表2
肺M.abscessus症の特徴
05|肺NTM症診療における
現在の取組みと今後の展望
司会最後にそれぞれのご施設で現在取組まれていることや今後の展望についてお話しいただけますか。
藤田大学病院の責務として日常臨床とともに疾患啓発と新規治療の開発が大きな目標です。引き続き開業の先生との研究会を開催するとともに、できるだけ早期に患者会を立ち上げたいと考えています。また新規治療の開発も退官までの目標です。
田尾私は療養所時代から結核、多剤耐性結核患者さんの手術に長く携わった経験があり、当院の呼吸器外科も癒着の激しい肺の切除術などを得意としています。肺NTM症では、重症化し空洞が限局している症例や気管支拡張症が広範囲に及ぶ症例には積極的に手術介入して薬物治療期間を短縮し、QOL低下を抑制する取組みをしており、今後も続ける予定です。
若松我々は患者さんの予後や死亡に関連するリスク因子を継続的に調べており、その中で栄養状態との関連9)が分かってきたため、栄養士や薬剤師、理学療法士を含む多職種での対応を今後さらに充実したいと考えています。肺NTM症は長期に診ていく疾患で患者さんの話をよく聞く必要がありますが、医師だけでは不十分な面もあります。多職種で介入して患者さんからより多くの話を聞き出し、患者さんに寄り添いながら極力症状がなく生活に困らない治療を行っていきたいです。
原田当院は高度先進医療をしており、肺NTM症は他の診療科、たとえば臓器移植のスクリーニングでみつかるケースや、生物学的製剤を使う関節リウマチやクローン病の患者さんなど、当科とは無関係の院内紹介も多いため、院外院内問わず役に立ちたいと考えています。また開業の先生とも今以上に患者さんのフォローをお願いするなど、さらなる連携に期待を持っています。
司会本日は長時間にわたり、疾患のことだけではなく、普段先生方がどのようにご苦労を抱え、患者さんと向き合っておられるかも伺うことができました。ありがとうございました。