座談会

藤田 次郎 先生
琉球大学大学院
感染症・呼吸器・
消化器内科
(第一内科)教授

大湾 勤子 先生
独立行政法人 国立病院機構
沖縄病院副院長、緩和医療科、
呼吸器内科

金城 武士 先生
琉球大学大学院
感染症・呼吸器・
消化器内科
(第一内科)助教

長野 宏昭 先生
沖縄県立中部病院 呼吸器内科
近年、肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)患者が急増していますが、国内での疫学的特徴や診療体制などには地域差があるといいます。今回は沖縄県で感染症診療に取り組まれている先生方をお招きし、肺NTM診療の現状や沖縄地区での取組み、今後の展望などを伺いました。
開催日:2021年12月11日、開催場所:ロワジールホテル那覇
01|国内における肺NTM症の現状と沖縄地区の特徴
司会近年、国内では肺NTM症が増加していると聞きます。まずはこの背景や原因について教えていただけますか。
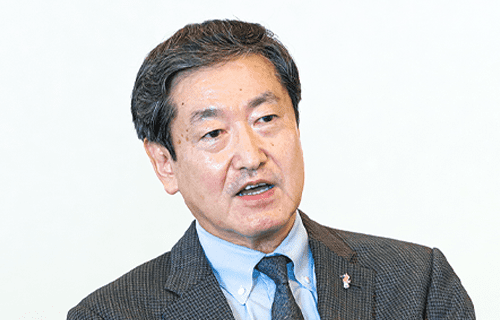
藤田1980年代までは、かつて抗生物質のない時代に肺炎で十分な治療を受けられなかった方が高齢になり呼吸器感染症に罹患する例が多くみられました。しかし1990年代から胸部CT検査が普及して、抗酸菌感染症やびまん性汎細気管支炎の診断が可能になるなど、診断技術と抗菌薬の進歩に伴い呼吸器感染症の構造が大きく変化し、肺NTM症がクローズアップされてきたのです。また、日本では2014年に肺NTM症の罹患率が結核の罹患率を上回っています1)。結核は治療が確立され治癒が可能であるのに対し、肺NTM症は治療期間が長く治癒も難しいことから臨床的重要性がより大きくなっており、これは「日本結核病学会」の学会名を2020年に「日本結核・非結核性抗酸菌症学会」に変更した点にも表れています。
大湾肺NTM症の原因菌は肺の損傷部位につきやすいため、高齢者の増加により疾患が増加した面もあると思います。当院でも60~70代がピークです。
金城そうですね。現行の治療薬の効果が十分でなく治癒が難しいため、治癒できない患者が徐々に蓄積し、高齢化に伴い死者数も増えている状況だと思います。
大湾一方で特に既往歴がない中高年の女性でも増加しています。NTMは浴室やシャワーヘッドなどの水回り、土壌に存在しており表12、3)、原因のすべてではありませんが、ガーデニングや入浴が好きといったことが関係しているかもしれません。
司会沖縄の地域的な特徴はありますか。
藤田日本では肺NTM症の原因菌種の約90%がM. aviumとM. intracellulareを2つ合わせたMACで、北に行くほどM. aviumが、南に行くほどM. intracellulareが多い状況です図11)。一方、沖縄ではM. abscessusが本土と比べ非常に多いのが特徴です。
長野M. abscessusは沖縄のほか台湾や韓国など東シナ海を囲む地域で多い傾向がわかりつつあり、我々が行った疫学研究では県内のNTM陽性患者416例のうち30.5%、さらに肺NTM症と診断された患者の36%でM. abscessusが検出されました4)。米国でも沿岸部の地域に多いという報告があり5)、湿度など気候の影響の可能性も考えられるのではないかと考えています。
表1
NTMの生息環境
図1
肺MAC症の原因菌種の国内分布
02|肺NTM症の診断・治療について
司会診断技術向上の一方で、肺NTM症は発見されにくいとも聞きます。

金城肺NTM症に特異的な症状はありません。CT以外で初期病変をみつけるのは困難ですが、日本ではCTが普及しているため、喘息などの基礎疾患がないにも関わらず咳や痰が続く場合は、CTを撮ることが肺NTM症を疑うファーストステップだと思います。また血痰、喀血は進行の目安になります。肺NTM症は几帳面な方に多いといわれ、当院でも「何月何日、一円玉くらいの血痰が出た」など、紙に書いて外来で1ヵ月の報告をされる方がいらっしゃいます。血痰が出ればCTまで撮ると思いますが、少し咳と痰が出る程度では精査されず、経過観察になるケースがあるかもしれません。
大湾CT所見は診断をする上で非常に重要で、日本ではCTが撮りやすいので、疾患名の知名度が上がり診断されやすくなりました。そして痰の量が増えたり血痰や微熱が出たりといった、以前より増加した症状をもとに精査し、悪化を認めれば治療を検討する流れになります。長くつき合う疾患のため、薬物療法とともに患者の栄養状態や呼吸リハビリの取組み状況、痰を出すためにどう工夫しているかなどを確認しサポートする必要があります。実際は診断よりも治療開始のタイミングの方が難しいと感じます。
司会肺NTM症を疑った場合の検査についても教えていただけますか。
藤田MACとM. abscessusでは画像所見が異なるため、CT所見で疑われる場合は喀痰を採取し、PCRで菌種を同定するのが主な検査・診断の流れかと思います。
金城肺NTM症は感染症であるため、画像所見から疑われる場合はNTMの菌を証明しなければなりません。通常、喀痰中のNTMの有無を調べ、2回証明された場合に原因菌と判断し肺NTM症と診断します表26)。ただ、NTMのうちMACはPCR検査で同定できますが、沖縄に多いM. abscessusはじめ、MAC以外の菌種は質量分析法が必要です。さらに質量分析でも同定できるのはNTMの約7割です。そこで、現在大阪大学との共同研究で次世代シーケンシング技術を用いた高速・高精度の菌種同定法を開発しています。実際にこの方法で新種の発見やこれまで同定できなかった菌の同定が進んでおり、今後NTM症に対する理解がより深まることを期待しています。
表2
日本における肺NTM症の診断基準
03|治療開始タイミングと
患者説明のポイント
司会治療開始のタイミングが難しいとのことですが、どのように判断されるのでしょうか。

大湾肺MAC症の場合、通常薬物治療は経口薬3剤を併用し、排菌陰性化後最低でも1年間は継続します7)。複数の薬剤を長期間継続するため、まず対象の患者が治療の継続が可能かどうかを症状や重症度から見極めます。症状の強い方には積極的に治療を勧めますし、2020年に改訂されたATS/ERS/ESCMID/IDSAガイドラインで、以前は経過観察をしていた方に対しても積極的な治療が推奨されるようになったこともあり8)、治療が継続できそうと判断した場合は、以前より積極的に提案しています。
長野肺MAC症は一度菌が検出されても約5割が自然治癒するという報告もありますが9)、治療が必要な方には完治を目指すより病勢や症状をコントロールし、長くつき合う疾患であることをご理解いただく必要があります。肺に空洞病変がある場合や血痰などの自覚症状が続く場合、肺の3分の1を超える陰影がある場合は積極的に治療を勧めます。逆に陰影が軽度の方、自覚症状が乏しい方、また75歳以上の高齢の方は薬剤の長期服用が副作用含め身体の負担になるため、よく話し合って治療を選択する必要があるでしょう。NTMは結核と違いヒトからヒトへ感染しないため、治療を続けながら家族との日常生活や仕事も続けられることを説明し、その上で治療を希望する方に行う形になると思います。
司会患者への説明で工夫されていることはありますか。
大湾「治らない」と言うと治療へのハードルが上がりますし、治療開始後も薬剤が負担になってきたり画像所見に変化がみられないとがっかりされたりもします。しかし排菌は確実に減ってくるため、「菌が減っているからもう少し頑張ってみましょう」と励ましながら継続します。一方、菌が完全になくならなければ努力が報われないと感じる方もおられ、継続が難しい方には休薬を提案しつつ、筋力低下を防ぐために体重を落とさず栄養をしっかり摂るよう指導するなどしています。

長野中には結核と誤解されている方、急激に重症化するのではと非常に心配される方もおり、「必要以上に恐れることはないけれども、親しき隣人としてつき合っていく必要がある」と説明しています。我々医師や専門家はつい理路整然といろいろ説明しがちですが、患者の不安や苦しみをまずは受けとめ、否定しないことが重要であり、常に患者の味方であることをご理解いただくのが一番大事だと思います。また患者の生活に悪化原因がないか確認することも重要です。以前肺MAC症で排菌量や肺の画像所見の悪化が続く方がおり、生活状況をよく聞くと、ペットの犬を毎日洗い、その風呂場が高湿度でカビだらけでした。あるときその犬が亡くなり洗う機会がなくなった結果、病状が急激に改善したのです。それ以降も、生活について深堀りして聞くことを心がけています。
金城治療開始前の患者とのコミュニケーションは非常に重要ですね。薬物治療の限界を説明しつつ、治療を躊躇する方には毎回時間をとってゆっくり話をし、少しでも治療に前向きな姿勢があればしっかり促し治療に進めます。CTで改善を認めなくても、「悪くなっていない」という伝え方にするなど工夫しています。
藤田結核の場合は専門病床に隔離することもあり、治療に対する患者のモチベーションが明らかです。一方、NTMの治療は隔離が必要なく、良くなったり悪くなったりし、当然薬剤の副作用の問題もあります。患者からの本当に治るのかというプレッシャーも強く、なかなか治療が難しい面はあります。
04|沖縄地区における
肺NTM症診療への取組み
司会沖縄での診療や連携についても何か特徴はありますか。
藤田抗酸菌が検出された方は基本的に県内で結核診療が可能な病院に紹介されます。沖縄本島で結核病床があるのは沖縄病院と当院(琉球大学病院)だけで、当院は4床しかないため、ほとんどが沖縄病院に紹介され患者が集まる状況です。
大湾そうですね。紹介元または当院でスクリーニング検査を行い、結核であればその治療をしますし、NTMの場合は経過観察となります。紹介元の医療機関にお返しすることもありますが、多くは当院で継続するため患者数は多いです。この疾患は病院間で連携を取り、ある程度集約した方が患者も説明や治療内容を確認しやすいと感じており、実際そういう状況になっていると思います。
長野沖縄の病院は米国医学の影響を受けていることもあり、救急室や外来、病棟で発熱がある方には積極的に喀痰のスメア・培養検査を行っています。そのため他地域に比べると早い段階でNTMを発見できている可能性はあります。また県内の専門医同士も、治療困難なケースがあれば直接相談したり環境調査に出向いたりするなど、互いが協力し勉強できる環境にあります。
藤田もともと県内の医療機関のネットワークそのものが強固で、連携は確立されているといえるでしょう。沖縄は戦後初めて開設された病院が大学病院ではなく沖縄県立中部病院で、当初は米軍の医師が指導に当たっていました。日本はドイツ医学を取り入れているため、感染症診療は呼吸器感染症、泌尿器感染症など科ごとに分かれていることが多いのですが、沖縄では臓器にかかわらずすべての感染症を診ます。ドイツ医学ではグラム染色などもあまり行いませんが、沖縄ではグラム染色や抗酸菌染色をあたり前のように実施しており、診療自体が全く違うのです。沖縄の感染症診療は日本一だと自負しています。
金城長野先生が紹介された疫学研究の際も、県内の呼吸器専門施設を中心に私と長野先生が一緒に訪問するなどし、そこの呼吸器専門医と情報交換もしています。県内のNTMの状況について理解いただけますし、患者の紹介を受けることもあり、我々の研究自体も連携強化の一助になっていると思います。
05|肺NTM診療における今後の展望
司会2020年は学会名の変更、2021年は肺MAC症の治療薬アリケイスが発売され、肺NTM症診療にも変化がみられます。最後に今後の肺NTM症診療の展望についてお話しいただけますか。
藤田アミカシン自体は非常に古い薬剤ですが、今回リポソーマル化により肺でのAUCが血漿の約1,700倍、マクロファージへの取り込みが遊離型アミカシンの約4倍に増加しました図2(in vitro)10)。既存薬剤の剤形と投与方法を変えることで、最もターゲットとする肺のマクロファージ内に高濃度で届くことに非常に驚くとともに期待しています。
大湾実際にアリケイスの専用吸入器「ラミラ®ネブライザシステム」を試しました図3。毎日洗浄と片付けがあるなど少し面倒な面はあるものの、慣れれば問題なく使用できると思います。新しい選択肢としてぜひ取り入れたいと考えており、看護部、薬剤部、検査科と一緒に勉強会を始めています。多職種で協力しないと患者への提供が難しい面があるため、近々チームも作る予定です。
長野これまで治療の選択肢が限られていた中で新しい薬剤が増えたことは希望の光であり、大切に使用したいと考えています。医師だけではなく、薬剤師や看護師にも力添えいただき、多職種によるきめ細かなサポート体制を作ることができれば、患者が継続し実際に効果を得ることも可能だと思います。
金城「治せます」と断言できない疾患のため、肺NTM症に関わる医師には閉塞感がありましたが、新薬の登場はNTMに関わる全医師のプレッシャーを軽減してくれる朗報だと思います。対象患者は多くなく、個々の病院で診療体制を構築するのは難しい面がありますので、沖縄病院でチームを発足するという取組みはすばらしいと思います。
藤田そうですね。この薬剤の使用や患者指導には多職種の協力が必要です。適応である「肺MAC症に対する多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者」を見極め表311)、チームが確立された施設に集約するのが沖縄では良いと思います。
司会先生方のお話を伺いながら、沖縄地区では病院と専門医が強固に連携し、肺NTM症診療にチームで取り組まれているという印象を強く持ちました。本日はありがとうございました。
図2
アミカシンのマクロファージへの取り込み