座談会 Young Expert Discussion

君塚 善文 先生
防衛医科大学病院
感染症・呼吸器内科 講師

南宮 湖 先生
慶應義塾大学医学部
感染症学教室 専任講師

朝倉 崇徳 先生
北里大学薬学部臨床医学
(生体制御学) 講師/
北里大学北里研究所病院 医長
(前 さいたま市立病院
呼吸器内科 医長)

古内 浩司 先生
公益財団法人結核予防会
複十字病院 呼吸器センター
肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)は、近年患者数の増加が問題になっている一方で根治できる有効な治療法がほとんどない状況が続いており、さらなる研究や対策の必要性が指摘されています。今回肺NTM症診療の次世代のリーダーともいうべき先生方をお招きし、肺NTM症の診療や研究の現状、課題などを伺いました。
開催日:2022年3月13日
開催場所:小田急ホテル センチュリー
サザンタワー(東京 新宿)
01|肺NTM症の現状と課題
司会近年、国内では肺NTM症が増加していると聞きます。まずはこの背景や原因について教えていただけますか。
南宮まず肺NTM症の疫学ですが、2014年1月から3月に日本全国で実施した疫学調査により、肺NTM症の罹患率が2007年の全国調査以降急増し、2014年の患者数は結核と逆転したことが明らかになりました図11, 2)。この調査の実施背景には、当時医療現場で肌感覚として肺NTM症の増加を感じていたものの、指定感染症ではないために具体的な数が分からないという事情がありました。そこで全国の日本呼吸器学会認定施設・関連施設884施設にアンケート調査を送付し、結核と比較することで肺NTM症の全体像を把握することにしました。調査では6割以上の施設から回答があり精度の高い数値が得られたと同時に、国内の医療従事者のポテンシャルの高さを感じました。
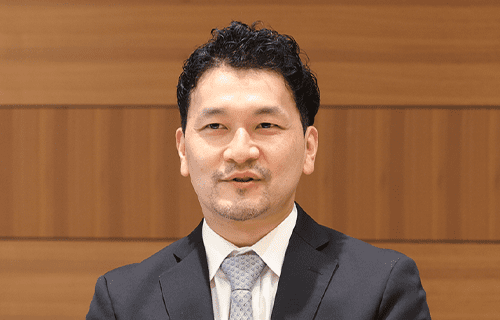
君塚肺NTM症増加の背景には、徐々に結核の罹患率や流行そのものが減少し、逆に肺NTM症の認知が医療界に広がってきたこと、検診などで胸部CTが頻用されるなど診断技術の向上が異常病変の早期発見につながった可能性が考えられます。現場では主に中高年で喫煙歴がない女性や、関節リウマチ(RA)やその他の膠原病など生物学的製剤を使用中の方での増加を感じており、これらは肺NTM症の素因としても知られています図23)。
朝倉NTM症の死亡者数は2020年度に結核を上回りました図34)。実際、結核の診療機会、重症患者を診る経験自体は減る一方で肺NTM症の診療機会は増えており、今後も増加していく可能性は十分あるでしょう。また日本ではCT検査が普及しているため無症状で画像所見が進行している患者の拾い上げができており、日本の肺NTM症患者は海外に比べ軽症で肺機能が維持されている方が多い印象があります。
古内新規診断数で注意が必要なのが、結核の2020年の新規報告数は前年からの減少幅が大きく5)、COVID-19の影響による診断や検査、受診の遅れが懸念される点です。肺NTM症への影響も今後注視していく必要があります。
司会肺NTM症の疾患認知の現状はいかがでしょうか。
君塚20年ほど前まで、結核は他人に感染してしまうため公衆衛生的な問題として重視される一方、肺NTM症は呼吸器内科医の中でも軽視されていたように感じています。現在は肺NTM症の患者さんが治癒せず外来受診をずっと続けることに対し医療者も患者さんも不安や焦燥感が出てきており、時代の経過とともに認知が進んだ面はあると思います。
古内そうですね。医療者の中での認知は確実に広まってきています。さらに一般の方に認知を広げるには、医療従事者向けの専門誌への投稿ではなく別の啓発的な活動が必要でしょう。
南宮この疾患は我々医療者も分からないことが多く、例えば進行しない方もいれば進行する方もおり、目の前の患者さんに5年後、10年後どうなるのか説明することがむずかしいのが実情です。クリアに説明できないこと自体が一般の方での認知を妨げている可能性もあり、今後広報活動や一般向けの啓発活動をさらに広げることが必要です。
図1
本邦における肺NTM症罹患率の
年次推移1)(1980〜2014年)
図2
肺NTM症を引き起こしやすく
すると考えられる素因
図3
結核およびNTM感染症の
死亡者数の推移(2006〜2020年)
02|肺NTM症の治療の実際
司会肺NTM症の治療にも課題が多いと聞きます。具体的にどのような点でしょうか。
君塚治療薬に関しては、本疾患の特効薬とよべる薬剤がなく、現在提唱されている標準治療法が20年以上ほぼ変わっていないことです。また、キードラッグの一つにマクロライド系抗菌薬があり、使用量が多いほど治療効果が高いことは分かっているものの6)、日本では海外に比べ投与量が少ないのが実情です。さらに自覚症状の有無は治療の動機付けの最大因子であり、無症状の方は治療しづらい面もあります。治療開始後も結核であれば半年ほどで治療が終了し、その後経過観察となりますが、肺NTM症は治癒しないケースも多くみられ見通しが立ちにくいのです。
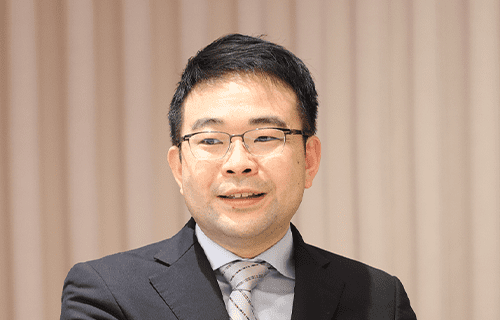
朝倉肺NTM症は治療すべき明確な基準がありません。結核は周囲に感染してしまうことが治療の強い動機付けになりますが、肺NTM症は自然に菌が陰性化する方もおり、全員に治療が必要なわけでもないのです。胸部画像での空洞の存在や喀痰中の菌量は治療開始の参考にはなりますが、個々の患者さんで症状は異なりますし、症状の種類と検査画像、菌量の組み合わせも様々です。当然患者さんの希望もあり、どのタイミングでどの患者さんに治療を始めるか我々も非常に悩ましく、患者さんとお話ししながら個々に決めなければならないのがむずかしい点だと思います。無症状であっても、喀痰から持続的に菌が検出され、画像が経時的に悪化する場合は治療をすすめることが多いです。
君塚そうですね。我々が実施した研究では、軽症の肺MAC(M. avium-intracellulare complex)症で診断後無治療であった患者さんを約7年間経過観察した結果、BMIと肺機能は徐々に低下し、さらに肺に占める結節影や拡張気管支の範囲は徐々に広がっていました図47)。このように軽症でも無治療では確実に増悪するものの個人差はあり、治療を開始するタイミングは非常にむずかしいです。
古内治療開始後も次は治療期間が問題になります。喀痰の菌陰性化後1年という目安はありますが、正確な治療期間は分かっておらず、薬剤の副作用で中断せざるを得ない方もいます。さらに問題になるのが再発です。再発には肺病変に残存していたNTMが再度増殖する再燃と、環境中から新たにNTMに感染する再感染の2種類があり、再燃が約4分の1を占めるため8)、治療が不十分である可能性も考えられます。当院で治療期間の検討を行った結果、培養陰性化後の治療期間が15ヵ月未満の方に比べ15ヵ月以上の方は再発率が低く図5、さらに再発のリスク因子として、治療期間に加え治療終了時のCT上の空洞所見や気管支拡張病変の重症度の高さも関連がみられました9)。これらは経過観察時に注意すべき患者像の参考になると思います。
南宮さらに加えますと、この疾患には重症度の指標となる客観的マーカーがなく、客観的な数値で改善・悪化が判断できません。治療薬の開発を進めるうえでも長期予後に直結するような、かつ臨床研究を行いやすいマーカーやアウトカムを開発していく必要性もあると考えています。
図4
肺MAC症未治療患者における
臨床的特徴の経時的変化
図5
肺MAC症治療による
培養陰性化後の治療期間別再発率
(Kaplan-Meier解析)
03|肺MAC症治療の新たな選択肢、
アリケイス
司会2021年7月に難治性肺MAC症の新たな治療選択肢であるアリケイスが発売されました。医療現場での受け止めについてお聞かせください。
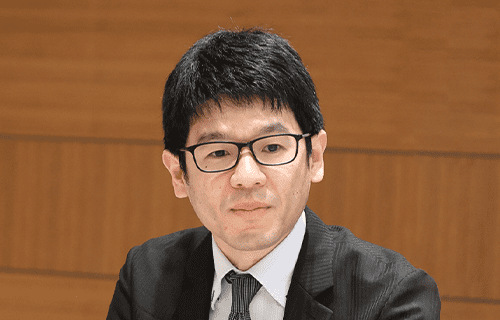
古内アリケイスはアミカシンの吸入製剤で、アミカシン自体はこれまで外来の点滴投与で使用されてきました。ただ肺MAC症治療は長期にわたるため点滴の継続は患者負担が大きく、かといって他に頼る薬剤がない状況でした。今回吸入製剤になり、長期治療継続の視点で使いやすくなったと思います。
南宮肺NTM症で長年新薬が出なかった状況も相まって患者さんの期待の強さを感じます。一方で有害事象も一定数発現するため、その対応が治療継続のためには非常に重要です。我々も勉強中であり、多くの先生方と情報共有しながら少しでも良い治療管理を目指したいと思います。
朝倉アリケイスは難治性の肺MAC症を対象とした無作為比較試験が実施されており10)、従来のHIV患者のデータなどをもとにした治療に比べ、エビデンスレベルの高い治療が行える点でも期待しています。
司会実際にアリケイスの導入状況や今後の課題についてはいかがでしょうか。
古内当院では40例弱の患者さんに導入しました。導入に際しては費用や手間などが問題になるため、外来でしっかり説明し理解を得ることが大前提です。最初は患者さんが3泊4日で入院し、初日に専門の病棟薬剤師による指導を受け、2日目は一緒に操作を、3日目は患者さん1人で行い覚えたら退院という形にしています。後から使い方で困ったという話はなく、きちんと指導し患者さんが慣れさえすれば、手技の面では継続可能だと思います。

南宮当院も約10例の患者さんに入院で導入しました。最初患者さんは自分で操作できるかという不安が強いですが、全員問題なく導入できています。費用面など押さえるポイントが多いため、看護師や薬剤師、ソーシャルワーカーなど多職種による連携とともに、マニュアルやチェックリストを作成し、漏れを防ぐ試みを行っています。
朝倉高齢患者さんでは半年〜1年の治療で呼吸状態や症状が改善する可能性があるものの、併存疾患があったり若年患者さんに比べ症状がなかったりする場合も多く、治療によるメリットと副作用を考慮すると決断が非常に難しいのが実情です。
君塚当院も導入した患者さんはいませんが、導入準備は整ったという状況です。アリケイスは患者指導をする看護師や薬剤師などの教育体制のほか、例えば外来治療中に副作用などで処方を突然中止した場合、高額な薬剤という点でその地域の薬局の在庫管理に影響しないような工夫が必要です。また患者さんの費用負担の面でソーシャルワーカーに公的な補助を案内していただくなど、多職種の横断的なサポートも含めた導入準備が必要な薬剤です。これらの点は課題でもありますが、新たな選択肢が増えたこと自体は非常に喜ばしいと感じています。
04|肺NTM診療における
今後の展望
司会今後の肺NTM症診療の展望についてお話しください。
南宮この疾患の研究と診療を発展させるため、より多くの医療従事者・研究者に参入いただくための器としてNTM-JRCという多施設共同研究の枠組みを作っています。大きな研究をする方がしっかりした研究結果を生む可能性が高いですし、施設の枠を超えて研究・診療の知見を積み上げていくことが非常に重要ですので、ぜひ多くの先生方に参入、活用いただきたいですね。私自身も肺NTM症になりやすい体質や遺伝的要因に興味があり共同研究を行っています。肺MAC症患者の遺伝子と対照者の遺伝子型を網羅的に比較したゲノムワイド関連解析では、細胞内外のイオンやpHの調整に関わるCHP2(calcineurin-like EF-hand protein 2)遺伝子の重要性が示唆され11)、今後は機能解析や海外の研究者とのさらに大規模な研究を予定しています。
朝倉最近、肺NTM症の特徴の一つとして気管支拡張が注目されており、国内の研究でも肺NTM症に合併する肺疾患の中で気管支拡張症が多いことが報告されています図612)。現在、国内の肺NTM症及び気管支拡張症患者の解析や、米国との共同研究で両疾患の関連を分子生物学的に解析する研究に取り組んでおり、何か役立ちたいと考えています。私も今後の肺NTM診療は今まで以上に様々な施設や様々な医師が参加し、日本全体で診療体制を整えていくことが重要だと思います。
古内私は特殊な病院におりますので、今日は異なる施設ながらも専門的な目線を持つ先生方と意見を交わすことで、出てくる意見や目線の違いを感じることが多々あり勉強になりました。医師同士が連携しながら一般の方に対する啓発もしっかり行っていくことが大事だと改めて感じました。
君塚そうですね。現場の医師が各々興味のあることを少しずつ解明し、それが集まることで疾患がより明らかになり治療につながるという期待や希望を感じ、私も非常に前向きな気持ちになりました。肺NTM症は世界中の先進国でも増加しています。日本で明らかになったことを分かりやすい媒体にし、専門医以外や学会のガイドラインなどに提言することで最新の治療を広く啓発していくことが今後の課題だと思います。これからも頑張りましょう。
司会先生方の活発なご意見を聞き、肺NTM症診療では施設の異なる先生方との連携も非常に大切だと実感しました。本日はありがとうございました。