座談会

井上 純人 先生
山形大学医学部附属病院 第一内科
呼吸器内科 病院教授

関 雅文 先生
埼玉医科大学医学部 国際医療センター 感染症科・感染制御科 教授
(前 東北医科薬科大学病院 感染症内科 教授)

長島 広相 先生
岩手医科大学附属病院
感染制御部 部長

山田 充啓 先生
東北大学病院 呼吸器内科 講師
肺MAC症に対する標準治療はクラリスロマイシン(CAM)、エタンブトール(EB)、リファンピシン(RFP)の3剤併用療法ですが1)、1997年の米国胸部疾患学会(ATS)ガイドラインに標準治療として記載2)されて以降、20年以上変化がない状況が続いていました。そうした状況下2021年7月に、前治療で効果不十分な肺MAC症に対して、アリケイス®吸入液590mgが登場しました。そこで今回、東北地方の呼吸器・感染症専門医の先生方をお招きし、肺MAC症治療の現状や今後の展望などを伺いました。
開催日:2022年4月8日
開催場所:ホテル メルパルク仙台(仙台)
01|肺NTM症診療の
早期診断における課題
司会肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)では早期発見がむずかしいと聞きます。まずはその要因について教えていただけますか。
関1つには疾患認知の問題があり、医師のなかでも特に呼吸器以外では肺NTM症を知らない、あるいは聞いたことはあっても「結核の仲間で治療が必要ない疾患」というイメージがあると感じます。何よりも無症状の方が一定数おられ、医師も患者さんも重篤なものとして捉えにくいのだと思います。
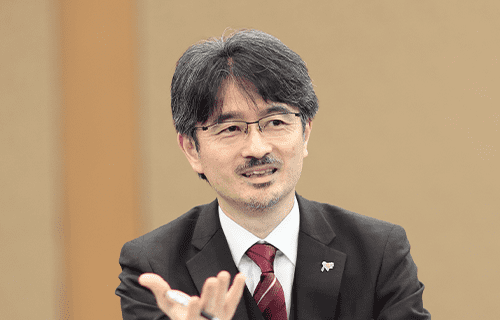
井上疾患経過が非常に長いという点も問題にされにくい要因だと思います。例えば当院に紹介受診される方のなかには、実は何年も前から肺に影はあったもののあまり変化がないため問題視されず、数年経ってみると進行していたというケースは少なくありません。また特徴的な症状がないため図13, 4)、患者さんに気づかれにくく、長期間にわたり咳嗽などの症状が続いていてもそれが普通の状況になっているケースもしばしば経験します。このほか、大学病院などでは医師が異動のために交代することがあり、年単位で患者さんをフォローできず、数年前と今の状況を比較しにくい状況もあると思います。
司会一般内科などではより診断や判断がむずかしいのでしょうか。
関診断自体より、治療すべき患者さんや治療を開始する時期の見極めがむずかしいと思います。確定診断自体は基本的には喀痰検体で2回菌を証明できれば可能です。ただし患者さんによっては痰が出ない方もおり、肺MAC症だとは思いつつも治療まではいかないケース、あるいは痰が出て確定診断できた場合でも、無症状や症状が穏やかな方は経過観察が続くケースが多いと思います。
司会痰が出ない場合はどうされるのですか。
井上ネブライザーによる食塩水の吸入や、ラングフルートという笛のようなものに息を吹き込むことで喀痰誘発を行います。確実に診断をつけた方がよい場合は、気管支鏡検査を行うこともあります。
長島当院はラングフルートを装備していないため、3%食塩水を吸入していただくことがあります。
関私も吸入誘発を試すことがありますが、気管支鏡検査の方が喀痰検体より検出感度が高いため、個人的には気管支鏡検査を実施することが多いです。これらの検査で菌の証明がむずかしい場合でも画像所見から肺MAC症が強く疑われる場合は、抗MAC抗体検査も補助診断として有用だと思います。
山田肺NTM症を疑い喀痰検体が得られない場合でも、抗MAC抗体検査で陽性が出ると肺MAC症である可能性が高いと考えられます。気管支鏡検査は侵襲的で患者さんにとって辛い検査ですが、MAC抗体陽性という証拠があると、医師側は気管支鏡検査の必要性を説得しやすくなり、患者さんも検査の決断に踏み切る材料になります。
司会治療の判断はどのようにされていますか。
井上診断がつかない場合や診断時点で治療がすぐに必要ないと判断した場合は、基本的に経過観察を続けますが、肺の影の増加や症状の発現がみられた時は治療を検討するタイミングだと考えます。
山田例えば30~40代の方がこの先50~60代になった時に進行し、肺の力がかなり落ちるような状況になると人生にとって大きな問題になり得るため、経過観察から治療の判断は、患者さんの年齢によっても異なりますね。
長島特に一般内科の先生方には、肺NTM症を疑うような影があれば一度専門医に相談していただきたいですね。経過観察でよいケースなのか、また、その際注意すべきポイントなどを確認いただいたうえで経過をみていただければ、診療水準の向上にもつながると思います。
関肺の空洞はかなり進行した状況を示し、薬剤の効果も低下するため、空洞が生じる前に早めに診断し治療を開始したいと考えています。また関節リウマチなどの基礎疾患がある方はリスクが高いため表15)、治療が必要な状況であることも今後啓発していく必要があると思います。
図1
NTM症の臨床症状
表1
肺NTM症の宿主感受性に
関連するリスク因子5)
02|肺MAC症治療における課題
司会肺MAC症治療には標準治療が定められているものの課題も多いと聞きます。具体的にどのような点があげられますか。
山田同じ呼吸器分野である肺がんでは治療が瞬く間に進歩しているのに対し、肺MAC症は標準治療が定められた20年以上前から現在も治療がほとんど変わっていません。経口薬3剤による併用療法が基本ですが、排菌停止に至る患者さんは限られており、満足できる治療効果が得られないのが実情です。
長島従来の標準治療は何らかの副作用が問題となるケースもみられ、治療開始後、数年の間に減量や休薬、時には中止せざるを得なくなることもあります。また、1回に服用する錠数が多く、特に進行例にみられるやせ型で体重減少が著しい方では「薬でお腹がいっぱいでご飯が食べられない」という訴えが聞かれることがあります。さらに、高齢の方には基礎疾患が多く、他剤との飲み合わせに注意し薬剤の調整が必要になるなど、非常に悩ましいです。
司会治療の継続自体もむずかしいということですね。
井上はい。治療期間の目安は菌陰性化後1年程度とされていますが 図21,2,6,7)、治療を始めてもすぐに効果を実感できるわけではないため、副作用と効果を天秤にかけると継続がむずかしい面があります。初期の副作用などを乗り越え2年ほど治療し、「ある程度は落ちついた」という状況になった時点でどうしても一度止めたいという方は止めて様子をみることはありますが、ある程度若い方であれば、「60代、70代になった時にひどい呼吸症状で苦しむのはよくないので治療を頑張りましょう」と先の展望をお話しし、できるだけ継続するようにしています。
山田肺MAC症は治療終了後も再燃・再感染を起こしやすいという問題があります。その理由は明らかではありませんが、薬物治療だけでなく環境整理もしっかり行う必要があるのかもしれません。
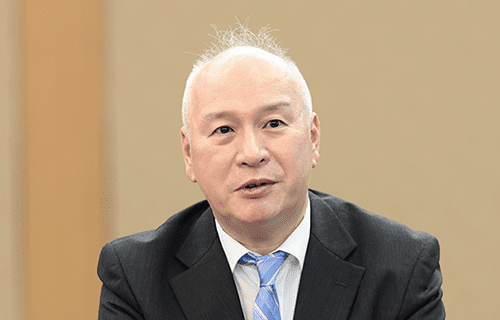
関現状では環境への介入効果も明らかではありませんが、土壌が共通するある特定の地域で患者さんが多いということは経験します。最近はその地域の方々が畑仕事や園芸などの際にマスクを着用するようになるなど注意し始めており、今後その効果が見えてくることを期待しています。
図2
肺MAC症治療終了時期と
経過観察
03|吸入治療薬アリケイスの
位置付けと期待
司会昨年(2021年)に、吸入治療薬であるアリケイスが発売され、先生方はすでにお使いだと聞きました。本剤の印象や現在の導入状況を教えていただけますか。
山田アリケイスは、ラミラネブライザシステムにより直接肺に薬剤を届けることができ、さらにリポソーム技術により感染細胞であるマクロファージに効率的に取り込まれるため8)、薬剤送達の面で工夫された薬剤だと思います。当院では1例に導入し始めたところですが、関連病院では効果がみられている例もあり、標準治療では効果が不十分でご自身の状況を理解されている方に対しては、今後しっかり説明し使用機会を増やす必要があると考えています。
関私は従来の標準治療を何年実施しても菌陰性化せず、患者さん自身も非常に困っていた4例に導入しました。難治性の方ばかりで菌が減らない方はいますが、逆に減少を認めた方もおり、今後治療薬としては選択肢のひとつになるのではないかと期待しています。
井上当院では今2例に導入しています。このうち1例は標準治療に追加治療をしても悪化が続いていた方で、追加していたアミノグリコシド系薬は点滴か筋肉内注射しか投与方法がなく、通院自体も大変な状況でした。アリケイスは自宅で吸入できるため、注射を何度もしなければならなかった状況を克服できる面でも有用だと思います。
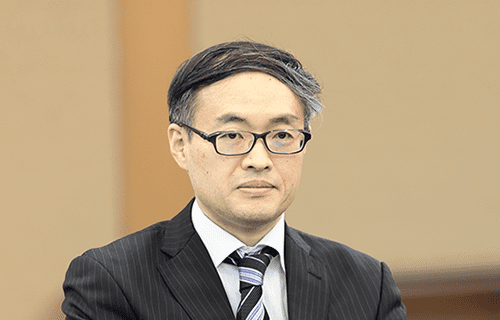
長島そうですね。私の出張先の病院にも1例アミノグリコシド系薬の筋肉内注射からアリケイスに切替えた方がおり、その方も注射の痛みが辛かったのが切替えによって本当に楽になったそうです。そういった意味で、痛みがないのはすばらしいですし、患者さんも喜ばれていました。
司会アリケイスの導入には院内での連携が重要とも聞きます。
長島吸入器の操作は薬剤師が主体となって指導しており、本当に助けられているという一言に尽きます。特に高齢の入院患者さんでは、このご時世ご家族が院内に立ち入れない時期もあり、薬剤師が長い時間をかけて丁寧に繰り返し指導しました。退院後何度か外来で指導が必要なケースはありましたが、患者さんもかなり慣れ、現在も治療を続けています。

山田院内連携は非常に重要です。当院も薬剤師による薬剤管理、患者指導や外来通院管理の面では看護師の努力にも助けられました。また、費用の面でソーシャルワーカーなど社会福祉に携わる職種が支援に関わってくれたことも大きいです。
井上薬剤師、看護師、ソーシャルワーカーとの連携は病院の総合力が問われるところですが、当院では昨今さまざまな新薬を導入するなかで患者指導の重要性が話題になったこともあり、比較的取り組みやすかったですね。
関アリケイスの導入には医師以外の職種の方々のバックアップが必要です。患者さんの教育入院が必要になることもありますが、スタッフはむしろ喜んで取り組んでいる印象もあり、チーム医療は新しい感染症診療の形としても前向きに捉えています。
04|肺MAC診療の今後の展望
司会最後に今後の肺MAC症診療の展望や、この領域で取り組むべきことなどお聞かせいただけますか。
関アリケイスという新たな治療選択肢を臨床の場でどのように生かしていくのか、それは大変重要な課題です。しかし施設ごとでは経験できる症例に限りがありますので、たとえば、地域ごとや学会などを通じてアリケイスの症例を共有して、今回のように議論できれば、学べることがいろいろとあると思います。そういった機会をぜひ、つくっていきたいと考えています。
山田私が大先輩から聞いた「息は生きる」という言葉があります。生きるためには絶対に息が必要ということですが、従来の肺MAC症治療には「標準治療をしても菌が消えないのは、医者が悪いのでなく菌が悪い」「そういう菌に感染してしまった患者さんが不運」といった、どこかあきらめる気持ちがありました。しかしアリケイスの登場で、臨床試験の結果だけではなく図39)、実際に菌陰性化を達成した患者さんも経験し、従来治療との効果の差を感じています。このような疾患でも治療が進歩していることを目の当たりにし、あきらめずに診療していくべきとの勇気を得られましたし、現在COVID-19の影響で呼吸器内科や感染症科は大変な状況にありますが、この分野を診る後輩医師が増えるように頑張りたいと思います。
井上アリケイスの導入に多くの職種が関わることは、感染症診療に多くの方が関心を持つことにつながり、肺NTM症に対する社会的な関心の向上や、若い先生方や学生が呼吸器内科医を志すきっかけになることを期待しています。また薬剤師や看護師にとっても患者さんに直接指導する機会はやりがいにつながると思います。一方で、関先生がおっしゃったように我々がエビデンスを積み上げていく必要があります。各施設でそれぞれが経験した症例を集め説得力のあるエビデンスを作ることができれば、もっと標準化した治療になっていくのではないでしょうか。
長島数年前になりますが、日本呼吸器学会の学術講演会でNTMの講演会場が非常に混み合っていた印象が残っています。一方で、やはり肺がん等と比べますと全体的にNTMをテーマにした会は少なく、一般内科医や我々呼吸器内科も情報のソースが限られています。今後県内でもNTMを周知させる機会を増やすための会の開催などに積極的に取り組みたいと考えています。
司会肺NTM症のよりよい診療に向け、本座談会が地域の連携、さらに広域の連携へとつながるきっかけになればと思います。本日はありがとうございました。
注)各薬剤の効能又は効果、用法及び用量などは、添付文書をご参照ください。