座談会

露口 一成 先生
国立病院機構
近畿中央呼吸器センター
臨床研究センター 感染症研究部長

木田 博 先生
国立病院機構
大阪刀根山医療センター
呼吸器内科 部長

玉置 伸二 先生
国立病院機構
奈良医療センター
副院長

永井 崇之 先生
大阪府立病院機構
大阪はびきの医療センター
感染症内科 主任部長
現行の肺MAC症の標準治療はクラリスロマイシン(CAM)、エタンブトール(EB)、リファンピシン(RFP)の3剤併用療法ですが1)、1997年の米国胸部疾患学会(ATS)ガイドラインに標準治療として記載2)されて以降、20年以上変化がない状況が続き、長年、新たな治療選択肢の登場が切望されていました。そのようななか、2021年7月にアリケイス®吸入液590mgが登場し、徐々に導入事例も増えてきています。そこで今回は近畿地方の呼吸器・感染症専門医の先生方をお招きし、肺MAC症診療の現状やアリケイス導入による治療の変化、今後の展望などについて伺いました。
開催日:2022年4月17日
開催場所:ホテルモントレ グラスミア大阪(大阪)
01|肺NTM症診療の
早期診断における課題
司会肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)では早期発見がむずかしいと聞きます。どのような理由があるのでしょうか。
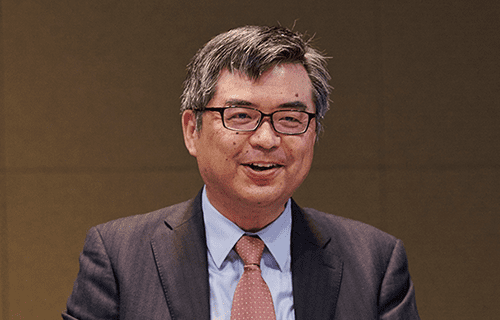
露口近年肺NTM症は急激に増加し3)、最近は開業医から「非結核性抗酸菌症疑い」「MAC症疑い」といった紹介状を受けるなど、一般内科医も含め疾患の認知度が上がってきたと感じます。一方で画像所見上、特に結節・気管支拡張型の場合は胸部X線検査のみでは判別しづらく、また咳、喀痰など症状が非特異的である点は早期発見を妨げるハードルの1つかもしれません。
玉置医療従事者での認知が進んでいることは確かですが、一般の方では診断された方でさえ疾患名が曖昧なことがあります。最近はPET検診や肺ドックなどで散布影が見つかり、肺MAC症疑いで紹介されるケースもあるため、今後さらに認識が深まり、治療が必要な方をピックアップすることが課題だと考えています。
司会診断がむずかしいとされる理由は何でしょうか。
露口診断には原因菌同定のために喀痰検査が最も重要ですが、問題はこの疾患は喀痰が出ない方が多いのです。
永井そうですね。喀痰が出ない空咳の方が多いため、当院ではネブライザーによる生理食塩水の吸引やラングフルート法で誘発喀痰を行うこともあります。
玉置結核の可能性を否定する面でも、できるだけ3日間連続で喀痰の評価をしています。喀痰検査で診断に至らず経過観察の判断をすることもあれば、若年者や治療介入が必要と判断した際は、侵襲的ではあるものの気管支鏡検査で診断することもあります。またMAC抗体検査は疾患を想起するうえで非常に有用であるため、積極的に利用しています。
木田MAC抗体検査は当院で開発された特異度が非常に高い検査法ですが図14)、現在診断基準には含まれておらず確定診断はできません。また本検査の感度は約70%で5)、30%の方は見過ごす可能性があります。一方で、当院の肺MAC症患者約1,000例の検討では培養1回陽性かつMAC抗体陽性であれば、ほぼ診断可能という結論に至っており6)、さらに海外でも培養1回陽性による診断が約4割でなされ、診断基準の改訂を求める意見も出ているため7,8)、今後肺MAC症の診断基準がこの方向に改訂されることを期待しています。
司会診断がつかない場合はどのように対応されるのでしょうか。
永井最終的に治療を進めるか否かが最も重要であるため、軽症例の場合はあくまで「疑い」という形で経過観察することが多いです。しっかりと診断をつけてほしいタイプの患者さんには気管支鏡検査を積極的に行うこともありますが、一方で肺MAC症に非常に特徴的な画像所見があってもMAC抗体は陰性、あるいはMAC抗体だけ陽性といった最終的に診断がつかない例も多く、診断に難儀することは多いですね。ただ、進行自体は比較的ゆっくりであり、当院ではほとんどの方が半年に一度の健康観察としています。
露口ある程度高齢で軽症の場合は、診断がついても無治療、経過観察という選択もあり得ます。ただしその場合は、「将来的に悪化する可能性がある病気だから、必ず定期的に病院に来て検査してください」と伝えています。
木田当院の場合、喀痰検査の結果が出るのが約2ヵ月後になるため、当初は2ヵ月間隔で通院していただき、病状が安定している方、軽症の方は、半年に1回を目安にフォローしています。ただし免疫不全や高齢者、痩せなどは肺NTM症のリスクとされるため図29)、これらに該当する方は特に重点的に経過観察すべきだと思います。
図1
肺MAC症の補助診断
図2
肺NTM症を引き起こしやすくする
と考えられる素因
02|肺MAC症治療における課題
司会肺MAC症治療は、標準治療にも課題があると聞きますが、具体的にどのような点でしょうか。
露口標準治療はキードラッグであるクラリスロマイシンにリファンピシンとエタンブトールを合わせた3剤併用療法が基本で、重症例には注射薬を追加します図31)。問題はこの標準治療で必ずしも治癒に至らない点です。結核では標準治療で約9割の治癒が期待できますが10)、肺MAC症はマクロライドの感受性が確認でき、かつ3剤による標準治療がきちんと行えたとしても治療成功率は6~7割にとどまります11)。また、副作用のために投与中止となる方も少なくなく、1剤が中止になると残り2剤による不十分な治療にならざるを得ないのです。
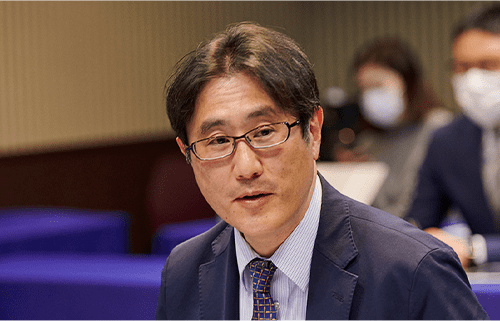
木田さらにこの標準治療では、1回あたり約10錠の服用が毎日1年以上続きます。欧米のガイドラインでは、軽症例には週3回の治療が提案されていますが12)注)、日本ではまだ確立されていません。また、高齢患者さんは合併症のある方も多く、薬物相互作用の問題も出てきます。
永井そして標準治療が無効であった時の次の一手に、標準的なコンセンサスが得られていないことも問題です。
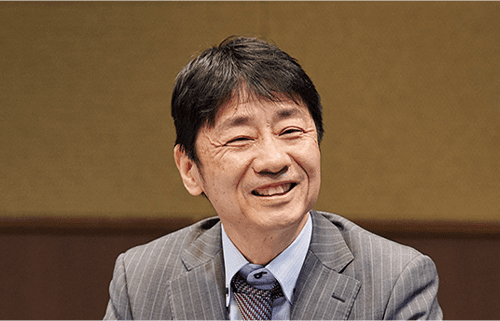
玉置2020年には、アジスロマイシンの適応外使用について、肺非結核性抗酸菌症に対し処方した場合に、審査上認めるとする通知が社会保険診療報酬支払基金より出されました13)。標準治療の1剤としてアジスロマイシンが普及していけば、錠数が減り少しはアドヒアランスや治療効果が改善するかもしれません。一方、重症例にはアミノグリコシド系の製剤を使うべきとされますが、これまでは点滴静注か筋肉注射しかなかったため、通院の頻度などから患者さんの理解が得られにくくなっているのが現状です。
司会環境因子に対しては何か介入されていますか。
露口初診時に土壌に触れる仕事や趣味がないか確認したり、環境因子の説明をしたりはしますが、介入というと土壌をいじる作業をできるだけ避けること、浴室を清潔に保つことを勧める程度です。
玉置確かにどこまで介入するかはむずかしいですね。私も水回りの手入れをすることや、ガーデニングの頻度を控える、といったことしか伝えていません。
永井たとえば浴室のリフォームなどは費用がかかりますし、リフォームをしても1~2年後に再感染することも十分想定されるため、私も何かを強く勧めるということはしていないのが現状です。
木田患者さんごとに環境要因が異なるため、何かを強く勧めることはむずかしいですが、いったん治療が終了した方の再感染を防ぐことは重要です。明らかに土壌や浴室などの環境による再感染を疑う方には個別の対応が必要かもしれません。
図3
日本における
肺MAC症の標準化学療法
03|新しい吸入治療薬
アリケイスの位置付けと期待
司会昨年(2021年)、アリケイスが発売されました。導入状況はいかがでしょうか。
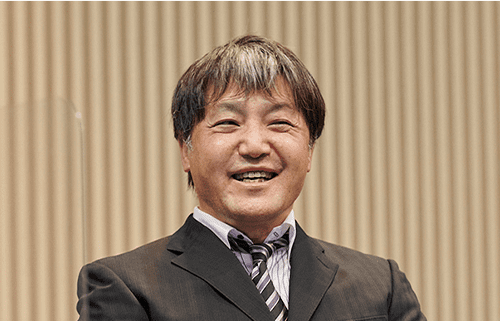
永井アリケイスは器械のメンテナンスを含め患者教育が非常に重要であるため、当院では2泊3日の教育入院で導入しています。当院には肺MAC症患者さんが多くおられますが、毎日吸入となると本人の理解力や同居の方のサポートが必要になりますし、耐性化が進んでいる方もいるため、現時点で導入できたのは難治例でアミカシンに対する感受性が確認できた5例です。今のところ大きなトラブルはなく継続できています。
木田当院では診断から10年以上経つような、化学療法を繰り返しても持続排菌になっている患者さんを中心に10例導入しました。ただ、副作用などの理由で断念したケースがあり、その方々を今後どうするのかが課題と考えています。また、導入直後に見られる嗄声など呼吸器系の副作用の不安を軽減する意味もあり、当院も1週間程度の教育入院で導入しています。
露口当院も導入は1週間程度入院とし、現在50~80代の難治例の12例に導入しました。患者さんには前もって臨床試験で約3割の方が菌陰性化したことを説明する一方で、7割の方では排菌が止まらなかったこともお伝えし図414)、過大な期待を持たせないようにしています。現時点で特に手技や重篤な副作用の発現などによる問題はありません。なかには数日で手技をマスターし入院期間を短縮する方もおり、外来導入が今後の課題と考えています。玉置先生は実際に外来で導入されているそうですね。
玉置はい。これまで9例に導入し、副作用などによる中止例を除く7例が継続されています。当院ではCOVID-19の影響による病棟の状況や病棟でネブライザーを使用するリスク、看護師と薬剤師の業務内容、さらに年単位で吸入が必要である点を考慮し、外来導入としました。実は薬剤副部長が過去にアリケイスの臨床治験に関与しており、外来導入に対しても非常に理解があったのです。導入を考える患者さんにはまず医師が説明しますが、その後の導入決定や具体的な患者指導は薬剤師が中心となり、さらにケースワーカーや看護師が介入します。初期の副作用は心配ですが、何かあれば連絡していただく形で救急対応にも考慮しており、特にトラブルは起こっていません。独居の高齢患者さんで、当初導入を躊躇したものの最終的に訪問看護の方を巻き込む形で導入でき、実際の吸入状況を確認できているケースもあります。
司会アリケイスを使用するうえで見えてきた位置付けや課題についてはいかがですか。
木田現状初回標準治療の成功率が6~7割という状況を考えますと11)、関節リウマチのT2T(Treat to Target:T2T)のように治療目標を決め、治療効果を適切に見極め、効果不十分※と判断したらアリケイスの導入を考慮し、目標到達率を上げる方が良いようにも感じます。
露口確かに現在空洞を認める方には早い段階から3剤標準治療に注射薬を追加していることを考えると、効果不十分※と判断されたら早めにアリケイスの使用を考えてよいのかもしれません。
永井そうですね。初期の3ヵ月以上にわたりアミノグリコシド系の薬剤を使用することで治療成功率が上がるという報告は散見されますので15,16)、費用の問題など総合的な判断は必要であるものの、今後検討されるべきだと思います。
玉置現在はアリケイスをかなりの進行例に投与していますが、本来は肺の線維性変化や気管支拡張が進行する前に投与を検討できるとよいと思います。費用や吸入アドヒアランスの問題もあり、現状は導入例が限られているものの、今後どのような症例や病型に効果があるのか明らかになることを期待しています。
04|肺MAC症診療の今後の展望
司会最後に今後の肺MAC症診療の展望についてお聞かせいただけますか。
永井経過が非常に多岐にわたる疾患のため、一般的に「こういうケースにはこの治療」といったガイドラインを作成するのはむずかしいと思いますが、早期症例に対するアリケイスの位置付けには大きく期待しています。
木田当院では現在、血清検査と核酸検査を組み合わせた早期診断法の開発に取り組んでいます。今後この疾患の診断時期がより早くなり、重症化を予防する方向に進んでいくのではないかと考えています。
玉置肺MAC症の経過を考えますと、個々の患者さんに沿った最適な治療をする必要性を痛感しています。またアリケイスについては、本当にこの薬剤が必要な患者さんに届くよう努力するとともに、外来導入は当院のような専門施設が集約して行うことが地域医療への貢献にもつながると考えています。
露口私もこの疾患は1人1人きちんと経過を観察していくことが最も重要だと思います。アリケイスについては効果が得られやすい患者背景や予後など、経過を見ていきたいと考えています。また、現在は菌陰性化が治療のゴールですが、その達成は容易ではなく、一方で他人への感染性はない疾患ですから、必ずしも菌陰性化だけではなく患者さんのQOLや画像所見も考慮して治療のゴールを設定していくことが今後の課題だと思います。
司会早期診断や標準治療など多くの課題が山積するなか、先生方が日々様々なことに気を配り肺NTM症診療に奮闘される姿を伺い知ることができました。本日はありがとうございました。
注)各薬剤の効能又は効果、用法及び用量などは、添付文書をご参照ください。