座談会
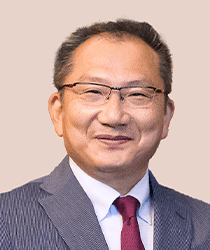
迎 寛 先生
長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科
呼吸器内科学分野(第二内科)教授

高園 貴弘 先生
長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科
呼吸器内科学分野(第二内科)准教授

福島 喜代康 先生
日本赤十字社
長崎原爆諫早病院
院長
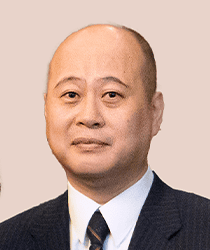
澤井 豊光 先生
長崎みなとメディカルセンター
呼吸器内科 診療部長・感染制御センター長

福田 雄一 先生
地方独立行政法人
佐世保市総合医療センター 呼吸器内科
管理診療部長
肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)は患者数の増加に伴い1,2)、限りある治療薬をどのように使うべきか議論される状況が続いていましたが、2021年に前治療に効果不十分※な肺MAC症治療に対してアリケイス®吸入液590mgが登場し、治療環境の変化が期待されています。そこで今回長崎県の呼吸器・感染症専門医の先生方をお招きし、肺NTM症診療の現状や長崎県の特徴、アリケイスの導入の実際、今後の展望などを伺いました。
開催日:2022年5月12日
開催場所:THE GLOBAL VIEW 長崎(長崎)
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
01|肺NTM症の現状
司会肺NTM症は近年増えている疾患である一方で、発見がむずかしいと聞きます。まず肺NTM症の現状について教えていただけますか。

迎日本ではかつて結核が大きな問題でしたが、近年結核の患者数が徐々に減少しているのに対し、NTM症の患者数は増えています。2014年の国内のアンケート調査では肺NTM症の罹患率が14.7人/10万人年と推計され、結核をしのぐ状況にあることが明らかになりました1,2)。NTM症による死亡者数も2020年には結核を超えており図13)、今や肺NTM症が非常に重要な疾患の1つになっています。増えている理由はよく分からないものの、疾患認知度や診断技術の向上、宿主要因として高齢化と関連があるのではないかと考えています。
福島診断技術の向上という点では、30年以上前までは肺NTM症の患者さんは結核罹患後の陳旧性の肺結核の方が二次的にかかるケースが多かったのですが、近年は基礎疾患がなく肺に陳旧性病変がない方が増えています。胸部CT画像で結核と肺NTM症それぞれに特徴的な所見が分かってきています。
高園肺NTM症の症状は、初期は乾性咳嗽が主で、徐々に進行して膿性痰や血痰、喀血といった症状が現れ、さらに進行すると肺が壊れて空洞が生じ慢性の呼吸不全のような状態に陥るのですが、気づかないうちに病状が進む点は感染症のなかでも特殊だと思います。高齢の方では、全身倦怠感や体重減少、食欲低下といったはっきりしない症状で発症する方もいますし、無症状で検診や他疾患の治療中に偶然見つかるケースもあるなど、症状だけでは特定しづらいですね。
澤井そのため、何か症状がある方や検診で指摘された方が一般内科を受診し、胸部X線検査などで少しでも異常所見があった場合は、すぐに専門医に紹介していただきたいと思います。
司会長崎県の地域的な特性はありますか。
高園長崎県では、肺NTM症の原因菌のうち北部でMycobacterium aviumが、県央や県南、島のある地域ではM. intracellulareの頻度が高いです4)。理由ははっきり分かりませんが、たとえば県北の中年女性では感染源が分からず、いつの間にか発症している方が多いのに対し、県南では農業に携わる高齢のM. intracellulare感染例で空洞形成が多い印象があり、生活習慣や職業、農業従事の有無などが関連するのかもしれません。
福島特に島原半島はM. intracellulareが多いのですが、火山灰があり他地域と土壌が異なることや、県内でも暖かい気候であることも影響しているように思います。
迎歴史的に感染症診療に力を入れてきた地域であることも長崎県の特性だと思います。というのも、江戸時代に遡ると当時鎖国の影響で海外から持ち込まれる様々な感染症は長崎から流行し全国に拡がっていったため、日本にとって長崎で流行を止めることが重要だったのです。昔は医学と言えば感染症対策であり、そのような流れで県内では昔から内科に呼吸器内科と感染症内科が設置されていますし、長崎大学には熱帯医学研究所があり感染症を主とした熱帯病研究に力を入れています。
図1
結核およびNTM感染症の
死亡者数の推移
(2006~2020年)
02|肺NTM症の診断および
治療における課題
司会肺NTM症を疑った後も診断や治療にたどり着くのがむずかしいと聞きます。

福島胸部CTの画像所見をもとに肺NTM症を考える場合は通常喀痰検査を行いますが、咳は出ても喀痰は出ない方が多いのです。当院では誘発喀痰法として3%高張食塩水の吸入を行います。それでも喀痰が出ない場合は経過を見つつ、陰影が増えてくる場合は気管支鏡検査を行います。喀痰検体が得られれば、培養検査や遺伝子検査、質量分析法などで菌種を同定し診断という流れですが図25)、時間がかかるため、特に喀痰が出ない方では非常に診断に難渋します。
迎場合によっては早朝の空腹時に胃液を採取し、菌の培養を確認して診断することもありますね。
澤井気管支鏡検査は侵襲を伴うため、患者さんの同意が得られない場合、あるいは超高齢者や日常生活のレベルが落ちている方では実施できません。一方、MAC抗体検査は感度が約70%、特異度が約90%と報告されており6)、陽性であれば「臨床的に肺MAC症」と言えるのですが、本検査はMACの主要構成成分であるGPL(Glycopeptidolipid)を認識するため、M. abscessusなどGPLを持つ他のNTMの菌種での偽陽性が起こりえます。MAC抗体検査はあくまで補助的診断として、培養検査で菌を同定することを第一に考える必要があります。
司会確定診断はどのタイミングで行うのでしょうか。
福田症状が強い方や血痰が出る方、画像上に空洞陰影がある場合などは、積極的に検査を行い確定診断に至りやすいのですが、症状や画像所見が強くない場合はむずかしいですね。すぐに治療が必要ないケースでは、かかりつけ医で定期的にレントゲンでの経過観察をしていただき、胸部CTは当院で撮影するなど、両方で診る形をとっています。
福島開業医の先生にもぜひ経過観察をお願いしたいです。また結核とNTM症は画像が類似し、両者が併発するケースもあるため、経過観察時には必ず結核を鑑別に入れ、疑わしい場合は結核補助診断のQFT(クォンティフェロン)検査などのIGRA(Interferon-Gamma Release Assays)検査を行うなど、結核の有無を確認いただきたいと思います。
司会治療の課題についてはいかがですか。
福田肺MAC症の場合は3剤の標準療法が基本ですが、肝機能異常や視神経炎、発熱や食欲低下などの副作用により、継続がむずかしいケースが少なくありません。また1回に3剤、約10錠を服用するため、高齢者では食事が入らなくなるケースも経験します。単剤治療は耐性化リスクが高く、さらに3剤標準療法も長期になると菌の性質が変化して薬剤耐性化が現れるため、経過が10年以上になる方などは治療がむずかしい状況にあります。

澤井現在の標準療法は1997年に米国胸部疾患学会が示したもので7)、四半世紀進化していないのです。副作用の問題はあっても治療効果が高いならば継続しますが、いつまで治療を続けるのかという問題もあります。菌陰性化後1年間という目安はありますが図38-11)、菌陰性化後1年以上治療を続けた方が予後が良いとの報告もあり12)、治療期間に関しては定まっていないのが現状です。またNTMは環境中に常在し、いったん治療が終了しても再燃や再感染が起こりやすいため、その対策がむずかしく新規の薬剤が待ち望まれています。
図3
治療終了時期と経過観察
03|新しい吸入治療薬
アリケイスの導入の実際
司会昨年新たに肺MAC症治療薬であるアリケイスが発売されました。既に導入されたご施設での現状を教えていただけますか。

高園当院ではこれまで患者さんに2泊3日で入院していただき、薬剤師と看護師による吸入指導や吸入器の洗浄方法などの指導を受けていただく形で導入しました。これは中高年や高齢の患者さんが多く、外来で繰り返し指導するのがむずかしいという理由だったのですが、2022年4月にアリケイスがDPCに加わり包括算定となったことで、今後入院導入は病院の減収につながるためハードルが高くなります。4月以降の新規導入例はまだありませんが、現在外来導入を検討中です。
福田当院の場合、コロナ禍での入院導入は大部屋でのネブライザー使用や洗浄・消毒がむずかしいため、外来導入を行っています。高齢の方が対象になるため、繰り返しの説明やご家族のサポートが必要となります。当院で最初に導入した患者さんは、ストレプトマイシンの筋注のために週3回受診している方であったため、「この薬剤を使うことで患者さんの通院負担が減る」ということを、まず外来スタッフに十分理解いただき、最初は薬剤師が導入方法を習得して外来看護師に指導し、外来導入する体制を作りました。
司会いざ導入してみて、導入とは別の面で何か気づいた課題はありますか。
高園臨床試験での投与6ヵ月目までの培養陰性化率は約3割で図413)、実際に効果がある方とない方を経験したため、患者さん自体の何らかの因子が効果に影響するように感じています。また薬価など医療費の問題から、患者さんに薬剤の必要性を納得いただくための最初の外来説明にかなり時間がかかりました。このほか声を使ったり大声を出したりする仕事の方では、副作用に発声障害があるため治療による弊害もあります。事前に起こり得る副作用に関しては導入前に十分な説明が必要です。

福田吸入器(ラミラ®ネブライザシステム)図5の取り扱いの面では、吸入中にハンドセットを水平に保てない、吸気バルブ(青バルブ)の設置の向きが分かりにくいなどがありました。ただ操作に慣れ、症状が改善されてくると手間はかかっても継続を希望する方がいらっしゃいます。2022年6月1日からは長期処方が可能になり、1ヵ月に1回程度の受診でフォローできそうであれば、患者さんにとってもよいと思います。
04|肺MAC診療の今後の展望
司会最後に肺MAC症診療への今後の期待や取り組むべきことなどをお聞かせください。
福島今まで難治性の肺MAC症には効果的な治療薬がなかったため、アリケイスには期待しています。一方で、肺MAC症が今増えている理由には、生体側の加齢や薬剤などによる抵抗力低下もあるように感じており、今後その辺りに注目した研究や生体の免疫を高める薬剤の開発を期待しています。
福田今まで3剤の標準療法を何年も行い、それでも進行した場合にはストレプトマイシンの筋注などを行っていましたが、アリケイスは標準療法が半年間の治療でも効果不十分であれば使用可能であり※、早い段階から肺の病変が進行するのを抑制できるのではないかと期待しています。また空洞性病変には緑膿菌の混合感染がみられるため、相乗効果が得られれば非常にありがたいですね※。ただ、アリケイスの使用による耐性獲得には注意が必要であり、今後データを注視していきたいと思います。
澤井私もアリケイスに期待しています。一方、初期治療には依然大きな変化がなく新たな治療の開発が必要です。全くの新規抗微生物薬の開発は困難としても、結核の薬剤などで開発を進めていただきつつ、我々は今ある薬剤を適切に使うことに注力する必要があるでしょう。キードラッグであるクラリスロマイシンの耐性制御は重要ですし、副作用が出ても安易に薬剤変更するのではなく、分割投与や減感作療法などで今ある治療が長く使えるよう努力していきたいと思います。
高園先ほどの話と重なりますが、アリケイスが効かない症例の原因を解明することと、アリケイス使用によるアミカシンの薬剤感受性の変化については、データをしっかりと追う必要があると考えています。
迎肺MAC症の治療は複数の薬剤を併用しないと効果がみられず、またそれぞれ副作用もあり、苦労して長期間治療しても治癒に至らず、副作用で治療を継続できない方もいます。何十年と治療が変わらなかったなかでのアリケイスの登場は、我々にとって明るいニュースであり期待しています。一方、今結核・非結核性抗酸菌症学会では若い会員が少なく、いかに若い先生方に結核やNTMに興味を持っていただくのかが課題です。最近は結核病床が減り、結核を診たことのない若い先生方も増えているため、この領域を担う次世代の先生方の育成が急務だと考えています。
司会アリケイスの登場でこれまでの治療環境に大きな変化が期待できる一方、新たな課題についても伺うことができました。本座談会が若い先生方に興味を持っていただく一助になればとも思います。本日はありがとうございました。
注)各薬剤の効能又は効果、用法及び用量などは、添付文書をご参照ください。