座談会

齋藤 武文 先生
国立病院機構 茨城東病院 院長

石井 幸雄 先生
国立病院機構 茨城東病院
(臨床研究部) 内科診療部
内科診療部長
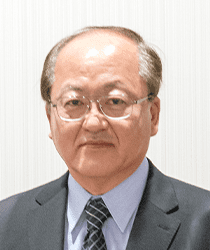
遠藤 健夫 先生
国立病院機構 水戸医療センター
呼吸器科 副院長

野中 水 先生
国立病院機構 茨城東病院
呼吸器内科・内科
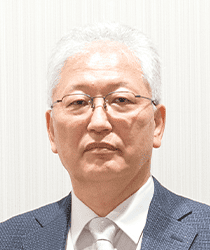
舩山 康則 先生
一般財団法人筑波麓仁会
筑波学園病院 副病院長・
患者サポートセンターセンター長・
感染管理室室長

松山 政史 先生
筑波大学医学医療系・
筑波大学附属病院 呼吸器内科
病院講師
2021年7月に、前治療で効果不十分な肺MAC症※に対して、アリケイス®吸入液590mgが登場し、1年が経過しようとしています。2022年6月には投薬期間制限が解除され、各地域においてその導入事例が集積されつつあります。そこで今回は茨城県の呼吸器・感染症専門医の先生方をお招きし、肺NTM症診療の現状を踏まえたうえで、アリケイス治療のご経験や取り組み、展望などについて伺いました。
開催日:2022年6月11日
開催場所:水戸三の丸ホテル(水戸)
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
01|近年の肺NTM症の傾向と
診療の現状
司会近年、肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)の患者が増えているそうですが、その背景にはどのような理由があるのでしょうか。
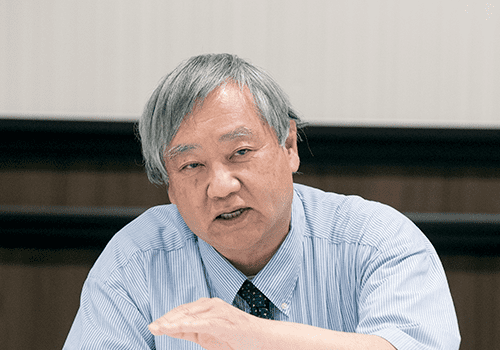
齋藤近年は、日本を含め、諸外国で肺NTM症の罹患率が上昇しており1,2)、本邦では特に2000年代以降に顕著な傾向となり、2014年の疫学調査からはその罹患率が結核を超えたことが示されています図11,3)。
理由は十分に明らかになっていませんが、医療従事者による疾患認知度が向上したり、NTMを検出する検査法の診断技術の発展に伴い診断能が改善した可能性や、宿主要因である高齢化が進んだことなどが考えられます。女性の方が発症しやすいので4)、高齢女性の増加も要因のひとつとして考えられると思います。またNTMは環境常在菌ですので5,6)、生活環境や自然環境の変化が影響している可能性も考えられます。実際、地表水のバナジウムやモリブデン濃度の上昇が肺NTM症の発症リスクを上昇させたという報告もあります7)。
司会患者数が増えている割には、一般の方々の間では疾患認知はあまり進んでいないと聞きますが、理由について解説をお願いいたします。
舩山肺NTM症の多くは進行がゆっくりで致死的なケースが少なく、結核と違いヒトからヒトに感染しないことから、呼吸器専門医以外の医師はこれまであまり注目してこなかったという背景があると思います。
遠藤やはり疾患啓発が不十分なことが影響していると思います。肺NTM症が疑われる軽症例では、喀痰が出ない場合、確定診断のために侵襲的な気管支鏡検査による喀痰の採取が必要になりますが、疾患の理解が不十分なことも影響し、大体の場合、患者さんに拒否されてしまうのが現状です。
司会肺NTM症は発見がむずかしい疾患とも言われていますが、専門医の先生方はどのような症状から肺NTM症を疑うのでしょうか。

石井持続する咳や痰、血痰などの症状、また検診や人間ドッグなどの画像検査所見から肺NTM症が疑われるのが一般的ですが、特異的な指標は確立されていません。ただ最近は、胸部単純X線検査やCT検査の技術の普及により、プライマリ・ケア医が画像検査所見から肺NTM症を疑うケースも多くなってきたと感じています。
司会肺NTM症は経過観察を行うケースも多いと聞きますが、経過観察中にどのような変化があれば進行を疑うのでしょうか。
松山無症状の患者さんの場合、咳、喀痰、血痰などの症状が発現した場合は、進行を疑います。一方、無症状のままでも、胸部単純X線やCTなどの画像所見の悪化や、抗MAC抗体価の上昇などがあれば進行と判断しています。
図1
本邦における肺NTM症罹患率の
年次推移1)(1980〜2014年)
02|肺NTM症の治療の実際
司会肺NTM症の治療開始のタイミングはどのように決めるのでしょうか。
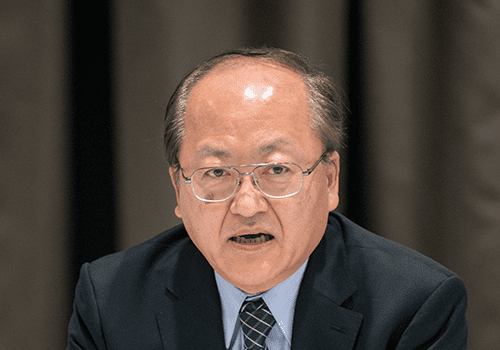
遠藤肺NTM症と診断されても、すぐに治療開始になるケースは少なく、結節・気管支拡張型タイプで軽症の場合などは、塗抹検査が陰性で菌量が少なければまずは経過観察を行います。経過観察中に、画像所見が悪化してきたら、治療開始を検討します。なお、空洞を形成するタイプや、菌量が多い場合は、早めの治療を検討します。
舩山肺MAC症に対する標準治療はクラリスロマイシン(CAM)、エタンブトール(EB)、リファンピシン(RFP)の3剤併用療法ですが8)、1997年の米国胸部疾患学会(ATS)ガイドラインに標準治療として記載2)されて以降、20年以上変化がない状況が続いていました。そのため、標準治療で十分な効果が得られないと、その後は打つ手がほぼない状況でした。近年になって、アミカシンの静注やアジスロマイシンの適応外使用について、肺非結核性抗酸菌症に対し処方した場合に、審査上認めるとする通知が社会保険診療報酬支払基金より出されました9,10)。昨年(2021年)は、アリケイスの使用も可能となり、ようやく選択肢が出てきたという状況にあります。
司会治療開始時に患者さんにはどのような説明をされていますか。
野中まずは、肺NTM症には残念ながら特効薬のようなものがまだないということと、長期の治療が必要なことをお話しします。肺MAC症の治療においては培養陰性化後の治療期間が15ヵ月未満の方に比べ15ヵ月以上の方は再発率が低いことを示したデータ図211)をお見せしながらお話しし、長期治療の必要性をご理解いただきます。「長い治療になるけれど頑張りましょう」とお伝えし、治療開始へと導くようにしています。
石井症状を改善させるための薬剤であれば患者さんも納得しやすいのですが、肺NTM症の場合は「投薬を続けることで症状を悪化させない」という側面もあり、そこは上手く説明する必要があると感じています。

野中また、長期治療では有害事象が問題になることがあるため、その早期発見に努めています。例えば、視神経障害の可能性のある薬剤を用いる場合は、治療開始前とその後も3ヵ月毎に眼科受診を継続してもらい、変化があれば早急に対応します。また標準治療を行っているなかで1剤の有害事象が問題になったら、その1剤のみを中止して2剤併用療法で長期継続を試みることもあります。
松山併存疾患のある場合は、他の診療科で使用している薬剤との相互作用を考慮して、事前に治療開始について他の診療科に伝達しておくなど、他科との連携も重要と考えられます。
図2
肺MAC症治療による
培養陰性化後の治療期間別再発率
(Kaplan-Meier解析)11)
03|肺MAC症治療の
新たな選択肢アリケイスの導入
司会アリケイスの導入状況はいかがでしょうか。
松山当院は大学病院で、検診で異常を指摘された軽症から中等症の肺MAC症患者を比較的多く診療していますが、なかには難治性であったり、標準治療に抵抗性を示したりするケースもあります。最近は、前治療で効果不十分※な症例に、アリスケイスの導入を検討するようになり、現在までに3例に導入しました。
舩山当院は総合病院でリウマチ科があるため、肺NTM症例のなかにも自己免疫疾患を有する患者さんがいらっしゃいますし、そのほか他院で治療に難渋したり、進行し肺機能がかなり低下したりして転院してきた方など、治療がむずかしい肺NTM症例が比較的多いという特徴があります。手術の適応がなく、さらに新たな治療選択肢もない、というケースを多く抱えています。
そうしたなかで肺MAC症※に対するアリケイスの有用性には期待を持っているのですが、医療費の問題があったり、高齢患者さんの場合、アリケイス専用の吸入器であるラミラ®ネブライザシステム図3の使い方の冊子や動画を見ただけで「自分には無理」と判断してしまったりすることもあり、導入には課題がある状況です。導入が決まれば詳細を説明できますが、何も決まっていない段階では時間をかけて説明することはむずかしく、対応に苦慮しているのが実情です。
実際に導入できたのは1例ですが、その方はアリケイスの動画を自ら視聴して使用を希望され、導入に至りました。当院には、アリケイスが適応となる患者さんはいらっしゃいますので、いかに導入にもっていくかが課題です。
遠藤われわれの病院は、結核病棟のない急性期病院であるため、重篤な肺NTM症例が紹介されることはほぼなく、そのほとんどは検診などで異常を指摘された軽症から中等症の患者さんです。しかし治療中に症状が進行するケースが少なからずあり、標準治療で十分な効果が得られない場合は治療に難渋しがちです。
そうしたなか、クラリスロマイシン耐性の難治症例でアリケイスの治験に参加経験のある1例に、アリケイスを導入する機会がありました。かなり進行した症例で、治験後はキノロン系の抗菌薬を導入し対応してきましたが、アリケイス承認後にその使用を再開しました。症状改善や菌量低下には至らないものの、画像所見は改善傾向がみられ、今後の経過を注視していきたいと思います。
司会導入にあたっての患者指導について教えてください。
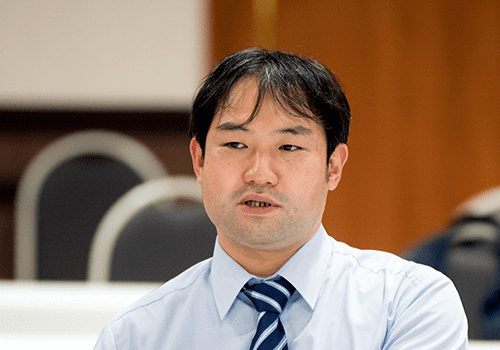
松山2022年4月より、DPC算定病院でアリケイスを使用する場合には、包括算定となりましたが、当院は大学病院ということもあり外来での導入指導がむずかしい状況にあるため、4泊5日の教育入院で導入しています。初日は薬剤師、2日目は看護師、3日目は医師がそれぞれ説明を行い、特定の職種の者に一任するのではなく、多職種の医療従事者が分担し協働して、患者さんをサポートする体制をとっています。
説明後には、患者さんに手技の動画を見てもらいながら、実際に手技を行ってもらうのですが、たいていの方は初日で理解し、2、3日目は問題なくできるという印象です。ただし、しっかり理解されているようでも実際にやっていただくとミスがあり、ご自分ではそれに気付くことができないというケースもありましたので、やはり導入時には、医療従事者がしっかりと手技ができているかを目で見て確認することが重要と感じています。
野中当院には軽症から重症まで幅広い肺MAC症例がいるのですが、現在までに10例でアリケイスを導入しました。当院はDPC算定病院ではないため、教育入院が比較的しやすい状況にあり、ほとんどの場合、教育入院で導入しています。ただしその場合も、初めに「こういう薬があります」とアリケイスを紹介するのは外来受診時です。そこでご納得いただいてから教育入院へと進みますので、外来での最初の説明の仕方も非常に重要と感じています。
また、教育入院の前にも、パンフレットなどの資材を用いて、丁寧に説明するようにしているのですが、その詳細な説明文を目にしたところで抵抗を感じてしまう方もいます。ただ、そういう方も実際に手技をやってみるとできることが多いので、医療従事者がうまく説明し、患者さんの抵抗感を和らげてあげることも重要と感じています。
04|実臨床におけるアリケイスの
位置付けと今後に
向けて
齋藤私は、症状が遷延し悪化していくケースを防ぐためにも、標準治療を6ヵ月間行い陰性化が認められない難治性肺MAC症※には、積極的にアリケイスの導入を検討しても良いのではないかと考えています。臨床試験からは、標準治療に難治性であった肺MAC症患者にアリケイスを追加投与し、約3割が陰性化したことが示されています図412)。
今後は、どのような背景の患者で、アリケイスが奏効しやすいのかを明らかにして、アリケイスをより有効に使用できるようになることが期待されます。
野中現在、茨城県ではアリケイス承認時にその導入を予定していた全施設を登録し、いわばオール茨城の体制で、アリケイスの臨床データを集積する取り組みを行っています。本研究からも、アリケイスの効果がより期待できる条件を明らかにしたいと考えています。
松山肺NTM症の予後不良因子に、空洞を有する、高齢、低BMIなどが挙げられますが13)、これらが疾患増悪にどう関与しているかなど、そうした基礎的な研究もさらに進めていく必要があると思います。そして、そうした因子を有する難治性肺MAC症に対して、アリケイスの有効性などが明らかになればと期待しています。
石井肺MAC症の易発症性や重篤化リスクを予測するバイオマーカーの開発が期待されます。
遠藤一般の方の肺MAC症の疾患認知度は低く、確定診断のための検査に協力してもらえないことも多々ありますので、疾患啓発も今後の重要な課題と思います。
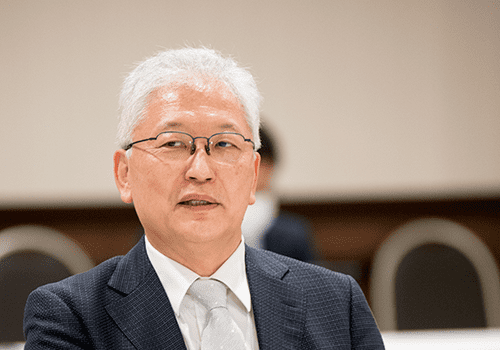
舩山肺MAC症は長期に経過する疾患ですので、非専門医の先生方との連携、地域連携なども重要です。そうした体制も今後より構築していければと考えています。
石井肺MAC症は、これまではあまり注目されてこなかった地味な疾患かもしれません。だからこそ課題も多く残されており、チャレンジングな疾患でもあります。アリケイスの登場もあり、今後の展開が期待されますね。
齋藤ただし薬物治療の向上が期待される一方で、薬物治療にばかり固執して手術適応例に延々と薬物治療を継続して致死的となるような事態は、避けなければなりません。そこは、肺MAC症の適正な診療・治療を十分に普及させていく必要があると思います。
司会本日のお話から、アリケイスの登場により肺MAC症の治療環境が大きく変わりつつあることを感じました。オール茨城での情報収集など、新たな取り組みも始まっており、今後の展開が期待されます。本日はありがとうございました。
注)各薬剤の効能又は効果、用法及び用量などは、添付文書をご参照ください。