座談会

平井 豊博 先生
京都大学 大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授

伊藤 功朗 先生
京都大学 大学院医学研究科 呼吸器内科学 准教授

西村 尚志 先生
京都桂病院 副院長 呼吸器センター・呼吸器内科 部長

岩田 敏之 先生
京都桂病院 呼吸器センター・呼吸器内科 副部長

藤田 浩平 先生
国立病院機構 京都医療センター 呼吸器内科 医長
肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)は、近年急速に患者数が増加し1,2)、2020年には死亡者数が結核を上回る状況となっている1)一方で、診断や治療などには課題が山積しているといいます。今回京都府の呼吸器専門医の先生方をお招きし、肺NTM症診療の現状や各施設での取り組み、今後の展望などを伺いました。
開催日:2022年9月27日
開催場所:ホテルグランヴィア京都(京都)
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
01|肺NTM症の現状
司会近年、肺NTM症が増えていると聞きます。まずその理由をご解説いただけますか。
西村1つには医療者の中で疾患認知度が高まってきたこと、そして以前は恐らく肺炎など別の疾患とみなされていたのが、近年は健診などを含めCT検査の機会が増えて検出力が高まり、「非結核性抗酸菌症」の疾患名がつくケースが増えたのが一因ではないでしょうか。また2020年にNTM感染症の死亡者数は結核を超え、2021年にはその差がさらに広がっていますが図11)、この背景にはNTM感染症の増加だけではなく、結核が確立された治療と衛生面の改善により大きく減少している状況があると考えています。
平井従来は一つの疾患が生命にかかわる状況であったのが、医療の進歩と人口の高齢化により、様々な疾患が併存した状態で寿命が延びたという背景もあると思います。また今お話があったように、日本はCT検査へのアクセスがよく、単純X線写真で判別できない病変がCTで発見されていることや、医師側の認知向上もあるでしょう。
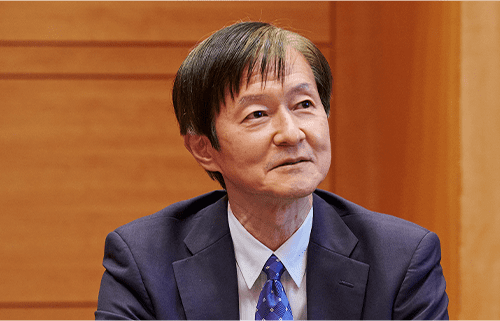
司会一般での疾患認知の状況はいかがですか。
西村抗酸菌感染症のうち結核は歴史的に有名ですし、ハンセン病も差別の問題などで知っている方が多いのですが、非結核性抗酸菌症はそもそも「抗酸菌」という名称が一般的ではなく、患者さんは「それは何ですか?」という反応が多いです。
平井患者さんに疾患名を伝えても、書いてくださいと言われますね。また心筋梗塞などと違って緩徐に慢性の経過の中で進行していくことが多いため、認識しづらい疾患だと思います。
伊藤ただ最近は、時々「私の症状は肺MAC症ですか?」などと言う方が出てきました。実際に肺MAC症かどうかは別として、これは5年前にはあまり感じなかったことです。わずかとはいえ認知度は向上していると感じます。
岩田確かにここ数年、新聞の記事や広告欄の書籍の紹介で肺MAC症の文字を目にする機会が増えました。一方で、肺MAC症という表現は、比較的短く書きやすいのですが、医師が説明する際に「肺MAC症」「非結核性抗酸菌症」「肺NTM症」など複数パターンを使用しており、統一化されていない点は伝わりにくい要因の1つではないでしょうか。
藤田非結核性抗酸菌症というと「結核」に反応する方が多く、正確な疾患名の周知はなかなかむずかしいですが、当院でも最近は中高年の方がスマートフォンで検索し、「この病気ですか」と尋ねるケースを見かけます。徐々にながらも認知が広がっている印象はあります。
司会慢性の経過で認識しづらいというお話でしたが、肺NTM症に特徴的な症状はないのですか。
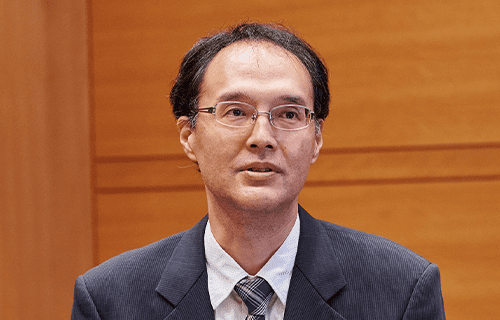
伊藤咳や痰が中心ですが、他の呼吸器疾患でもみられるため、強く肺NTM症を疑うには至りません。実際は健診や他疾患でのCT検査で指摘されるケースが多いと思います。
藤田当院の患者さんも、多くは健診異常や他科のCT検査で異常陰影を指摘されて紹介になるため、無自覚の方が多いですね。
岩田総合病院ですと他科や開業医の紹介で受診される方が多いですが、やはり他疾患でたまたま異常所見が指摘されるケースがほとんどのため、症状がない、またはあっても咳がたまにある程度で、患者さん本人が全く気にしていないことが多いです。逆に咳や痰がひどいケースは既に進行してしまっていると思いますが、咳や痰は肺癌やCOPD、肺炎など他の呼吸器疾患にも多いため、肺NTM症は症状ではなく画像検査の結果として疑う疾患だと思います。
図1
結核およびNTM感染症の
死亡者数の推移(2006~2021年)1)
02|肺NTM症診療の現状と課題
司会検出力の向上により見つかる確率が高まったとはいえ、早期発見はむずかしい状況なのでしょうか。
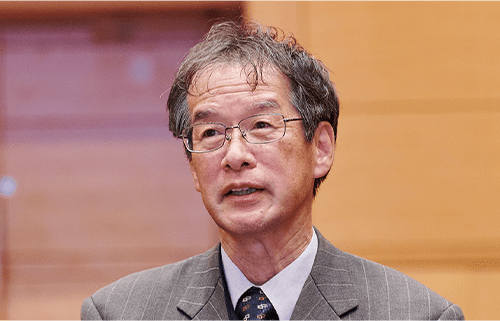
西村早期発見となると症状がない段階でみつかるということです。そうすると、そもそも健診や他疾患でたまたまCT検査を行う機会がなければむずかしく、さらに確定診断には菌の同定が必要であるため表3)、むずかしいケースがあると思います。
平井そうですね。画像検査での指摘後、そこから喀痰検査などで菌を同定し診断をつけていく過程は時間を要するため、特に一般医家の先生にはハードルがあるかもしれません。また喀痰検査で診断がつけば患者さんの負担が一番少ないのですが、それがむずかしい場合、気管支鏡検査は患者さんの負担が大きいため抗体検査を行うこともあります。そして疑わしい画像所見と抗体検査が陽性であれば、「確定はできないけれど肺NTM症の可能性が高い」というような説明をしています。
司会早期に疑っても喀痰検査がハードルになるのですね。
岩田誘発喀痰法という高張食塩水を吸入することで痰を出やすくする方法がありますが、周囲への感染予防のための環境確保が必要となり、現在のコロナ禍では当院の外来では控えています。現在外来では患者さんに痰の容器を持ち帰っていただき、痰が出た際に採取してその日に持ってきていただく形にしています。
藤田私も痰が出ない方には自宅で採取をお願いすることが多いですが、診断は早い方がいいと考えています図24)。当院では痰が出ない方に対し症状や年齢を加味して積極的に気管支鏡検査を実施しています。
伊藤この疾患が一生ものであることを考慮すると、私も菌名は早く分かった方がいいと考えています。確かに気管支鏡検査は患者さんの負担になりますが、若年で比較的将来が長い方にはできるだけ実施しています。一方で、長期間気管支拡張症として経過してきた患者さんが紹介されるケースも少なくありません。一部には症状があっても医師が喀痰検査を行わなかった、あるいは肺NTM症を疑わなかったために診断されていない方もおり、今後このようなケースは減らしていく必要があります。
司会確定診断に至ればすぐに治療を開始するのでしょうか。
西村肺NTM症の治療は最低限1年半から2年以上と長期にわたり、また疾患の進行が遅いこともあり、治療の開始は10年、20年先を考慮して検討します。例えば75歳以上の高齢患者さんですぐに治療を始めることはあまりありません。ただし症状が強い方に症状の軽減目的で試してみるというのは一つの方法かと思います。
藤田おっしゃるように1つの判断は年齢で、75歳を超えてくると本人の希望などを考慮しつつ様子をみるだけの方も多いですが、40代の方など、この先何十年と人生が続くことを考慮すると、早めに治療をした方がよいと考えており、若い方には積極的に治療を勧めます。年齢以外では症状の強い方、血痰が継続して出るような方も積極的に治療を導入するなど、個々の患者さんの状態を見て選択しているのが現状です。
平井空洞病変の存在や病変が広範囲の場合、診断がつけば治療する可能性が高いのですが、そうではなく症状も軽度であればまずは経過観察し、その過程で症状や画像所見に悪化が生じるなら治療について相談します。その際年齢は1つの判断要素ですが、70歳でも希望しない方、80歳でも積極的に希望される方はいますので、患者さんの人生観や希望も踏まえて治療を決める方針をとっています。
表
日本における
肺NTM症の診断基準
図2
肺NTM症の早期診断の意義
03|肺MAC症治療の課題と
アリケイスへの期待
司会肺MAC症治療では標準治療に課題があると聞きますが、具体的にどのような点でしょうか。
伊藤標準治療は経口薬3剤の併用が基本ですが、まず1回に服用する錠数が多いのです。また以前レセプトデータを用いて肺MAC症患者での処方実態を調べたところ、3剤が1年間以上処方されていたのは約3割、3剤のうちキードラッグであるクラリスロマイシン(CAM)単剤で3ヵ月以上治療されている患者が約1割という結果でした5,6)。現在の治療は副作用などで3剤を継続できる方が少なく、CAMの単剤使用による耐性化の問題もあります。
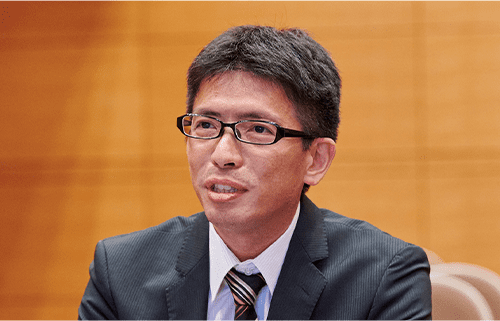
岩田そうですね。副作用や耐性化で治療継続がむずかしいほか、この治療が本当に効いているのか我々が実感しにくいところもあります。
藤田結核であれば6~9ヵ月の標準治療で治癒に至りますが、この疾患は一見治ったように見えても再発する方が少なくありません。治療期間が年単位に及ぶにも関わらず根治できないという失望感を患者さんに与えてしまうのですね。
平井ただ初回の治療導入時に副作用で上手くいかなかった場合でも、こまめに副作用を評価しながら徐々に慣らしていくと、最終的に目標治療量まで到達できる方もおられます。患者さんと粘り強く向き合っていくことが重要です。
司会このような課題があるなか、2021年にアリケイスが発売されましたが、印象はいかがですか。
伊藤従来アミノグリコシド系の薬剤は標準治療で効果不十分の方を対象に入院治療で使用することが多かったのですが、アリケイスの登場により外来治療が可能になったのは魅力的だと感じます。
岩田専用の吸入器図3の組み立て・洗浄が必要であるため患者さんに負担が多少かかるものの、入院せずに済みますし、患者さん本人が手技を理解し継続できる方、あるいは協力者がいる方であれば有用な選択肢だと思います。
藤田当院の導入ケースでは、新しい治療と説明して開始したためか満足度が高く現時点でやめたいという方はいません。1ヵ月もすれば手技にも慣れ日課になっているようで、最初の導入が上手くできれば日常のルーチンワークとして継続できると思います。
04|肺MAC症治療の今後の展望
司会最後に肺MAC症治療の今後の課題や期待についてお一人ずつお願いします。
西村現状の治療法だけでは完治がむずかしいため、例えば50代、60代の方には積極的に検査を行い、肺の組織障害が生じる前に治療を開始すること、高齢の方には症状緩和を優先した治療を検討するなど、今ある治療法でどう対応していくのかが今後の課題かと思います。
伊藤今後さらに医師の認知度と問題意識の向上とともに、患者さんをはじめ一般の方への認知・周知が重要だと思います。症状がなくても進行すると厄介であるという認識が広がれば、若いうちに、またはより早期の段階から受診・診断され、治療に取り組むことができるのではないでしょうか。

藤田確かにこの疾患は認知度が極端に低いため、実際に苦しんでいる方が多いこと、NTMが水回りや土壌など自然環境中に常在し図47,8)、可能であれば環境からの曝露は避ける方がいいといったことを広く知っていただくことが重要です。そして、きちんと研究をして治療法を開発しなければならないという機運を高めることが、我々医療従事者にとって重要ではないかと思います。
岩田この疾患は治療をしても消耗性に進行し痩せて元気がなくなるため、疾患コントロールに加え栄養状態の評価や治療介入を行い、治療継続や通院ができなくなる状況を回避することが重要だと考えています。またアリケイスを必要な患者さん注1)に確実に使うために、今後、吸入器が改良され手技がより簡素化されることを期待しています。
平井アリケイスの登場により治療選択肢が一つ増えたことは喜ばしいものの、より適した患者像や治療継続期間などは今後の検討課題であり、同時に臨床現場では引き続き新薬の登場が期待されます。また個々の患者さんの将来リスクを予測する指標の構築に向けた病態研究や、肺の機能低下を回復する再生医療研究など、研究活動にも取り組む必要があるでしょう。
司会本日は肺NTM症について、専門医の先生方の様々な角度からのご意見や各施設での工夫などを聞くことができ、有意義な時間を過ごすことができました。この疾患に対して画一的なものが確立していない状況ではありますが、今後も情報共有をしながらよりよい診療実現のために取り組むことが重要であると改めて実感しました。本日はありがとうございました。
図4
NTMの生息環境
注2)各薬剤の効能又は効果、用法及び用量などは、添付文書をご参照ください。