座談会
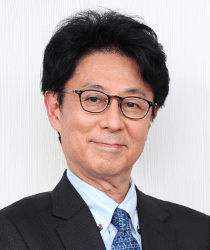
相良 博典 先生
昭和大学 医学部内科学講座
呼吸器・アレルギー内科学部門
教授
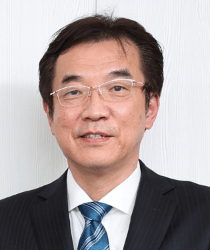
権 寧博 先生
日本大学 医学部内科学系
呼吸器内科学分野 教授

多賀谷 悦子 先生
東京女子医科大学 内科学講座
呼吸器内科学分野
教授・基幹分野長

南宮 湖 先生
慶應義塾大学 医学部
感染症学教室 専任講師
肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)は、近年の患者数増加に伴い、一般外来での診療機会が増えているといいます。そこで今回、肺NTM症の専門医と、呼吸器内科専門医の先生方をお招きし、呼吸器内科における診療の現状と課題、2021年に本邦に登場した吸入療法であるアリケイス®導入の可能性などを伺いました。
開催日:2023年4月3日
開催場所:JPタワー ホール&カンファレンス(東京)
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
01|肺NTM症の国内および
呼吸器内科における現状
司会最初に肺NTM症の診療や研究がご専門の南宮先生から、肺NTM症の基本情報として国内の疫学などを中心に現状のご解説をお願いします。
南宮肺NTM症の罹患率は、私どもが全国884の日本呼吸器学会認定施設・関連施設を対象に実施したアンケート調査にて、2014年時点で結核を超える10万人年あたり14.7人であること(図1)、このうち88.8%は肺MAC症が占めることを報告しています1, 3)。また厚生労働省の人口動態調査によると、2021年の死亡者数が結核1,845人であるのに対し、NTM感染症は2,324人であり2)、肺NTM症は明らかに増加傾向にあります。この理由として、疾患自体の増加に加え、恐らく肺NTM症に対する患者さん、社会、そして我々医療従事者の認知度の高まりがあるのではないでしょうか。たとえば健康診断のCT検査で中葉舌区に粒状影や気管支拡張を認めた場合に肺NTM症疑いとなる、肺MAC症の補助診断として抗GPL-core IgA抗体という検査モダリティが活用されるようになり、陽性の場合は積極的に肺MAC症を調べるといったケースが増えてきた印象があります。さらに肺NTM症の発症リスクとして気管支拡張症、COPD、関節リウマチ(RA)、低体重、その他ステロイドや生物学的製剤の使用などが報告されており(表)4)、高齢化や肺NTM症になりやすい方の増加、他疾患に対する治療の変化も、罹患率を上昇させる要因と考えています。
司会肺NTM症の患者数、死亡者数が増え続けているということは、一般の呼吸器内科でも診療機会が増えているのでしょうか。
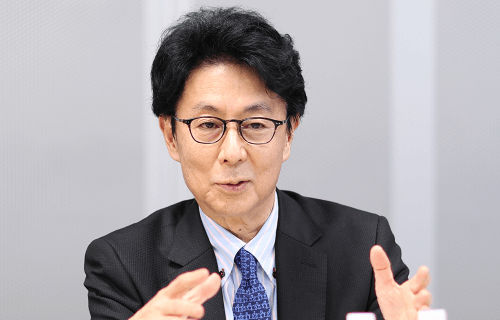
相良そうですね。当院の場合はリウマチ・膠原病内科や一般の開業の先生、プライマリケアの先生から胸部異常陰影で紹介された方で、検査をすると肺MAC症というケースが多いです。肌感覚としても外来患者さんの中でかなり増えている印象があり、私自身が今診ている患者さんの2~3割は肺MAC症です。
多賀谷ここ数年はコロナ禍ということもありCT検査が増えたためか、当院でも患者さんは増えています。特に施設自体にRA患者さんが多く受診されることもあり、その紹介なども含めますと、初診では毎週必ず肺NTM症の方がいらっしゃる状況です。
権当院の状況も似ており、やはりRA関連の紹介は多いですね。そのほか健康診断で指摘された方やステロイドの使用中に肺NTM症の疑い例になった方もいますし、他院での診断後、開業の先生のところで落ち着いていたものの、画像所見が悪化したために紹介されるケースなど、バラエティに富んだ患者さんがいらっしゃいます。
図1
本邦における肺NTM症罹患率の
年次推移(1980〜2014年)1)
表
肺NTM症の宿主感受性に
関連するリスク因子
02|肺NTM症診療の現状の課題
司会肺NTM症の診療機会が増える一方で、課題に感じておられることはありますか。
南宮まず早期診断が治療開始時期の判断や治療方針の決定に重要とされるものの、診断時の年齢や必ずしも症状がないなど、疾患の特性上どのタイミングで治療介入するのかという点が現場の医師を悩ませています。また実際に治療介入した場合の治療期間も、国内外のガイドラインで「菌陰性化後1年」が目安であるものの、2012年の日本結核病学会(現 日本結核・非結核性抗酸菌症学会)の見解にあるように明らかなエビデンスはなく、適正な化学療法期間は今後の研究課題とされています(図2)5〜8)。実際、治療が終了しても再感染するケースもみられ、長期間治療を続けるには患者さんにどう伝えるかという点も課題に感じています。
相良おっしゃるように、肺NTM症は結核と比べ経過が長く、現時点では完治がむずかしいため、画像所見に変化がなければ治療介入になかなか踏み切れず、早期診断をしても治療介入ができていないケースのほうが多いと思います。また肺MAC症の標準治療は3剤併用が基本ですが6)、薬剤耐性や副作用により継続が困難なケースや、さらに治療介入し菌陰性化後1年治療を継続といっても、そもそも陰性化しないケースもあるなど難治例も多く、臨床としてはむずかしい面が多いです。
多賀谷副作用などで治療継続できない方は多いですね。またベースにRAがある患者さんも多く、病態も様々であり、RAの生物学的製剤による治療と肺NTM症の進行抑制のどちらを優先すべきか、また併用薬の相互作用の問題など、治療判断に迷うケースは少なくありません。
司会RAをはじめ、他疾患に併発したケースがより治療を困難にしている面もあるのですね。
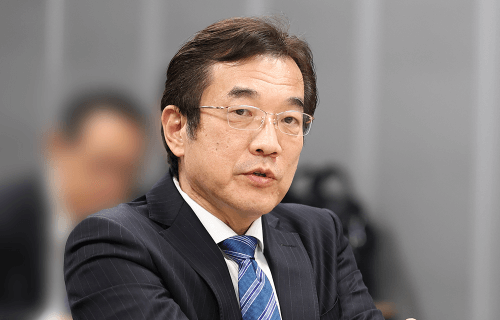
権肺NTM症の合併と診断されたRA患者さんへの生物学的製剤投与は原則禁忌ですが9)、肺NTM症の発症はRAの疾患活動性が高く生物学的製剤治療を必要としている患者さんに多かったり、生物学的製剤以外でも両疾患の治療薬に薬物相互作用の問題があったりなど、症状改善に有効な選択肢が限られます。そのため、リウマチ専門医とうまく連携し慎重に経過を観察しながら治療をおこなう必要があります。
多賀谷RAの薬物治療は免疫を抑制するため、治療をしっかりおこなうと感染症が発症、増悪するという痛し痒しなのです。その時々で今はどちらの治療が重要か、リウマチ専門医と話し合い、肺NTM症の治療を少し中断する間にリウマチ治療を強化する、治療強化し落ちつけば次は肺NTM症の治療をおこなうという形で、個々の患者さんによって調節が異なるのですね。
相良RAは、そもそもRA lungといって膠原病肺を起こすことがあり、治療で免疫抑制薬や生物学的製剤も使用するため、肺NTM症を合併しやすいのです。また合併した肺NTM症が必ずしも軽症ではなく、両方の疾患コントロールは非常に重要かつむずかしいです。RAの治療が必要であっても肺NTM症のためになかなか治療介入できず、実際に治療しても治りづらいケースは多いため、今後アリケイスのような薬剤を使うことで肺NTM症の疾患コントロールがうまくできれば、RAのコントロールにもつながると考えています。
図2
肺MAC症の
治療終了時期と経過観察
03|各病院におけるアリケイス
導入・使用の実際
司会いま薬剤名が出ましたアリケイスは2021年に難治性の肺MAC症注1)に対する治療選択肢として発売されました。本剤が適応となる患者像や現在の認知度などはいかがですか。
南宮医学的な適応は肺MAC症に対する多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者注1)ですが、加えて治療に前向きな方、自己管理ができる方というのも重要なポイントと考えています。
相良当院では現在アリケイスの担当チームを作っており、そういった意味で肺MAC症が専門ではない呼吸器内科医の中でも徐々に認知度は高まっていると思います。
権そうですね。導入に至るかどうかは別として、少なくとも当院の呼吸器専門医は当然知っていると思います。ただし1人で患者さんにすべての情報を説明できるほどの知識を持っているか、導入までの全ステップを1人で進められるかというとむずかしいかもしれません。
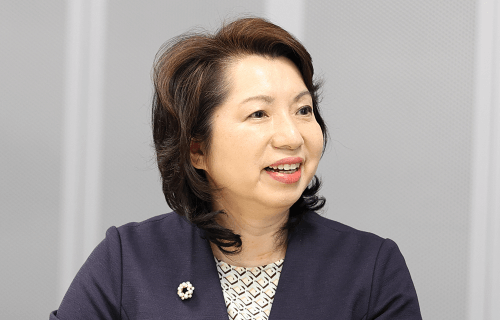
多賀谷肺MAC症は入院患者さんのなかでも難渋する疾患の一つであり、アリケイスは従来の治療がむずかしい患者さんに次の一手となる薬剤を切望していたところに登場しました。そのため若い先生たちや今まで治療に難渋してきたベテランの先生たちも興味を示しています。当院では結核や感染症を主に診ている先生がチームリーダーとなり、難治症例や治療に迷う症例を相談して導入を勧められる流れになっています。
司会アリケイスは外来治療が可能な反面、導入時の吸入指導などがむずかしいようにも感じますが、肺MAC症が専門ではない呼吸器内科でも導入は可能でしょうか。
相良呼吸器疾患の中でも喘息やCOPDは吸入療法が主たる治療であり、我々呼吸器内科医はデバイスに関しては熟知し経験値も高いため、導入は可能でしょう。実際患者さんが増え、診療機会も増えているわけですから、肺MAC症が専門ではない呼吸器内科でもできるだけ早期に介入して治療をしっかりおこなっていけば、重症患者さんをこれ以上増やさなくて済むのではないかと思います。
権日常診療の中に吸入指導を含めた患者指導や自己管理に対する指導体制はもともと構築されているため、こういった新しい吸入薬の導入に関しても呼吸器外来の中での提供体制は作りやすいと思います。とはいえ、従来の吸入療法に比べると複雑かつ異なる面もあるため、当院でも担当医を決め、その先生を中心に医療スタッフがチームを組み、各ステップを説明し導入する体制にしています。呼吸器専門医は当然こういった治療に参加すべきですし、現に参加しているのではないでしょうか。
多賀谷呼吸器内科の看護師さんもデバイスの指導には慣れています。アリケイスは従来のデバイスとは異なる面はあるものの、当院も担当医と外来看護師さんがチームを組み、動画なども活用して吸入手順を確認し、ケアルームで指導・導入する形で準備しています。
司会慶應義塾大学病院ではすでにアリケイスの使用経験を多くお持ちですので、導入時の工夫点、留意点などありましたら教えてください。

南宮先生方と同様に、吸入指導は慣れている看護師さんや薬剤師さんにお任せする、高額療養費の説明は事務の方にお任せするといった役割分担をおこない、多職種を巻き込んで個々の職種が主役になれるフローで導入することが円滑に進めるためのポイントだと思います。一方で副作用には注意が必要です。アリケイスの副作用のうち頻度の高い発声障害(嗄声)は治療開始直後に発現しやすいことが報告されています(図3)10)。当初経験が乏しかった頃は対処法に悩みましたが、現在はゆっくり吸入する、吸入の時間帯を夜にしてみる、うがいは左右交互にするなど、細かい工夫をしながら嗄声を抑えることを目指しています。
04|呼吸器領域における
肺MAC症診療の展望
司会アリケイスの登場で肺MAC症注1)の治療環境の改善が期待されますが、最後にご施設や先生ご自身が今後この領域で取り組みたいこと、取り組むべきだと感じていらっしゃることなどをお話しください。
相良従来の治療では、必ずしも効果が実感しづらい、治療介入に躊躇するといったケースは少なくありませんでした。しかしアリケイスという次の一手が登場し、実際に臨床試験でも効果が認められているわけですから11)、今後はより早い段階で治療介入するとともに、アリケイスも積極的に導入することが患者さんのQOL向上につながると思います。同時に我々はこの薬剤を育てていくべきであり、臨床データをさらに集積し、より投与が適した患者像などを示していく必要があると考えています。
多賀谷肺MAC症で入院する難治症例は本当に治療に困っておられ、我々医師の立場としても手詰まりを感じていた中、アリケイスという局所(肺末梢)へ直接到達12)する魅力的な吸入薬が登場しました。当然副作用には注意が必要ですが、それでも効果が認められている薬剤の存在は心強く、今まで「治らない病気」と思っていた患者さんも、まだ次の治療があるとなれば希望がもてると思います。そのためにも早期に介入し、できるだけ菌陰性化を保ち元気なまま過ごしていただけるような治療が必要だと改めて感じました。また宿主側の研究がさらに進展し、今後新たな治療戦略が出てくることも期待しています。
権肺MAC症患者さんの中には、それほど高齢でなくとも進行し亡くなるケースを時々経験します。したがってやはり早期に治療を開始し、アリケイスも積極的に導入し、すべき治療はすべておこない、亡くなる患者さんが1人でも減るような診療が必要でしょう。そのためには呼吸器内科医だけでなく開業の先生にもこの疾患を理解していただき早めに適切な医療機関に紹介できるようなしくみを作る、呼吸器内科医も積極的に診療に取り組みエビデンスを作るなど、より確実に有効な治療を患者さんに提供できるようにすることが重要だと思います。
南宮従来の肺MAC症の治療に課題を感じていた中、アリケイスの登場は患者さんにとっても、かつ医師・医療現場にとっても一つの希望だと思います。今後、研究面では現在行っている宿主因子、疾患関連遺伝子研究や免疫学的な解析をさらに進めること、診療面では呼吸器内科医全員が肺MAC症を診られるように、たとえばアリケイス導入時のプロセスの中で煩雑な部分のハードルを少しでも下げられるような情報提供や環境づくりを、現在提供されている資材なども活用しつつ(図4)、取り組みたいと考えています。
司会先生方のお話から、肺NTM症診療は今や専門医にとどまらず、広く呼吸器内科で整いつつある状況を実感いたしました。本日はありがとうございました。
注2)各薬剤の効能又は効果、用法及び用量などは、添付文書をご参照ください。