座談会

丸毛 聡 先生
公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 病院長補佐・呼吸器内科部長・感染症科部長・感染制御対策室長

浅井 一久 先生
大阪公立大学
大学院医学研究科
呼吸器内科学 准教授

延山 誠一 先生
関西医科大学香里病院 内科
– 総合診療科部長・地域医療連携部部長・医療情報部部長・感染制御部副部長
呼吸器内科教授

倉原 優 先生
国立病院機構 近畿中央呼吸器センター 臨床研究センター 感染予防研究室長
肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)、このうち特に肺MAC症は近年患者数が増加し、一般呼吸器内科でも診療に変化があるといいます。そこで今回、抗酸菌症診療の専門、呼吸器専門医の先生方をお招きし、肺MAC症診療の現状と課題、新たな吸入薬であるアリケイス導入も含めた今後の展望などを伺いました。
開催日:2023年4月6日
開催場所:ホテルグランヴィア大阪
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです
01|肺NTM症/肺MAC症の国内
および
呼吸器内科での現状
司会最初に肺NTM症の疫学やリスク因子などの基本情報、また、各ご施設での診療状況を教えていただけますか。
倉原2014年の全国アンケート調査により、国内の肺NTM症罹患率は塗抹陽性肺結核を大きく上回る14.7人/10万人年、このうち88.8%は肺MAC症が占めることが明らかになりました1)。約10年前の報告ですが、2021年の厚生労働省の人口動態調査では、NTM感染症による死亡者数も結核を超える2,324人まで増加していることから(図1)2)、現在の抗酸菌症の診療はほぼ肺NTM症が占める状況だと思われます。さまざまな肺NTM症のリスク因子が報告されていますが(図2)3)、実臨床でも中高年の痩せ型女性が圧倒的に多い印象です。また、死亡のリスク因子は、BACESスコアという肺NTM症の重症度スコアリングシステムにより、BMI(<18.5kg/m²)、Age(>65歳)、Cavity(空洞あり)、ESR(赤血球沈降速度)上昇、Sex(男性)を各1点として合計5点の場合に5年死亡率が82.9%と報告されており4)、このスコアリングを意識して診療しています。当院は呼吸器専門病院のため、人間ドックで肺の陰影を指摘された無症状の方のほか、呼吸器科を標榜する開業医やクリニックで治療がうまくいかず紹介されるケースが多いです。
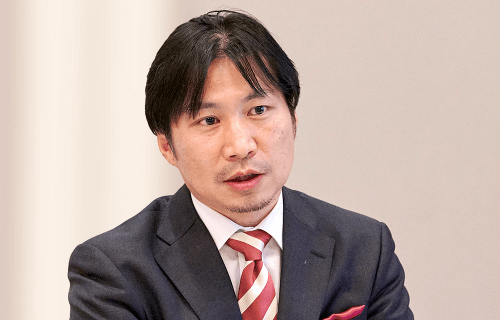
丸毛肺MAC症患者さんの増加は当院でも実感するところで、健診で肺の異常陰影を指摘された方、咳を主訴に受診された方、その他、院内の乳腺外科やリウマチ・膠原病内科からの紹介例も多いです。ここ数年はコロナ禍で健診控えがあったため、今年以降さらに増加することを懸念しています。
浅井大阪市は政令指定都市のなかで結核の罹患率が最も高いのですが5)、2021年の報告ではコロナ禍前と比べ約3分の2に低下しました6)。一方、肺MAC症は院内の他科から紹介されるケースが増えており、結核の減少と肺MAC症の増加は私も実感しています。人間ドックで初期に発見される方や紹介時点で肺に空洞を認め進行している方など、患者さんは千差万別です。
延山先生方と同様で、健診で指摘されたケース、咳や血痰で内科から紹介されるケース、また、関節リウマチや乳がんのフォローアップで実施するCTや骨シンチグラフィで肺の陰影が確認されて紹介されるケースなど、肺MAC症はあらゆる方面から紹介される印象です。
司会肺MAC症と他の呼吸器疾患で、診療の共通点や相違点はありますか。
丸毛たとえば喘息は患者さん自身が困っていることが多く、症状があって治療するため、治療がスムーズに導入でき、薬剤の効果への満足感も得やすいです。逆にCOPDは、症状が現れにくく症状発現時には進行している点で肺MAC症と似ています。COPDの治療が普及しにくいことは以前からの課題ですが、今、肺MAC症でも同様の問題が起きていると思います。
延山肺MAC症は初期に肺に陰影を認めても無症状の場合が多いですが、画像所見が徐々に悪化し、咳や呼吸苦、血痰が突然出て、その時点で治療しても治療効果があまり得られない印象があります。患者さんのニーズに応えるのが難しい疾患だと常々感じています。
浅井肺MAC症は診断に喀痰検査での菌検出が必要で7)、検体採取自体が困難であるのも他疾患との相違点かつ困る点です。喀痰が得られない場合は気管支鏡検査で初回診断ができなくはないですが、治療の途中経過を気管支鏡で毎回確認するわけにはいかず悩ましいです。
倉原喀痰検査は診断や効果判定の指標として非常に重要です。検体採取はたしかに難しいですが、肺MAC症患者の唾液様検体と膿性痰を比較すると、約60%は唾液様検体でも培養検査で菌が確認できたという報告があり8)、喀痰採取が難しい場合は唾液で一度試してみてもよいと思います。
図1
肺NTM症の疫学:
死亡者数の推移2)
図2
肺NTM症を引き起こしやすく
すると考えられる素因3)
02|肺MAC症治療における課題
司会今、肺MAC症の診断・検査の課題が出ましたが、治療にも課題はありますか。
丸毛画像所見で陰影が広範囲に拡がり、塗抹検査で菌がすぐに確認できた場合や、BACESスコアが高い方は治療開始の判断がしやすいのですが、無症状で排菌している方の場合は治療に納得されないケースや、標準治療を開始しても副作用により中断するケースがあり、治療開始のタイミングは難しいです。
延山以前は、陰影や排菌があればすぐに治療を開始していた時期もありました。しかし、現実には副作用で続けられない方や副作用のフォローで他科受診が必要になるケースもあります。さらに、治療の有無で予後があまり変わらない印象もあり、治療開始のタイミングは私も今まさに悩んでいる課題です。
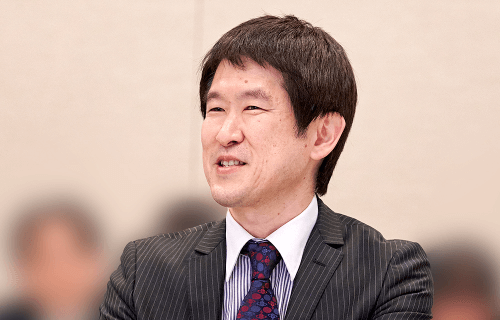
浅井他疾患の治療をすでに受けている場合、肺MAC症の3剤併用療法をさらに追加するのは患者さんも抵抗感があるため、低リスクの方は経過観察も一つの選択肢だと考えています。実際、培養検査でしか菌を確認できない場合は、少し慎重に経過をみることが多いです。
倉原治療開始は、基本的には医学的に困っている方を対象に、総合的に判断しています(図3)9-11)。一方で、排菌していても無治療で4~5ヵ月経過観察した場合に、予後にあまり影響しないことも報告されています12)。軽症や高齢者の場合、まずは4~5ヵ月程度経過観察してみて、治療開始の判断をしてもよいと私も考えます。
司会併存疾患の存在が、治療をより困難にしている面もあるのでしょうか。
浅井そうですね。たとえば関節リウマチはその疾患名の通り関節の疾患ですが、関節以外の部位にも症状が現れ、肺に生じる間質性肺炎や気道分泌型のリウマチ肺と呼ばれる肺病変は肺MAC症の素地になりやすいです。肺MAC症の合併を疑うと鑑別のために気管支鏡検査を行いますが、そもそも検査自体が患者さんの負担にもなります。
丸毛他科からの紹介例で、特に原疾患の治療が肺MAC症を悪化させるような場合、両疾患を比べてより重症の疾患の治療を優先しますが、そうするともう片方の疾患が悪化するというモグラ叩きのような状況に陥ることもあります。合併症のある患者さんは他科との連携が必須で、原疾患の現在の治療状況を担当医に直接電話して確認することもあります。
延山特に関節リウマチや乳がんの治療中に肺MAC症を併発したケースは、肺MAC症を治療しようにも薬剤の相互作用の問題もありなかなか踏み切れず、経過観察の間に悪化するといった歯がゆい思いをしますね。私も他科と直接連絡を取り、こちらの治療が優先できるかどうかなどを確認しています。
図3
肺MAC症の治療開始時期9-11)
03|アリケイス導入・使用の実際
司会従来の肺MAC症治療に課題があるなか、2021年に新たな治療選択肢としてアリケイスが発売されました。まず使用経験が豊富な倉原先生から、本剤が適用となる患者さんや実際に使用した印象、注意点などを教えていただけますか。
倉原アリケイスは肺MAC症の標準治療を6ヵ月行っても菌陰性化が達成できない、画像上増悪しているような効果不良例に上乗せで使用する位置づけの薬剤です注)。個人的には、治療開始後6ヵ月時点で菌陰性化が得られず、菌量が多い方への早めの導入が効果を得やすい印象です。注意点として、主な有害事象に発声障害があり、第Ⅲ相試験ではアリケイス投与群の46.6%で報告され13)、実臨床でも同程度みられます。発声障害は投与開始後1週間~10日での発現が多く(図4)14, 15)、具体的な対処方法はエビデンスがなく課題ですが、初期に改善する方や、症状と付き合っていける方もいらっしゃいますし、治療が終了すれば改善するため、治療前に大まかな経過を患者さんに伝えておき、吸入を間欠的に行うなどして慣らしながら継続することが重要です。
司会一般呼吸器内科でのアリケイスの認知度や印象、導入意向はいかがですか。
丸毛当院は導入経験がありますが、一般の呼吸器専門医は、知っていても使ったことがないケースが多いのではないでしょうか。デバイス治療に慣れてはいても、アリケイスは喘息やCOPDの薬剤に比べると高額かつ操作が複雑で、メンテナンス作業も含め患者さんが毎日継続するのは難しく思えます。また、第Ⅲ相試験での投与6ヵ月目までのアリケイス投与群の菌陰性化率が約3割13)という結果だけを見てしまうと、喘息の抗体製剤などを使い慣れている呼吸器専門医は使用を躊躇する面もあるでしょう。ただ、第Ⅲ相試験はかなりの難治例も含んだ結果ですし、薬剤のDDSや機序を理解し実臨床での使用感もお聞きすると、今後、一般の呼吸器内科でも導入は必要だと感じます。
浅井アリケイスは新しい薬剤として認知されてはいるものの、二次結核薬のように専門施設で使用する薬剤というイメージが先行し、導入に踏み込みづらい状況だと思います。また、結核の少ない地域では抗酸菌症の診療経験がない若手医師もおり、抗酸菌症の治療自体がハードルになるかもしれません。とはいえ、ここまで肺MAC症が増加すると、抗酸菌症の専門医にすべて紹介するのは非現実的です。当院は導入の検討を始めたところですが、他施設も広く導入を検討する必要があると思います。
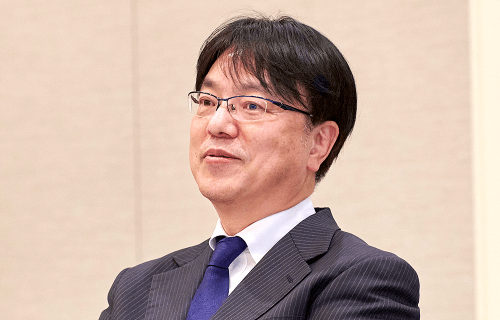
延山そうですね。私もアリケイスの存在は知っていたものの、特殊なデバイスと費用をハードルに感じていました。しかし、従来の治療で効果不十分な患者さんは目の前にいるわけで、実際に使っている先生方のノウハウを取り入れ、他職種との連携や呼吸器専門医の知識をもってすれば導入できると思いました。当院は外来で喘息の吸入指導をするシステムを自院で立ち上げていますので、アリケイスについてもこのシステムを活用したクリニカルパスなどを検討したいと思います。
倉原おっしゃるように、アリケイスのラミラ吸入器は面倒そうなイメージが医師と患者さん両方にあり、喘息やCOPDに用いる吸入薬よりも薬剤指導が最も高いハードルだと思います。その点で、基本的に導入は自己管理できる方を対象とし、最初に徹底的に吸入指導を行い、その後はアリケア サポート(図5)などを活用すると、一般呼吸器内科でも導入は徐々に進むのではないでしょうか。
丸毛高齢患者さんは家族のサポートのない方が多く、もう少し若い世代では子どもの教育費などが必要な状況で高額な治療に躊躇する方も多く、導入しにくい面はあります。ただ、当院の最初の導入例は高齢で軽度認知症があり、同居家族は年上の配偶者のみでしたが、別居している娘さんやヘルパーさんが親身になって吸入確認などをしてくださり、治療継続とともに最終的には菌陰性化も達成できました。患者さんの多くは高齢であり、介護保険制度なども利用しながら導入するとよいと思います。
図4
アリケイスの国際共同
第Ⅲ相試験(CONVERT試験)に
おける
有害事象の発現時期14)
04|肺MAC症診療の今後の展望
司会最後に、肺MAC症診療の今後の展望や取り組みが必要だと思われることなど、先生方のお考えをお聞かせいただけますか。
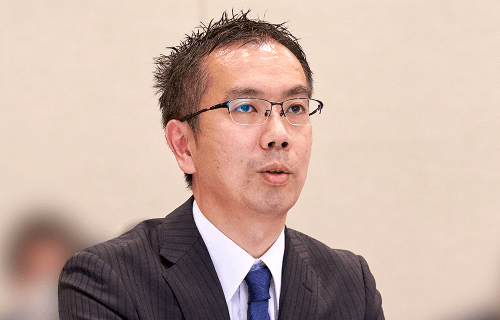
倉原昨今、医療分野はDX化が進んでいますが、アリケイスを使用するようになり、今まで以上に薬剤師さんや看護師さんと話し合う機会が増え、病院と調剤薬局の連携など、医薬連携が泥臭い方向に進んでいることに面白みを感じます。当院でのアリケイス導入は入院が基本ですが、全国的には外来導入が主だと聞きます。今後は外来導入にも積極的に取り組みたいと考えています。そのためにも医薬連携、多職種連携が重要です。
丸毛肺MAC症治療は普段私たちが診ている疾患よりも患者さんへのサポートが必要で、医師と患者さんが二人三脚で行うべきだと思います。これは他疾患にも必要であり、たとえばがん患者さんには行っていると思いますが、肺MAC症患者さんにはできていなかったため、今回改めて必要だと感じました。
延山肺MAC症は無症状から有症状までさまざまな病態があります。そこに合併症もあり、一次治療、二次治療の導入タイミングなど、まだまだ日本中の呼吸器内科医で統一されていないことが本日見えた気がします。当院のアリケイス導入はこれからですが、これまで呼吸器診療で培った経験を踏まえ、制度なども活用しながら、この患者さんを必ず治すという意志を持って取り組みたいと思います。(本座談会の後、関西医科大学香里病院ではアリケイスの吸入指導システムが導入され、すでに何人もの患者さんが治療を開始しています。)
浅井一般の呼吸器専門医のなかには抗酸菌症の診療機会が少なく食わず嫌いの医師もおり、呼吸器専門医レベルの治療はできていなかったかもしれません。いまだ十分な治療を受けていない患者さんは多いと思いますので、私たちも肺MAC症を身近な疾患として診療に取り組みたいと思います。
司会肺MAC症患者の増加や診療に課題があるなか、一般呼吸器内科での診療の広がりやアリケイス登場による治療環境の改善が期待される状況にあると知ることができました。本日はありがとうございました。
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。