座談会
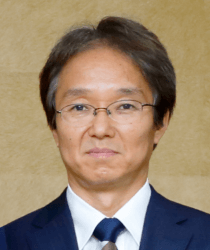
今野 哲 先生
北海道大学大学院医学研究院
呼吸器内科学教室 教授

中久保 祥 先生
北海道大学大学院医学研究院
呼吸器内科学教室 助教
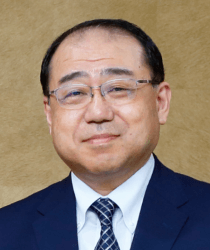
網島 優 先生
北海道医療センター
呼吸器内科 内科系診療部長
感染対策室長

千葉 弘文 先生
札幌医科大学医学部 呼吸器・
アレルギー内科学講座 教授

黒沼 幸治 先生
札幌医科大学医学部 呼吸器・
アレルギー内科学講座 准教授

長井 桂 先生
JCHO北海道病院 統括診療部長
呼吸器センター 呼吸器内科 部長
近年、肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)のなかでも、とくに肺MAC症の患者数が著しく増加しています。呼吸器専門医のみでは対応が困難になりつつあり、地域連携の重要性が増してきています。そこで今回、呼吸器専門医の先生方をお招きし、肺MAC症診療の現状と北海道での地域連携のあり方、また、治療選択肢であるアリケイスの導入などについて伺いました。
開催日:2023年9月20日
開催場所:ホテルニューオータニ イン 札幌
提供:インスメッド合同会社
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
01|本邦の肺MAC症の動向と課題
司会本日は北海道地区の先生方に肺MAC症診療についてお話しいただきたいと思います。まず、近年の肺MAC症の動向と課題について教えていただけますか。
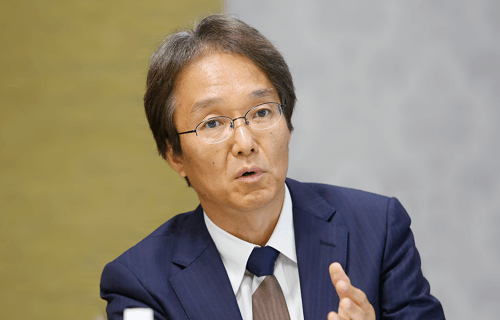
今野近年、本邦では肺MAC症を含む肺NTM症の罹患率が著しく上昇して、すでに結核の罹患率を超え、患者数は年々増加しています1)。こうした状況は実際の診療においても強く実感され、最近は、肺MAC症を診療しない日はないと言っても過言ではない状況にあります。
千葉同感です。私の感覚では、肺MAC症はcommon diseaseになってきた印象です。
網島この背景には、疾患認知度の上昇により患者さんの発見が促されたことや、肺MAC症の罹患リスクが高い高齢者人口が増えたことなどが、関連していると考えられます。
黒沼課題については、まず、治療法の啓発が不十分という点があります。肺MAC症の標準治療は、クラリスロマイシン(CAM)+リファンピシン(RFP)+エタンブトール(EB)による3剤併用療法が基本ですが(表1)2,3)、一部ではかつて汎用されていたCAM単剤療法や、EBを含まないレジメンが用いられています。これらは、マクロライドの耐性化を抑止するために、現在では、肺MAC症に対し避けるべき治療法とされています3)。
中久保肺MAC症は進行すると治癒がむずかしいこともあり、その観点からは早期治療が重要ですが、一方で症状に乏しい例や無症状のケースも非常に多いです。肺MAC症の治療は長期になるので、とくに無症状のケースではいつ治療を開始し、いかに治療継続を促すかが、悩ましい課題だと思われます。
網島症状がほとんどないものの、画像所見では明らかな病変、特に空洞を有するようなケースは速やかな治療開始が必要になりますが、無症状の患者さんから治療の同意を得るのは簡単ではありません。そうしたケースでは、症状が出てからでは治療効果が思わしくない可能性があること、予後を考えて、無症状のうちに治療開始したほうがよいことをお伝えしています。
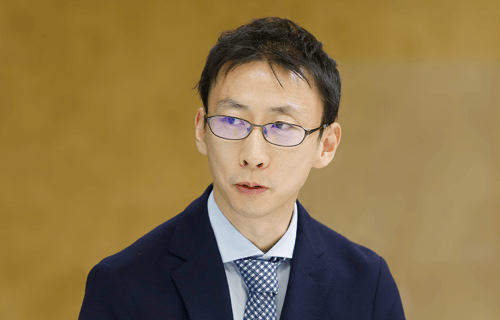
中久保おっしゃる通り無症状でも積極的な治療が必要なケースもあり、近年のガイドライン等は全体的にそこを強調する方向性にシフトしているようです3)。一方、無症状で長期の経過観察でも悪化がなく軽快していくケースがあることも事実で、全例が治療を要するわけではないのがこの疾患のむずかしさです。
個人的には、完全に無症状で画像所見でも軽微な異常しか認めず経過観察で変化がなければ、基本的には慎重な経過観察を継続しています。ただし、将来を考えて、若年者は少しでも進行あるいは症状があれば積極的な治療を勧めています。
黒沼2023年6月に「成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」が改訂されて、肺MAC症の治療開始基準が新たに示されました(表1)3)。こうした新しい情報も周知させて、必要なケースには確実に治療導入していくことが重要と考えます。
司会肺MAC症が難治性になるケースがあるとのことですが、先生方の印象はいかがですか。
今野標準治療を6ヵ月以上行っても菌が陰性化しない場合は難治性とされます。菌側の要因としては再治療に伴う耐性の出現、宿主側の要因には併存疾患、とくに肺疾患の影響で肺MAC症を発症しやすい素地を有することや、免疫低下などが関連していると考えられます。また、併存疾患の治療薬が影響することもあり、副作用や薬物相互作用により治療に難渋することがあります。
千葉難治性になるケースは半数を超えている印象があります。これは、治療法がまだ十分に確立されていないことの現れと考えられ、やはり肺MAC症は大きな課題のある疾患だと思われます。
長井私も、現在は難治化する例が半数を超えているように感じています。治療薬が使えない、次の治療法がないというケースがあり、肺NTM症全体でみると、近年の死亡率は上昇していることが示されています(図1)4)。この10~20年間で、本邦の肺MAC症は大きく様変わりした印象があります。
表1
成人肺非結核性抗酸菌症化学
療法に関する見解― 2023年改訂 ―3)
(日本結核・非結核性抗酸菌症学会
非結核性抗酸菌症対策委員会、
日本呼吸器学会 感染症・結核学術部会)
図1
結核およびNTM感染症の
死亡者数の推移
(2006~2022年)4)
02|アリケイスの導入状況と
使用の実際
司会2021年にアミカシン吸入剤であるアリケイス注)が発売されましたが、先にお話しいただいた肺MAC症の現状、課題を念頭に、本剤の適応や導入状況、位置づけなどについてご意見をお聞かせください。
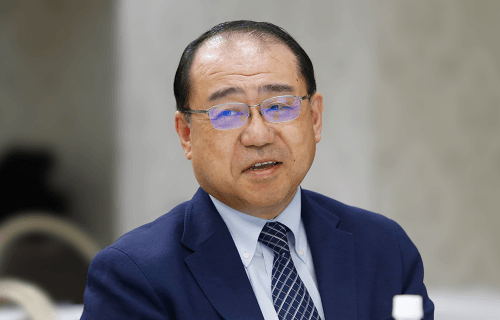
網島当初、アリケイスは難治性ですでに治療選択肢が乏しくなった重症の肺MAC症例に用いていました。しかし、それでは十分な改善がむずかしいケースもあり、現在は肺の空洞化や気管支拡張が軽微なより早期に導入するようにしています。「成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」では、線維空洞型、空洞のある結節・気管支拡張型、あるいは重度の結節・気管支拡張型の場合には、3剤併用療法にアミノグリコシドを併用し、難治性の場合にはアリケイスを併用することを推奨していますが(表1)3)、私の経験でもこうした使用法の有用性を実感しています。
中久保私も、重症例ではより早期からのアリケイス導入が有用と考えています。ただし、3剤併用療法で十分に効果が得られる方もいますので、アリケイスは、多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者に併用するという点を遵守する必要があります。
長井実際にアリケイスを導入する際は、吸入手技が煩雑なため、患者さんが「自分にもできる」と自信がもてるまで操作を繰り返し練習していただきます。JCHO北海道病院では、約4日の入院指導を行っていますが、将来的には外来での導入を目指しています。
今野北海道大学でも本来は外来での導入が望ましいと考えていますが、マンパワーの問題から、入院指導で導入しています。当院には若手の医師が多いという強みがありますので、病棟看護師とともに、若手医師にも指導を担ってもらっています。
網島北海道医療センターでは、医師と外来看護師が協働して外来で導入しています。また、アリケイスは薬価が高いため、場合によってはソーシャルワーカーに費用の相談や限度額適用認定証の説明を担ってもらうこともあります。
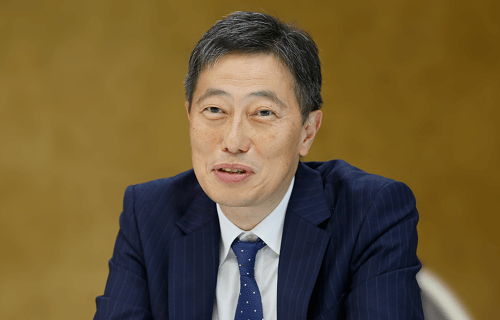
千葉アリケイスは導入の際の課題はあるものの、吸入剤ゆえに自宅で治療できるという点は、患者さんにとって大きなメリットだと思われます。また、薬物送達の面でも肺の病変部に直接的に薬剤が届き、全身への曝露が抑えられるメリットがあります5)。ただし、確実に吸入できているかを医師が細かく確認することが非常に重要で、吸入手技や器具の取り扱いも含めて、医療者側が積極的にフォローする必要があります。
司会アリケイスの副作用や継続状況はいかがでしょうか。
網島吸入開始直後は発声障害が発現しやすく(図2)6)、当院でも8例中6例で発現しました。休薬したケースもありましたが、回復後に吸入を徐々に再開すると、その後は継続できました。ほかには、口腔咽頭痛や、吸入に伴うむせ返りや咳嗽などが現れやすいのですが、それらの症状で投与を中止した例は、当院では今のところありません。
長井当院でも嗄声の副作用は経験しますが、嗄声による投与中止はありません。咳嗽は患者さんにとって辛い症状ですので、吸入時に咳込む場合は、中断して少し時間をおいてから再度吸入してもらうこともあります。
中久保アリケイスは、必要性が高い方に導入する薬剤ですので、導入前に副作用の説明を行いながらも、過度な不安は抱かせないようにフォローし、いざ副作用が出現したら適宜対処していくことが重要ではないでしょうか。使用初期の副作用を乗り越えれば、その後の継続は比較的スムーズにいく例が多いようです。
図2
アリケイスの国際共同第Ⅲ相
試験(CONVERT試験)に
おける有害事象の発現時期6)
03|肺MAC症診療で求められる
地域連携、新たな働き方
司会患者数の増加により、肺MAC症診療における地域連携の重要性が増しているようですが、先生方のご施設での状況はいかがでしょうか。
今野北海道は医師が不足しているうえに土地(診療範囲)が広いという特有の事情があり、呼吸器専門医、また、医師のみでの対応がむずかしくなってきていますから、ここは、一般呼吸器内科医や多職種の方々と連携して対応することが重要です。
中久保北海道大学に紹介される肺MAC症には、重篤な基礎疾患に肺MAC症を併発したケースが比較的多くみられます。最近は、血液疾患や移植などの精査から肺MAC症が発見されて、紹介来院する患者さんが増えている印象です。こうした例では、基礎疾患や薬物相互作用など、さまざまな因子を考慮した判断が必要ですので、大学病院に相談することになると思われます。

黒沼札幌医科大学に紹介される肺MAC症は、喀血などの大きなイベントを発症した例、併存疾患を有し複数の診療科での管理が必要な例、難治例が主です。治療方針の相談も多く、診断や治療に難渋する肺MAC症が結構な割合で存在することが認識されます。
長井JCHO北海道病院は市中病院に該当しますが、当院で治療方針を決定したら、初期治療でストレプトマイシンを使用する場合はほぼ全例で近医を探し、連携して管理しています。
その場合、副作用チェックは当院で行っています。当院での診療期間は院内の他科との連携がとれているので、多様な副作用をチェックすることも可能です。一方、近医に依頼する際は、当院から眼科や耳鼻科など複数の診療科に資料を送ってそれぞれに副作用チェックをお願いしていますが、その重要性が十分に伝わっていないケースがありました。
黒沼私は大学だけでなく地域の病院にも診療支援に行きますが、相談が遅れてしまうケースがあるため、近医から基幹病院へ紹介・相談するタイミングの見極めも地域連携の課題の一つだと思います。また、肺MAC症の治療薬は一般呼吸器内科では用いる機会が少なく、呼吸器専門医でないと使えないというイメージをもたれがちで、それが連携のハードルになることもあります。
司会2024年4月より、医師の働き方改革が施行されますが(表2)7)、これも含めた今後の肺MAC症診療の展望についてはどうお考えでしょうか。
千葉働き方改革の基準に合わせていかに診療の質を下げずに調整するかが課題で、そこはできる工夫を一つひとつ積み重ねるしかないと思っています。そのなかで、病診連携やタスクシェアは肝になるでしょう。
網島タスクシェアを採用する場合は、医師の業務をほかの医療従事者に担ってもらうことがとくに重要です。北海道医療センターでは、特定行為を担う看護師の育成に力を入れており、医師の業務が分担できる看護師を増やす体制整備を進めています。
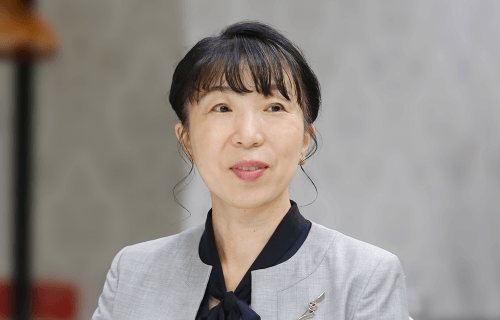
長井今後は、呼吸器専門医のみならず呼吸器科を標榜している診療所全般に、肺MAC症診療の病診連携を基幹病院から依頼する必要性が出てくるかもしれません。当院も非結核性抗酸菌症の長い診療経験がある施設ですので、他院ではむずかしいような病態の患者さんにも、積極的に対応していきたいと思っています。
千葉通常、肺MAC症は緩やかに経過するため、疾患知識が十分に普及すれば、治療方針の決定後はむしろ逆紹介しやすい疾患になるのではないでしょうか。呼吸器専門医が診断、治療導入、副作用の確認まで行い、その後の治療継続は近医に依頼するという形の連携が、一案になると思います。
黒沼肺MAC症患者さんを地域で管理するなかで、呼吸器専門医は「アドバイスしながらともに診ていく」という姿勢をとることが大切ではないかと考えています。協働の機会を増やして正しい情報を周知する必要があると感じます。大学で学んだ若い専門医たちが循環することによって、今後、地域から北海道全体の肺MAC症の治療水準を上げてくれることを期待しています。
中久保大学病院は、診療とともに、新たな情報を発信する役割も担っています。このためには、研究時間の確保が不可欠であり、そうした面からも地域連携は重要です。将来的には本日お集まりの先生方のご施設とも協力して、北海道発の肺MAC症のエビデンスを発信できたらと考えています。
千葉北海道の肺MAC症診療は、一部の中心地域を離れると、医療環境が整備されているとはいえない状況です。基幹病院で受診するために100km以上の遠方から泊まり込みで移動される患者さんも少なくありません。地域連携、病診連携の輪を広げることによって、より均てん化された医療を目指したいと思います。
今野この広い北海道で、均等に高いレベルの医療を提供することはわれわれのいちばんの目標です。医師不足ではありますが、肺MAC症の診療体制も働き方改革の新しい基準をクリアできるように整備しつつ、あらゆる方策で取り組んでいきたいと思います。
司会先生方のお話から、肺MAC症診療の課題、とくに患者数増加が喫緊の課題で、その解決には地域連携が要であり、一般呼吸器内科の先生との協働が非常に重要なことが認識されました。本日はありがとうございました。
表2
医師の働き方改革と対策7)
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。