座談会

權 寧博 先生
日本大学医学部附属板橋病院
主任教授 呼吸器内科部長

水村 賢司 先生
日本大学医学部附属板橋病院
病院准教授
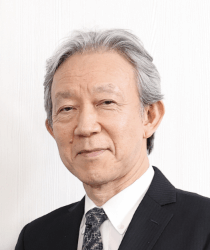
髙橋 典明 先生
板橋区医師会病院 院長
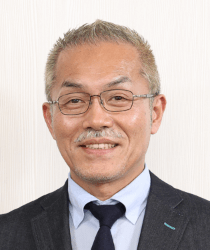
辻野 一郎 先生
日本大学病院 准教授
呼吸器内科 科長

吉信 尚 先生
東京曳舟病院 内科統括部長
近年、肺MAC症患者は増加の一途をたどっていますが、一方で新薬の登場やガイドラインが改訂されるなどの新たな展開もみられ、肺MAC症診療を取り巻く環境は徐々に変化してきています。そこで今回、日本大学および基幹病院の呼吸器専門医の先生方をお招きし、このような変化が実臨床にどのように反映されているのか、また、肺MAC症診療の現状や残された課題、さらに今後の展望についてお伺いしました。
開催日:2024年4月2日
開催場所:JPタワー ホール&カンファレンス(東京)
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです
01|実臨床での肺MAC症の動向
司会本日は肺MAC症診療の動向と課題、展望などについてお伺いします。近年の動向として、日本では肺NTM症が急増しており、そのほとんどを肺MAC症が占めている1)とのことです。この患者数の増加は、実臨床にどう影響していますか。
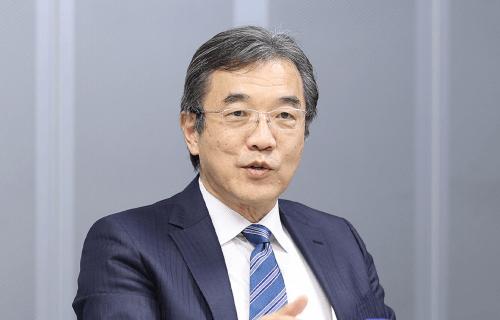
權肺Mycobacterium avium complex(MAC)症を外来診療する機会は、実際に増えている印象があります。呼吸器科診療において、肺MAC症は非常に重要な管理対象になってきています。
髙橋二次救急施設である板橋区医師会病院では、2024年3月の呼吸器科外来の総数のうち肺MAC症が占める割合は約5%でした。肺MAC症は進行が緩徐でかつ治療期間が長期にわたるため、私の実感では患者数が急増しているというよりは、診療する患者さんがどんどん蓄積されてきているという感覚です。
吉信東京曳舟病院は城東地区にある二次救急指定医療機関で、東京都災害拠点病院でもあります。肺MAC症を診療する機会、新規患者数は確実に増えている実感があります。肺MAC症の認知度の向上に加えて、CTが汎用されるようになり、診断される患者数が増えたことなどが背景にあるのではないかと考えています。
水村日本大学医学部附属板橋病院でも、肺MAC症の確定診断のための紹介受診が増えています。一般呼吸器内科の先生方が、診断に積極的になってきているのを感じます。
辻野一般開業医の先生方においても、潜在的な肺MAC症患者を発掘するノウハウが進歩してきているように感じています。これはCT検査の普及に負うところが大きいと思います。
髙橋患者さんの特徴としては中高年、とくに閉経期以降の女性が多い印象があります。また、近年は、CT検査で肺MAC症を疑われて来院する、無症状や軽症の患者さんが圧倒的に多いです。
司会患者数の増加を背景に、肺MAC症診療でも他院との連携が重要になってきていますが、その状況はいかがでしょうか。

水村日本大学の系列病院では、肺MAC症についても病診連携が進んでいます。近年は、CT検査で肺MAC症が疑われた段階で紹介されるケースが多くなっています。開業医の先生方においても肺MAC症は早期に対処すべき疾患へと認識が変化し、難治化してから紹介されるケースは減少しています。
權通常、日本では、多くの呼吸器内科はCT検査へのアクセスが良好ですし、近隣の画像検査センターなどと連携しているクリニックもあり、肺MAC症を診療するための基礎は整っているように思います。さらに質の高い管理を目指すには、無症状であってもいったんは呼吸器専門医に紹介いただき、連携して管理することが望ましいと考えています。連携における課題としては、紹介や治療開始のタイミング、治療をどちらの施設が担うかなどの基準を明確にしにくいことがあります。
02|肺MAC症診療の
むずかしさと課題
司会肺MAC症は治療開始の判断がむずかしいことが少なくないようですが、とくに課題と感じられるのはどのような点でしょうか。
吉信治療開始を検討するには、まずは肺MAC症の診断基準に合致していることが前提となります。しかし、喀痰が採取できない場合に、侵襲的な検査である気管支鏡は気軽にできるものではなく、診断に難渋します。このような場合、東京曳舟病院では抗MAC抗体検査(図1)2)を行い、陽性ならば、さらに3%食塩水をネブライザで吸入する誘発採痰法や喀痰誘発補助具であるラングフルートを使用し、診断の向上に努めています。
權日本大学医学部附属板橋病院には採痰ブースがあり、周囲にも配慮して喀痰が採取できる環境ですが、なかなか採取できないことも多いですね。肺MAC症は軽快と悪化を繰り返しながら経過することがよくありますので、悪化したタイミングで再び検査・診断を試みるケースも多いのではないでしょうか。
辻野肺MAC症の症例では、基本的に線毛運動が低下していることが多く、喀痰を採取できないケースが多いと思います。肺MAC症の確定診断に喀痰を用いる際、異なる検体で2回以上の培養陽性を確認する必要がありますが3)、これは実臨床では少々ハードルが高いと感じています。糖尿病やがんなどの併存疾患があり、肺MAC症の進行が速いケースもあるので、そのような場合は確定診断に至らなくても治療開始を検討することもあります。
司会無症状であっても積極的に治療開始を検討するのは、どのようなケースでしょうか。
吉信排菌量が多い症例、肺に空洞がある症例、さらに空洞周囲に浸潤影を認める場合は難治化する可能性が高く、診断が確定されたら積極的に治療します。
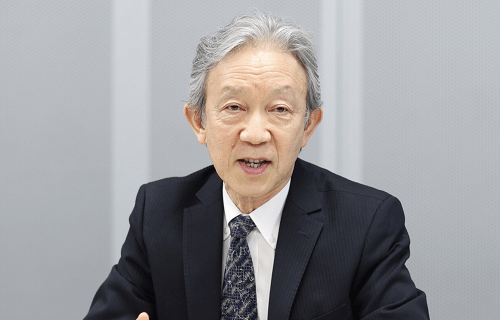
髙橋逆に排菌量が少なく空洞を認めない無症状例では、病態が急変する可能性は低いので、経過を見ながら治療の判断をしてもよいのではないかと個人的には考えています。そのようなケースでは、私は3~6ヵ月間隔で経過観察しています。
司会肺MAC症が難治化しやすいのは、どのようなケースでしょうか。
辻野結節・気管支拡張型であっても空洞を認める症例は難治化しやすいのですが、そのような難治例はほぼやせ型の方という印象があります。十分に食べられない方や、糖尿病、がんなどの基礎疾患を有する方、ステロイド薬を使用している方では、難治化しやすいと考えられます。また、栄養状態や肺の環境が不良だと、薬物治療を行っても効果が出にくいかもしれません。
權成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解(2023年改訂)では、標準治療を6ヵ月以上実施しても細菌学的効果が不十分なケースが難治例と定義されていますが4)、私の体感では治療しても排菌が続くケースは肺MAC症患者の半数弱ではないかと思います。難治例はかなりの割合に上るのではないでしょうか。
水村私は初回治療で菌陰性化しない割合は3~4割程度で、初回治療後に3割強が難治化しているように感じます。また、肺MAC症と診断されないままマクロライド系薬剤を単剤で長期に使用し、診断時にはすでに耐性化している例も少なくなく、このようなケースはとくに治療が困難です。
辻野肺MAC症の発症に関わる因子は多彩で(図2)5-6)、さまざまな可能性を想定しながら踏み込んで問診していくと、初診は10~20分かかってしまうこともありますが、それらの情報は難治化を予防するうえでも重要と考えています。
図2
肺NTM症の発症に関わる
NTM曝露と宿主因子5-6)
03|アリケイスの導入状況
司会難治化する肺MAC症が少なくないなかで、難治例への選択肢として、アミカシン吸入薬であるアリケイスが登場しました(図3)。先生方のご施設での導入状況はいかがでしょうか。
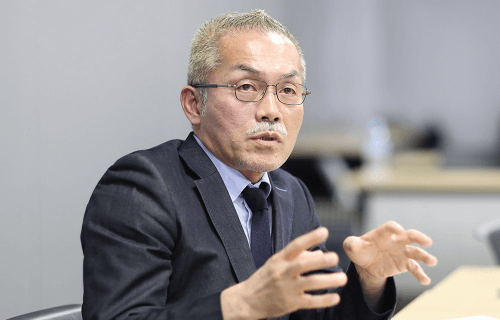
辻野日本大学病院では、アリケイスの資材やサポートサービスを活用しながら、多職種のスタッフの連携のもとに導入しています。アリケイスは吸入手技が煩雑で、器具の消毒なども必要なのですが、そこは看護師が説明・指導を担っています。
權日本大学医学部附属板橋病院では、地域のクリニックの協力のもとに、通院が困難だった患者さんに在宅導入した経験もあります。院内の連携体制、各種資材やサポートサービス、そして地域の病診連携も活用して、アリケイスの導入は比較的スムーズにできていると思っています。
吉信アリケイスは薬価が高いので、東京曳舟病院で導入する際にはケースワーカーにも参画をお願いし、高額療養費制度などの医療費の負担を軽減するための公的制度を周知していただいています。看護師、薬剤師、ケースワーカーなど多職種が連携して説明・サポートするとともに、導入当初は医師が2週間ごとに吸入状況をチェックしています。ただ、サポート体制がしっかりしていても、理解力の低下した高齢者で、ご家族の協力が得られない場合にはアリケイスの導入はむずかしいと思っています。
髙橋吸入デバイスの組み立てが困難な高齢患者さんもいらっしゃいますから、自身で吸入や管理ができない方への介入は今後の課題ですね。
司会具体的には、どのような条件の方にアリケイスを選択されていますか。
辻野画像所見で肺MAC症の進行が速いことが確認された場合には、標準治療で十分な効果が認められなければ、排菌量が少なく自覚症状に乏しくても、アリケイスの導入を積極的に検討しています。
水村標準治療を6ヵ月以上行っても排菌が陰性化しない難治例には、アリケイスあるいはアミノグリコシド注射薬の追加が推奨されていますが(表1)4)、さまざまな理由で注射はむずかしいが吸入薬であれば使用できるという方には、とくにアリケイスを勧めやすいですね。
司会アリケイスには、吸入開始直後に発声障害など特有の副作用が発現しやすいという課題がありますが7)、これにはどう対処されていますか。
水村最初の1ヵ月は嗄声などの副作用が出やすく、これは脱落の原因になることもあります。それを防ぐには、吸入途中でうがいをしたり、あまり深く吸い込まないようにしたり、ちょっとした工夫を取り入れることも有用なのですが、それでも症状が出る場合には、私はあまり無理をさせないようにしています。無理に継続した結果、脱落してしまっては意味がないので、「辛かったら少しお休みしても構いません」とお伝えし、たとえ投与休止を挟んでも、治療を継続することを第一に目指します。このような副作用は継続とともに軽減することが多いので7)、症状が落ち着いて治療が軌道に乗るまでは、こまめに様子を伺い励ましながら治療継続を促しています。
吉信副作用のうち高頻度に起きる嗄声と、重篤な副作用である過敏性肺炎と第8神経障害については、投与前に私は患者さんに必ず説明しています。単に副作用の可能性を伝えるのではなく、それを軽減する方法や対処法も併せてお伝えし、患者さんの不安を軽減するよう努めています。
表1
成人肺非結核性抗酸菌症
化学療法に関する見解
― 2023年改訂 ―
肺MAC症の治療4)
04|今後の展望
司会最後に肺MAC症診療の展望をお伺いします。今後の期待や予想される展開について、ご意見をお願いします。
辻野前述の通り、肺MAC症の確定診断に喀痰を用いる場合は異なる検体で2回以上の培養陽性を確認する必要があり3)、これは実臨床では少々ハードルが高いと考えます。診断基準を変える必要はないですが、診断補助に有用なPCR検査などを活用することも、ガイドラインなどに追記してもらえればと思っています。
また、肺NTM症の原因菌のなかには、難治性の迅速発育菌で死亡リスクが高いものもあります。そのような患者さんの治療においては、保険適用外の薬剤も保険適用に準ずるような形で使用できる制度ができればと願っています。さらに、われわれ呼吸器科医の今後の使命としては、耐性菌をできる限り残さない、次世代に引き継がない治療を行うことが重要と考えています。これは、肺結核においても同様です。耐性菌の問題、保険制度、経済面を含む医療環境など、それらを包括的に改善し、感染症治療を成熟させていく次の段階に進めるべきと感じています。
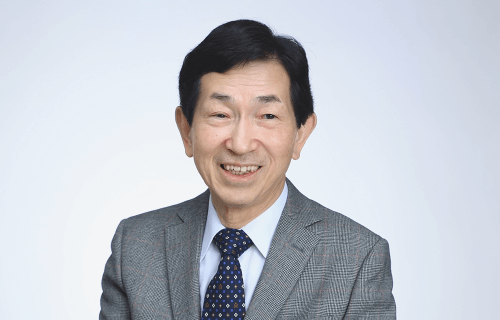
吉信肺MAC症の治療では、まず成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解(2023年改訂)4)が周知され遵守されることが重要だと思います。そのうえで、キードラッグとなる薬剤が今後さらに1~2剤登場すれば、現状の治療課題もだいぶ克服できるのではないかと期待しています。
髙橋新薬の開発とともに、宿主側の抵抗力を強める介入についても研究が進むことを期待しています。将来的には、たとえば、吸入薬により肺のマクロファージに直接的に作用して免疫を高めるなど、肺の環境や免疫を改善するような介入を従来の療法と併用する治療戦略が、治療の主体になっていくのではないかと考えています。
水村アリケイスについては、投与開始のタイミングや投与法の詳細が検討されて、より有用な使用法が確立されることを期待しています。また、MACは土壌やシャワーヘッドなどの水周りにも生息する環境常在菌ですので7-8)、発症や難治化を予防するには、治療とともに環境への介入も重要と考えています。
權アリケイスに関しては、今後、嗄声をはじめとした吸入薬特有の副作用を軽減する方法についても、対処法がより確立されることを願っています。現状では、どの施設でもアリケイスの導入が可能という状況ではありませんが、全国的な均てん化を図り、必要なところに普及するよう後押ししていく必要があると考えています。また、肺MAC症を筆頭とした肺NTM症の患者数、死亡者数が増加している1,10)という課題には学会レベルで取り組み、適切な診療が全国で受けられる社会を作っていければと考えています。
司会先生方のお話から、肺MAC症の現状や課題が認識されるとともに、よりよい未来に向けた道筋も見えてきたように感じました。本日はありがとうございました。
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。
Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
ラミラ® is registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.