座談会
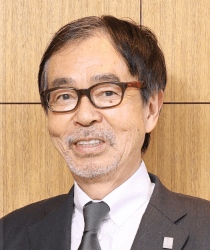
玉置 淳 先生
浜町センタービルクリニック、
東京女子医科大学 名誉教授
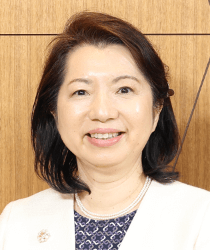
多賀谷 悦子 先生
東京女子医科大学
呼吸器内科学講座 教授

杉田 知妹 先生
東京都立大久保病院
呼吸器内科 医長

東 直子 先生
東京北医療センター 呼吸器内科
医長
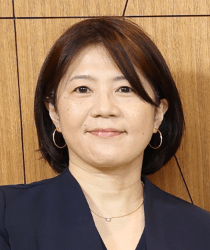
青野 ひろみ 先生
東京警察病院 呼吸器科 部長
本邦の肺MAC症診療は、疾患認知度の向上や新薬の登場などを背景に、一昔前と比べると状況が変わりつつあります。しかしながら、診断や治療におけるさまざまな課題は今も残存しており、また、患者数の急増という新たな課題も加わって、これらへの対応は決して容易ではありません。今回、東京都区部の基幹病院である東京女子医科大学をはじめとした呼吸器専門医の先生方をお招きし、肺MAC症診療の現状や課題と、課題を克服するために必要な今後の取り組みや展望などについてお伺いしました。
開催日:2024年4月18日
開催場所:小田急ホテルセンチュリーサザンタワー(東京)
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです
01|本邦の肺MAC症患者の動向
司会本日は肺MAC症診療の現状と課題、展望などについてお伺いします。本邦では肺NTM症患者さんが急増していると伺っていますが、先生方の実臨床での感覚はいかがでしょうか。
玉置患者さんの絶対数が増えているというよりは、疾患認知度の向上やCT・健診の普及などを背景に、診断率が上昇している印象があります。
多賀谷最近は呼吸器内科のクリニックでも、咳や痰が続いている患者さんに対しCT検査を提案する頻度が増えているようで、これも診断率の上昇に寄与していると考えています。
青野現在は、PCR検査で迅速にMACを検出できますし、CTの解像度も良好ですので、以前に比べると、肺MAC症の診断までのハードルは少し下がったように感じています。
東最近は、結核特異的インターフェロン-γや抗MAC抗体を測定する血液検査なども普及しており、結核と肺NTM症、肺MAC症の鑑別が容易になったことも、診断率向上につながっているのではないでしょうか。
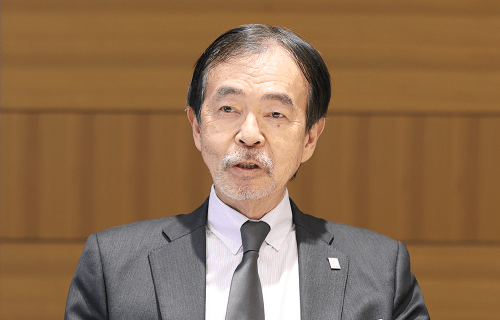
玉置ただし、肺MAC症の確定診断に喀痰を用いる際は2回以上の異なる検体で培養陽性を確認する必要があります(表1)1)。診療する患者数が増えていると先生方が実感し、早期診断の重要性(図1)2)も認識されている一方で、確定診断に至る割合は低いのが現状でしょう。画像所見から肺NTM症や肺MAC症が疑われる症例は多いものの、疑い例と確定診断例は分けて考える必要があると思います。
東肺MAC症疑い例では喀痰を採取できないケースが多く、その場合、確定診断には気管支鏡検査が必要になりますが、侵襲性から、この検査に尻込みする患者さんは少なくありません。そのような場合は、患者さんに「風邪をひいて痰が出たら、肺MAC症の検査に使えますので持ってきてください」と伝え、採取用の容器も事前に渡しています。検査室にもその旨を周知しておき、患者さんが痰を持参されたら、抗酸菌検査を速やかに行っています。
司会肺MAC症患者さんの近年の傾向、特徴などについてはいかがでしょうか。また、診療時の患者さんに対する対応や説明で気をつけていることがあればお話しください。
多賀谷近年は、健診で異常を指摘されその後の検査で肺MAC症が判明する方が以前より多くなったと感じています。肺MAC症は、典型的にはやせ型の方や基礎疾患を有する患者さんが多いのですが3)、そうしたケースでは、標準体型で基礎疾患もない、いわゆる典型例ではない患者さんがみられます。
青野年齢的には20~30代はごくわずかで、40代後半ぐらいから罹患率が上昇し、女性が多いという印象があります。画像所見で異常陰影を指摘されて来院されるケースでは、病変の範囲はまちまちですが、たしかに肺NTM症、肺MAC症が疑われる所見が認められることが多いです。
東肺MAC症は症状がない、あるいは軽症なことが多く、当面は経過観察となるケースが少なくないのですが、私は経過観察の場合も、症状が発現したら治療を開始することを患者さんに伝えています。治療は最低でも1年は継続が必要であること、副作用の可能性や十分な効果が得られない可能性、治療は生涯にわたる可能性があることなども、当初より説明しています。また、肺MAC症疑いの方にも、肺MAC症がどのような疾患であるかをお伝えし、経過観察のための定期的な来院が必要なことを説明しています。現在は肺MAC症のさまざまなパンフレットなども公開されていますので、それらもお渡しして、十分な理解を促しています。
杉田検査も治療も、患者さんがきちんと理解し、医師と患者さんで共通の認識をもって取り組むことが非常に重要ですので、説明の際には、患者さんの意識や理解を確認しながら話を進めるように心がけています。治療が必要でも投薬に同意が得られない場合には、粘り強く説明を繰り返し、理解していただくよう努めています。
司会治療を開始しても難治化する肺MAC症患者さんは、どの程度いらっしゃるのでしょうか。
青野多剤併用療法を6ヵ月間程度実施しても排菌が陰性化しないケースが難治性と定義されていますが4)、排菌の多い肺MAC症患者さんは治療しても完全に菌を根絶することは難しいでしょう。そうなると、治療が必要な肺MAC症患者さんは、多くが難治化すると考えられます。
杉田とくに肺に空洞を認める場合は、治療しても菌陰性化が非常に難しい印象があります。肺MAC症では、最近になってようやく吸入薬が使えるようになりましたが、従来は内服薬の多剤併用療法と点滴しか選択肢がほぼなく、難治化すると次の治療選択肢がないという状況になりがちでした。肺MAC症治療の基本は、限られた選択肢のなかで、副作用と耐性化を避けつつ治療を継続することですが(図2)5,6)、それは決して容易ではないと感じています。
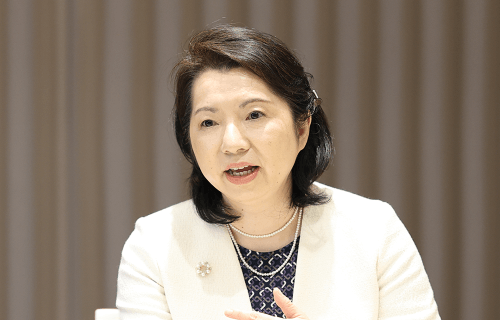
多賀谷とくにやせ型の患者さんは画像所見が悪化しやすく、しばしば血痰やCRP上昇を認めて、重症化しやすい印象があります。そのような場合は、治療してもるい痩が進行して、難治化するケースが多いと感じています。また、標準的な3剤併用療法を副作用のために中止するケースもあるため、確定診断し治療までたどり着いても、治療継続できなくなることがあります。さらに、必ずしも良好な治療効果が得られるわけではなく、一進一退の経過を辿ることが多いです。ここは患者さんが不安を抱きやすいところなので、医師がうまくフォローしながら経過を説明する必要があります。
表1
日本における
肺NTM症の診断基準1)
図2
肺MAC症の治療目標5,6)
02|肺MAC症診療における
病診連携の現状
司会近年は、肺MAC症診療においても病診連携が進められつつあるようですが、先生方のご施設では、この連携状況はいかがでしょうか。
多賀谷先述のように、肺MAC症は増悪を繰り返す疾患であるため、クリニックの先生方でも診療をためらう方は多く、いったんは紹介を受けてくださっても、逆紹介で戻されてしまうこともよくあります。画像検査による経過観察がされておらず、増悪してから再紹介されるケースもあるため、経過観察の具体的な方法や逆紹介の基準を明確にしておく必要があると感じています。
青野現状では、肺MAC症の診断や治療を呼吸器内科のクリニックの先生方が主体で行うことは、むずかしいのではないかと感じています。そのような前提で、病診連携においてクリニックの先生方にお願いしたいのは、結核が疑われる症例に遭遇したら、画像検査を実施していただくことです。そこで結核や肺NTM症を疑う所見があれば、基幹病院にご紹介いただければと思います。可能であれば、血液検査や喀痰検査なども実施していただければさらにありがたいですが、画像検査結果のみでご紹介いただいても、病診連携としては問題ないと私は考えています。
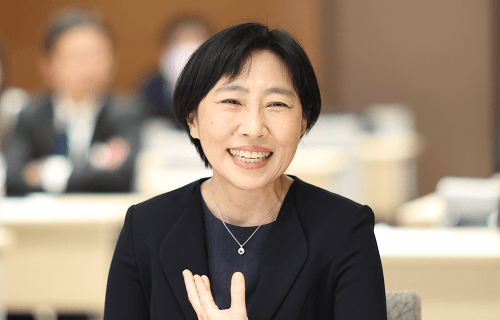
杉田とくに点滴治療を行う患者さんは頻繁な通院が必要ですので、そこは地域の呼吸器内科に担っていただきたいところなのですが、引き受けてくださるクリニックはなかなか見つからず、病診連携の課題は少なくないと感じています。
03|アリケイスの導入状況
司会先ほど、肺MAC症治療は難渋しやすいと伺いましたが、そのような状況で難治例への選択肢として、アミカシン吸入薬であるアリケイスが登場しました(図3)。先生方のご施設では、アリケイスはどのように導入されていますか。
多賀谷標準治療を行っても菌陰性化しない、画像所見が悪化する、微熱や炎症所見が継続する方などは、そのまま治療継続しても改善は難しいと判断し、アリケイスの適用を検討します。また、標準治療の副作用により生活に支障が生じている場合も、積極的に導入を検討します。肺MAC症治療の選択肢に吸入薬があることを知らない患者さんがほとんどですが、内服薬の副作用や、多剤併用による薬剤(錠数)の多さに悩んだりしているところにアリケイスを提案されると、前向きに受け取りやすいようです。

東とくに既存薬での治療中に悪化を認める方、服薬が困難になっている方には、アリケイスを積極的に勧めてもよいのではないでしょうか。現状の薬剤で改善が見られない場合に「新たな治療を始めてみませんか」という流れでご提案することも一案と考えています。
杉田アリケイスが臨床導入された当初は、すぐにコロナ禍になったこともあり新たな治療を導入する余裕がなく、興味はあったものの具体的な行動は起こしにくい状況でした。しかしそこから数年を経て徐々に普及し、基幹病院のみならず、市中病院でも積極的に導入する施設が出てきました。そうなると、当院でも導入は可能であろうと思うようになり、メーカーなどにもアドバイスをもらいながら、導入に踏み切りました。アリケイスは吸入手技が煩雑なことや薬価が高額なこともあり、導入前の説明や指導に労力を要します。そのため、医師だけでなく、ケースワーカーや看護師などの多職種のスタッフが連携して導入を担う体制を構築しており、連携のフローも作成して院内で共有しています。
玉置説明や指導に時間を要する点は、院内だけでなく訪問医療も活用する体制を整備すれば、克服できるのではないかと考えています。また、高齢者や認知機能が低下した方は、デバイスの操作が難しいことがありますが、そのような方でも安全に使用できるようサポート体制を強化することも、今後は必要ではないかと考えています。肺MAC症治療が難渋しやすいなかで、期待できる選択肢をできるだけ活用する体制を作っていければと思っています。
04|今後の展望
司会本日、肺MAC症診療のさまざまな課題が明らかになりましたが、今後必要と思われる取り組み、期待される展開について、ご意見をお願いします。
東私がとくに望んでいるのは新薬の登場です。現状では肺MAC症の治療は長期にわたり、ときには終わりが見えないこともあります。このような状況を変える、難治化を防げる薬剤の登場を望んでいます。
杉田肺MAC症の治療薬は長らく進展がなく、そこにようやくアリケイスが新たな選択肢として登場しましたが、これに引き続く形で、有効な新薬が複数登場してほしいですね。

青野本日のお話にあったように、肺MAC症の確定診断では2回以上の培養陽性を確認する必要がありますが1)、そのような排菌を認める段階になると、肺の構造がすでに壊れている可能性があります。将来的には、この診断基準をもう少し緩めて、より早期から薬物治療を開始したりすれば、治療成績の向上につながるのではないかと考えています。
多賀谷肺MAC症の治療は、たとえ有効性の高い薬剤を用いても、病態が進行し、るい痩が顕著になってからの投与では、効果が得にくいという問題があります。そうした面から、より早期から投与できる薬剤が登場してほしいですね。
アリケイスについては、アミカシンをリポソーム粒子に封入した吸入薬で、既存の肺MAC症治療薬とは異なるドラッグデリバリーシステムを有しています。肺MAC症が気道を侵される疾患であることを考えると、気道に直接的に作用する、投与経路が異なる薬剤は貴重だと思います。
玉置アリケイスについては、医師への周知もまだ不十分ですし、有効性と安全性のエビデンスはこれからさらに集積していかなければなりませんね。また、肺MAC症での肺の空洞化には、好中球細胞外トラップが関与するとされています7)。こうした知見から、炎症細胞を標的とした治療をより早期に開始すれば、肺MAC症の進行を抑制できる可能性があるのではないかと考えられます。細菌に対する治療法とともに、こうした宿主に対する治療法も、今後、確立されることを期待しています。
本日の討論から、肺MAC症診療ではさまざまな課題が残存していることが改めて浮き彫りになりましたが、今後の展望について先生方のご意見を伺うと、そうした課題の克服が将来的な希望へとつながっているように感じました。
司会肺MAC症診療の厳しい現状が明らかになるとともに、将来への希望も感じられる会になりました。先生方、ありがとうございました。
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。
Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
ラミラ® is registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.