座談会

菊地 利明 先生
新潟大学大学院 医歯学総合研究科
呼吸器・感染症内科学分野 教授
呼吸器・感染症内科科長
心療内科科長
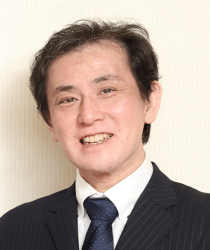
青木 信将 先生
新潟大学大学院 医歯学総合研究科
医歯学総合病院 呼吸器・
感染症内科 助教

桑原 克弘 先生
西新潟中央病院
呼吸器内科統括診療部長

松本 尚也 先生
西新潟中央病院 呼吸器内科 医長

田邊 嘉也 先生
新潟県立新発田病院 呼吸器内科・
副院長
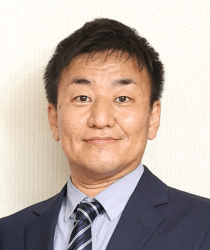
影向 晃 先生
新潟市民病院 感染症内科科部長
呼吸器内科副部長
肺MAC症診療では、近年、新薬の登場や成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解が改訂されるなど、新たな展開がありました。しかし、必ずしも推奨通りの治療が可能なわけではなく、個別の判断や対応が必要なケースが少なくありません。今回、新潟県で肺MAC症診療に携わる呼吸器専門医の先生方をお招きし、診療の現状をお示しいただくとともに、課題とその対策、また、治療選択肢であるアリケイスの導入状況、使用の実際についてお話を伺いました。
開催日:2024年7月10日
開催場所:ホテルオークラ新潟
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです
01|肺MAC症診療の現状
司会本邦の肺MAC症患者数は年々増加していますが1)、先生方が実臨床で遭遇する肺MAC症はどのようなケースが多いのでしょうか。
桑原西新潟中央病院は新潟県の結核拠点病院ですが、肺MAC症の診断確定例で、治療に難渋するあるいは治療方針を決めかねて紹介されるケースがとくに多いです。結核疑い症例が、肺NTM症との鑑別のために紹介されるケースも少なくありません。

青木新潟大学医歯学総合病院では、検診のCT画像などから偶発的に肺MAC症が見つかり紹介される軽症例が多いのですが、一方で、難治性となり重症化したケースも多く、軽症例と重症例の二極化が進んでいる印象があります。
桑原結核での紹介例はかなり減少している一方で、肺MAC症は治癒がむずかしいこともあり、診療する患者数がどんどん累積しているのも近年の特徴と感じています。
司会こうした患者数の増加に対応するには、肺MAC症診療においても病診連携が重要と考えられますが、新潟県内における連携状況はいかがでしょうか。
影向診療所では肺MAC症の治療経験が乏しいことが多く、治療が必要な症例に関しては、一般内科の診療所への逆紹介はむずかしいと感じています。また、経過観察をお願いしても、少し変化があったり、くすぶる病状があったりすると、再紹介されることが少なくありません。再診自体は問題ないのですが、その後に再び逆紹介する流れが整っていないところに連携の壁を感じています。

菊地肺MAC症の多剤併用療法のレジメンは肺MAC症に特化したもので、用法・用量は一般的な抗菌薬の使用法とは異なります。また、重篤な副作用の可能性のある薬剤も含むため、一般内科の先生方が用いるにはハードルが高いようです。現状では、治療および診断は基幹病院が担わざるをえない状況だと思われます。
桑原そのほかには、治療開始と終了、難治例となった場合の救援治療の方法、併存疾患を有する症例の治療方針、手術の実施などについて判断を担うのも、基幹病院の責務と考えています。
田邊一方、年齢的に治療を見送る判断となった方や、副作用のため治療継続が困難でも状態が安定している症例などは逆紹介が可能で、地域の診療所に経過観察を依頼しています。
また近年は、がん治療やリウマチなどで免疫抑制療法を行っている方が肺MAC症を発症するケースが少なくありません。そうした方では標準的な肺MAC症治療がむずかしい場合がありますが、そのような場合は各診療科と相談して治療方針を決定する多科連携が構築されています。
松本肺MAC症の標準的な多剤併用療法を用いる場合、眼科の副作用の定期的な検査が必要ですが、それはかかりつけの眼科の先生方に担っていただいており、この連携にはとても助けられています。
02|肺MAC症診療の課題
司会一般的に、病気は早期診断・治療が重要ですが、肺MAC症は必ずしもそうではないところが診療の大きな課題となっているようです。この点についてはどうお考えでしょうか。
菊地肺MAC症は極早期は確定診断がむずかしく、また、疾患経過に個人差が大きいため治療開始のタイミングを見極めにくいという問題があります。自然治癒する例もあるものの、軽快と悪化を繰り返しながら徐々に進行するケースが多く、治療開始の判断は専門医でも悩むことが多いです。
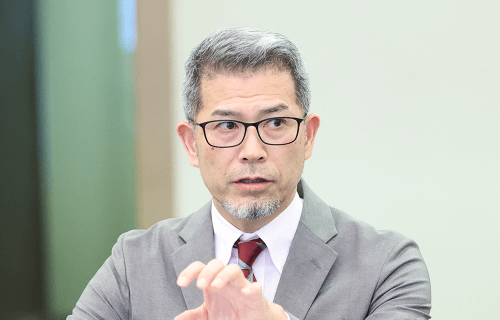
田邊こうしたなかで、2023年に「成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」が改訂されて、肺MAC症の病型別に、経過観察を前提とした個別の治療開始の判断、および具体的な治療レジメン(表1)2)が示されたのは大きな転機と感じています。私は、栄養療法や去痰治療に注力するのみでも進行が緩徐になる症例があることを経験しており、肺MAC症は必ずしも全例に標準治療が必要ではないことを感覚的に理解していましたが、この改訂によりそれが示されたのは非常に意義があると思っています。一方、積極的な治療が勧められるケースが明示されたことの意義も大きく、医師の肺MAC症診療に対する意識は変化してきていると考えられます。ただし注射薬については、通院の労力を考えると、現実的にはハードルが高いと感じています。
青木実際、注射薬による治療ができる方は限られています。また、多剤併用療法を6ヵ月以上実施しても細菌学的効果が不十分なケースが難治例と定義されていますが2)、線維空洞型は注射薬を使わないとほぼこの難治例に該当する印象です。そうなると、線維空洞型や大きな空洞と予後不良因子を有する症例などは難治化し、難治例に対する注射薬以外の選択肢として吸入薬アリケイス(図1)を導入するという流れが現実的でしょう。治療開始時からこの流れを念頭に置く必要があるのではないかと思います。

桑原肺MAC症患者さんのボリュームゾーンは中高年の女性ですが、まだ元気に過ごせる年代の方々を悪化させないためには、早期診断・治療が重要ではないでしょうか。未診断のまま抗菌薬を単剤投与して耐性化したり、難治化が予想される病型が放置されたりすることは、とくに若年患者さんでは厳に避けたい事態です。
松本実際には、無症状の方であれば、治療の必要性の見極めも兼ねて3ヵ月ぐらいは経過観察とするのが妥当ではないかと考えています。無症状でも治療が必要と判断した場合、その提案はむずかしい面もありますが、私は「この菌はお風呂の黒カビみたいなもので、放置するとそのうち汚れが強くなり、5~10年後にはかなり肺が汚れてしまう可能性があります」などとお話しし、治療の必要性をお伝えしています。そのうえで「80歳になっても元気でいたいと思うなら、60歳の今、治療を始めませんか?」などと未来を見据えた提案をすると、患者さんの多くは同意してくださいます。
また、肺MAC症の治療は長期継続が必要ですが、まずは半年間の継続を目標として提案しています。半年後にどれだけ改善したかを患者さんに画像でお見せし、患者さんの頑張りを称えつつ「せっかく成果が出たのだから、もう少し続けませんか?」と提案します。前向きな形で提案すると、結果的に患者さんの大半は1~2年間の治療を継続してくださいます。
表1
成人肺非結核性抗酸菌症
化学療法に関する見解
― 2023年改訂 ―2)
肺MAC症の治療
03|アリケイスの
導入状況・使用の実際
司会先述の見解改訂により2)、難治例に対する新たな選択肢としてアリケイスが推奨されましたが、導入状況はいかがでしょうか。
影向新潟市民病院では、3泊4日の入院指導によりアリケイスを導入する体制整備を現在進めており、いずれは外来導入も可能にしたいと考えています。コメディカルのスタッフに協働をお願いする形で依頼したところ、各職種の核となるスタッフが積極的に動いてくれ、この体制整備は速やかに進行中です。
青木アリケイスは吸入手技が煩雑なため、新潟大学医歯学総合病院でも当初は入院導入を採用していました。しかし、アリケイスを使いこなすのが困難と考えられる超高齢者は導入対象から外しており、対象の大半である若年者は速やかに手技を習得できたため、現在は外来導入へと変更しました。

松本西新潟中央病院では1週間の入院導入を採用しているのですが、それは体験入院という位置づけにして、患者さんには「試しにアリケイスをやってみましょう、実際に使用を続けるかどうかは、試してみてから決めていいですよ」とお伝えしています。アリケイスの情報提供は、初診時からパンフレットを渡したり、その後に実際の吸入器を見せて触ってもらったりと積極的に行っていますが、導入する際は、決して患者さんを追い詰めないように気をつけています。
影向アリケイス導入を患者さんに提案する際には、現在はさほど症状がなくても、後々苦しむことにならないように今から導入が必要である、ということを理解していただくのが大切なポイントと考えています。昨年までは、コロナ禍により呼吸器内科医は多忙で、新規薬剤について詳細に説明しようにも時間の確保がむずかしい状況でしたが、現在は落ち着いてきました。見解改訂の後押しなどもあり2)、アリケイスの導入・普及に取り組む機運は高まってきていると感じています。
司会アリケイスは、具体的にはどのような患者さんに用いていますか。また、どのようなタイミングで導入されていますか。
青木多剤併用療法を6ヵ月実施しても菌陰性化しなければ、その治療を継続しても菌陰性化が得られない可能性が高いことが報告されていますので3)、難治性になったらできるだけ速やかにアリケイスを導入することが重要と私は考えています。また、アリケイスの効果は、クラリスロマイシン感受性で空洞が大きくない、肺の構造がある程度保たれているなど、やはりより早期の段階の症例で得られやすい印象があります。
桑原アリケイス導入を検討してほしいと紹介されてくる患者さんはすでにかなり重症化していて、導入してもあまり効果が望めないケースが多いことに課題を感じています。難治例に速やかにアリケイスを導入する体制が整備されれば、治療成績はかなり向上するのではないかと私は予想しています。
田邊肺MAC症は基本的に治癒がむずかしく長期的に付き合っていく疾患ですので、難治例でとくに将来的に悪化が予想される方や体重減少が始まっている方などには、私はアリケイスの導入を強く勧めています。
インスメッド社からはさまざまな患者サポートサービスが提供されており(図2)、コールセンターも常設されています。コールセンターはアリケイスの費用面の相談にも対応していて、負担額の算出なども個別に行ってくれますので、導入を迷っている方にはこうしたサービスも積極的に紹介しています。
司会アリケイス導入後の継続や、その後のフォローについては、どのような状況でしょうか。
青木アリケイスの投与開始直後は、発声障害や咳嗽、口腔咽頭痛などの吸入薬に多い副作用が発現しやすいため4)、最初は必ずしも連日吸入にこだわらずに、副作用があれば一時休止することも許容しています。また、吸入を朝食前に行うなど、吸入のタイミングを工夫することも、副作用軽減に有用です(図3)5,6)。
松本私は副作用対策として、導入初期には毎月、血液検査と聴力検査を行っています。聴力の副作用に関しては、日常会話の音域には問題がなく患者さんが気づきにくいケースもあるので、とくに注意が必要です。
図3
発声障害などの
呼吸器系有害事象への対応5,6)
04|肺MAC症診療の今後の展望
司会肺MAC症診療について、今後の期待や取り組みたい課題があればお聞かせください。
菊地新潟県は面積が広いこともあり、地域によって患者層が異なり、医師の経験にも差異が生じています。そうしたなかで肺MAC症診療の均てん化が必要と感じており、ここは新潟市が中心となって取り組みたいと考えています。
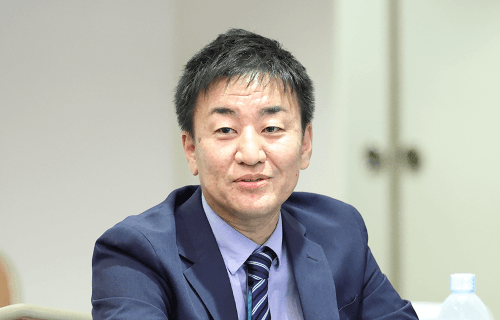
影向まずは呼吸器内科医が積極治療に向けて、治療方針をアップデートする必要があると感じています。さらに現在は、感染症についても病診連携が広まりつつありますので、肺MAC症診療においても、抗菌薬の適正使用をはじめ、正しい知識を共有した連携が求められます。一般内科の先生方には、まずは連携に加わり、ゆくゆくは肺MAC症診療全体にも関わっていただけるようになればと願っています。新潟県内の呼吸器内科医は仲間との結びつきが強いので、近隣全体を通して診療レベルを底上げしていきたいと思います。
青木治療については、開始基準が明確でない点が最も大きな課題だと思います。臨床症状、画像所見、菌の特性など、何らかの指標が確立されて、今後、適切に治療開始できる症例が増えることを願っています。
桑原見解改訂によりある程度の指針は示されたものの2)、見解通りの治療が必ずしも可能なわけではなく、やはり個別の対応が必要です。今後は、副作用対策、手術などの併用、栄養療法、リハビリテーションなども含めた包括的な介入によって、患者さんのQOL向上を目指すことにも力を入れたいと考えています。
松本肺MAC症は慢性疾患であり、長期に経過するなかで患者さんはさまざまな悩みを抱きやすく、不定愁訴のような訴えも多くみられます。こうした心理面からの訴えや、疾患進行に伴うサルコペニア、虚弱体質などには漢方薬が有効なことがあります。患者さんの訴えを傾聴する姿勢を大切にするとともに、今後は、漢方薬の応用についてもさらに検討したいと考えています。
田邊見解2)が改訂され治療法も向上し、新たな展開のあるなかで、私自身が肺MAC症診療に対してもっと前向きになる必要があると、本日改めて感じました。松本先生のお話からは患者さんを思う熱意を感じ、私も患者さんに対して粘り強く諦めない姿勢を持って、今後の診療に臨みたいと気持ちが新たになりました。
アリケイスについては、オール新潟で実臨床のデータを集積して、効果や課題を明らかにできればと考えています。
菊地アリケイスの登場により、難治例の選択肢が増えたことは非常に大きな進歩だと私は考えています。一方、アリケイスを導入しても菌陰性化できない患者さんもいます。そうした方では、菌陰性化を治療目標とすること自体がすでにむずかしくなっていることが多く、いかにQOLを向上させるかに注力したほうが、患者さんにとって有益な場合があります。アリケイスの使用法を工夫したり、アリケイスを補助する治療法を導入したりすることでQOL改善を目指すような展開も、今後、期待できるのではないでしょうか。
アリケイスが登場したことで解決した問題がある一方、その登場に伴って新たな課題があぶり出された面もあると思います。新旧の課題に取り組みながら、肺MAC症診療を向上していければと考えています。
司会先生方、本日はありがとうございました。
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。
Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
ラミラ® is registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.