座談会
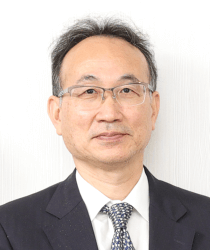
清家 正博 先生
日本医科大学大学院医学研究科
呼吸器内科学分野 教授
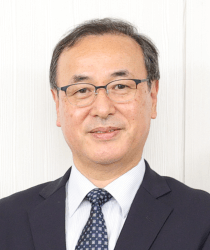
岡野 哲也 先生
日本医科大学千葉北総病院 准教授
呼吸器内科部長

山口 朋禎 先生
東京臨海病院 副院長
呼吸器内科部長

峯岸 裕司 先生
三井記念病院 呼吸器内科 部長
日本医科大学医学部 講師

田中 徹 先生
日本医科大学 内科学講座
呼吸器・感染・腫瘍部門 助教
肺MAC症治療は長らく進展がなく停滞していましたが、近年、新規薬剤の登場や治療指針の改訂があり、ようやく新たな展開を迎えました。こうした状況と患者の増加に伴って医師の肺MAC症に対する認知度と注目度は増しており、今はまさに、呼吸器専門医のみならず一般内科医においても肺MAC症と向き合う機運が高まっているといえます。今回、日本医科大学および基幹病院の呼吸器専門医の先生方をお招きし、新たなフェーズに入った肺MAC症診療の現状、課題と対策、および展望などについて伺いました。
開催日:2024年6月20日
開催場所:JPタワー ホール&カンファレンス(東京)
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです
01|実臨床における
肺MAC症の実情
司会本日は肺MAC症診療の現状を踏まえて、課題と対策、および今後の展望などをお伺いしたいと思います。近年、本邦では肺NTM症の罹患率(図1)1-3)および死亡者数4)が上昇していますが、実臨床ではどのようにお感じでしょうか。
山口東京臨海病院は地域の基幹病院なのですが、肺MAC症患者を診療する機会は増えています。健康診断で異常陰影を指摘された、あるいは開業医の先生方が肺MAC症を疑って紹介されるケースがとくに多く、これは肺MAC症の啓発が進んで、クリニックでも肺MAC症が認識されるようになったことが関連していると思われます。
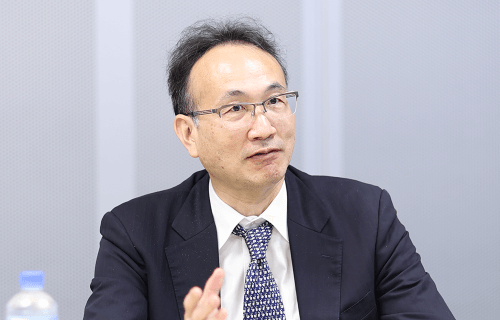
清家肺MAC症の罹患率を上昇させると考えられる要因はいくつもありますが(図2)5)、私はこうした要因による患者数の実際の増加以上に、「見かけ上の増加」が診療に影響しているように感じます。肺MAC症は治療法がまだ十分に確立されていないため治らない症例が蓄積し、それが他疾患と比べると、相対的に患者数が増えているように見える面があるのではないでしょうか。
峯岸経過観察期間の基準も明確にされていませんので、菌陰性化後にどこまで経過観察を継続すべきか、また、未治療での経過観察の場合にはいつ経過観察を終了してよいかなど、判断がむずかしいところがあります。そうなると、既存の患者さんの経過観察を継続したまま新規の患者さんはどんどん増えるという状況で、診療数は増えるばかりになります。
山口死亡に関しては、基礎疾患に肺MAC症を有する方で、気管支拡張症が終末期になったり、呼吸不全とるい痩が進行したりしたところに、最終的に肺MAC症が増悪して亡くなるケースが多い印象です。この点も、治療法が確立されていないことが関連していると思います。
岡野患者数増加に伴うむずかしい状況があるなかで、近年は、肺NTM症に注目した活動が活発化してきています。たとえば、日本結核病学会は結核が減り肺NTM症が増加している現状から、2020年にその名称を日本結核・非結核性抗酸菌症学会へと改めました。この影響もあり、医師間での肺MAC症の認知度、注目度はかなり高まってきているようです。COVID-19の影響で一時は中断されていた啓発活動もパンデミックの終焉により再開され、医師が肺MAC症治療に向き合う機運が高まっているのを感じます。
司会先生方が診療する肺MAC症は、どのようなケースが多いのでしょうか。特徴などはありますか。
峯岸三井記念病院は一般病院なのですが、無症状での紹介例がほとんどです。健康診断や他疾患でのCT検査で偶発的に異常陰影が見つかり、紹介されてくる症例が多いです。放射線科からのレポートには「肺NTM症疑い」と記載されていることも多く、肺NTM症の啓発が進んできていることを、ここからも感じています。
清家大学病院では、基礎疾患を有する方がCT検査を受け、そこで放射線科医が肺NTM症を疑い院内で精査に回される、というケースが多いのではないでしょうか。一方で、他施設に比べると重症例や治療がむずかしい症例も多いと思います。
田中そうですね。私の患者さんでも、基礎疾患がある方が肺MAC症を発症するケースが比較的多く、悪性腫瘍の方が1~2割を占めています。また、関節リウマチを合併する方も多く、リウマチによる肺構造の破壊に加えて免疫抑制剤の影響もあり、対応に苦慮することが少なくありません。
岡野日本医科大学千葉北総病院は高齢化が進んだ地域に位置することもあり、高齢で呼吸不全を呈する肺MAC症の患者さんを紹介されることが多いという特徴があります。症状が進行し全身状態が悪化した患者さんを治療しても十分な効果は期待できず、そのような状態で治療を行えば副作用が重篤化する可能性もあります。そのため、積極的な治療はむずかしいケースが少なくありません。
司会患者増加に対応するには病診連携が重要な鍵になると言われていますが、この連携状況はいかがでしょうか。
岡野当院では、元同僚の肺MAC症専門医が近くでクリニックを開業されており、軽症例はそこに逆紹介しています。その後は、点滴や入院治療が必要になれば再紹介してもらい、良好な病診連携を築いています。こうした病診連携があるか否かは、肺MAC症の診療体制として大きな差になると感じています。
田中私も病診連携を活用して適正な診療数に調整しようとしているのですが、一般のクリニックでは症状や画像所見が悪化すると対応不可と判断され、逆紹介してもすぐに戻されてしまうケースがかなり多い印象です。ここは課題と感じています。
図1
本邦における
肺NTM症罹患率の
年次推移1-3)(1971〜2017年)
02|いつ治療を開始すべきか
司会肺MAC症患者さんの特徴は施設によって異なるようですが、全体的にみると、軽症や無症状例が多いと聞いています。軽症や無症状の場合、治療開始のタイミングはどう判断されていますか。
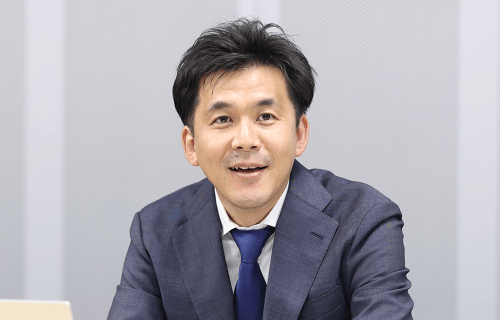
田中無症状例の治療開始の判断はむずかしい課題ですが、原則的には、塗抹陽性例や空洞を有する症例は、初診時から積極的に治療を検討します。それ以外のケースは経過を重視しつつ、全身状態、合併症、症状などを加味して総合的に判断しています。
峯岸治療開始の判断には、病態の進行速度と年齢を考慮することも重要と考えています。進行速度と平均余命から、無治療でも余命に影響しないと思われる場合には経過観察を継続し、一方、50~60代の患者さんであれば余命への影響を考慮して積極的な治療を検討します。
山口軽症例の場合は、私は症状を重要視しています。血痰などの症状は繰り返すケースが少なくないので、症状が発現し、塗抹陽性が確認されていれば、通常は治療を開始します。
03|若手医師の教育
司会肺MAC症診療の課題として、治療開始や経過観察の目安が確立されていないなど、治療指針の統一が進んでいない点が挙げられましたが、こうした状況に対応するために、ご施設で取り組んでいることがあればお話しください。
山口この状況に対応するには、やはり医師の教育が重要と考えます。東京臨海病院ではカンファレンスで症例を共有し、治療方針を話し合っていますが、教育体制としてはこれで十分とはいえず、とくに経験の少ない若手医師を教育する機会が不足していると感じています。

峯岸肺MAC症で入院するケースはまれなので、若い先生方はどうしても肺癌や間質性肺炎などの重篤かつ入院頻度の高い疾患に興味をもちやすく、肺MAC症の勉強は後手に回ってしまうのかもしれません。
岡野当院では、元国立療養所系列の施設における肺MAC症のカンファレンスに、Web上で参加させてもらっています。先方からの情報を受け取るだけの形にはなりますが、若手医師の教育につながっていると感じています。
峯岸医師の教育は、皆さん感じている通り課題があるものの、近年は肺MAC症治療にもいくつかの進展があり、若手の先生方と肺MAC症治療について話す機会を作りやすくなったと感じています。2021年には、アミカシン吸入薬であるアリケイスが登場しましたが(図3)、こうした新薬登場を機に、若手の先生方と肺MAC症診療について改めて議論する機会を設けるのも一案です。
山口関連学会による肺NTM症の扱いは、かつてはとても小さかったですが、今では大々的に取り上げられるようになりましたし、講演会も増えているようです。系統的に勉強する機会はなかなかないものの、若手の先生方が肺NTM症の情報を目にする機会は増えているでしょう。
清家今回のように治療指針が変わったり、新薬が登場したりした機会を利用して、教育の機会を設けていければよいですね。さらに大学病院では、関連学会などとも協働して若手教育を推し進めていきたいと思います。
04|アリケイスの導入
司会肺MAC症治療の近年の変化の一つにアリケイス注)登場が挙げられましたが、導入状況はいかがでしょうか。また、導入の際に課題に感じることなどはありますか。

山口東京臨海病院では、アリケイス導入の際には多職種連携による4泊5日の入院指導を行っており、最近、その入院パスを作成しました。肺MAC症は体重減少のある患者さんが多いので、リハビリや栄養管理を担うスタッフにも協働してもらい、包括的な指導を行っています。
田中アリケイスは吸入手技が煩雑なので、数回の外来指導でそれらを網羅するのはむずかしく、忙しい大学病院での外来導入は無理があるように感じています。幸い、日本医科大学付属病院では連携する呼吸器ケアクリニックに導入を担っていただいており、そちらで医師・看護師・薬剤師が連携して患者さんを指導しています。外来導入がむずかしい方に対しては当院での入院導入を可能にしたいと考えているため、その際には、東京臨海病院の入院パスを活用することを考えています。
清家やはりどんなに良い薬であっても、患者さんの理解が十分でないと使用できませんので、アリケイスの導入では患者教育が一つのハードルになると感じています。
田中とくに一人暮らしの高齢患者さんの場合は、家族のサポートを受けられないことが導入のハードルになりがちです。そのため私は導入を検討する前に、サポートしてくれる人がいるかなど、患者背景を詳細に聞くようにしています。また、アリケイスは費用面も導入のハードルになることがあります。
山口高価で吸入手技が煩雑な薬剤となると、導入の判断には、治療効果とのバランスが重要になってくると思われます。アリケイスの投与対象は、「成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」に則り、多剤併用療法を6ヵ月以上実施しても細菌学的効果が不十分な難治性の肺MAC症となりますが(表1)6)、現段階では、この基準に加えて、医師の見極めが必要と感じています。
清家アリケイスによって恩恵がもたらされる患者さんには確実に使っていく必要がありますが、実際の使用では、まだ手探りのところがあるのが現状だと思います。せっかく新たな選択肢が登場しても、それを有効に使えなければ意味がないので、導入のための体制整備や教育をはじめ、アリケイスを使用するための基盤を整える必要があるでしょう。
田中肺MAC症は症状に乏しいことが多く、患者さんが新規薬剤の導入に難色を示しやすいという問題もありますね。患者さんに体調などの変化を自覚してもらうために、「肺NTM症の治療をしている方のための呼吸と体調日誌」のような自己管理日誌を、標準治療を開始した時点から患者さんに記載してもらうのも有用でしょう。これにより、医師も患者さんの微細な変化を把握できますし、患者さん側も自身の病状をしっかりと把握することで、アリケイス導入を含め、医師からの治療変更の提案を受け入れやすくなるかもしれません。
表1
成人肺非結核性抗酸菌症
化学療法に関する見解
― 2023年改訂 ―6)
05|今後の展望
司会最後に、肺MAC症診療において、今後、先生方が取り組みたい課題や今後の展望についてお話しいただけますか。
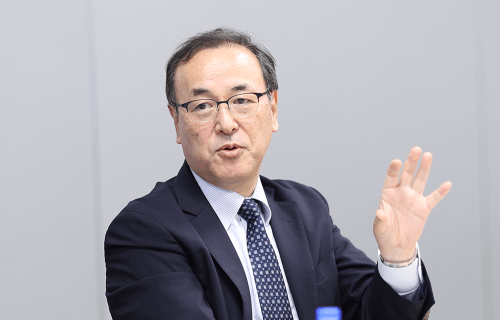
岡野現在は、肺MAC症への注目が高まっている時期だと思われます。そうしたなかで、私は研究面がさらに進展しアリケイスのような新しい薬剤の開発が進められることを期待しています。さらに、感染症対策は予防が基本であるため、MAC感染症の予防法が確立されることを願っています。
山口MACは環境常在菌ですので、今後、環境因子への介入方法が明確になることを望んでいます。エビデンスを確立させるのはむずかしいかもしれませんが、シャワーヘッドの取り扱い、浴室掃除やガーデニング時の装備など、有効と考えられる具体的な対策を周知していければと考えています。
峯岸環境因子への介入は、再感染予防の観点からも重要と考えられますね。啓発活動については「肺MAC症は、放置すれば命にかかわることもある」という点を、周知する必要があると感じています。たとえば、高血圧や糖尿病であれば、患者さんの認知度も高く、無症状でも多くの方は治療開始に同意してくださいます。一方、肺MAC症は認知度が低いゆえに、無症状のうちは治療の必要性を理解しにくいようで、治療開始の同意を得るのに苦労することが少なくありません。肺MAC症も、生活習慣病と同程度の認知度になるよう、啓発活動に力を入れる必要があると感じています。治療すれば当然、副作用の可能性はありますが、将来的なさまざまなリスクを予防するために治療が必要なケースがあるという点は、慢性的な成人病と同じ考え方ですので、それを周知する必要があると考えています。
田中アリケイスについては、今後、エビデンスの集積を進めて、どのようなタイプの患者さんでより効果が得られやすいか、データ集積に期待しています。肺MAC症だけでなく、他の肺NTM症、とくにM. abscessusの症例に対する効果的な治療法の確立なども、今後の展開として期待しています。
清家大学病院に求められているのはエビデンスを出すことと教育だと考えています。アリケイスを正しい患者さんに正しく届けるにはまだまだハードルがありますが、まずは大学病院が中心となってデータを集積し、エビデンスとして発表することが重要です。また、肺MAC症の教育についても大学病院が積極的に関わることが重要で、関連学会などとともに活動していきたいと思います。
山口やはり、肺MAC症の認知度を高めることは、今後、われわれの重要な課題になりそうですね。医師のみならず、一般の方々に対する啓発も推し進めていきたいと思います。
司会先生方、ありがとうございました。
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。
Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
ラミラ® is registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.