座談会

中島 啓 先生
亀田総合病院 呼吸器内科
主任部長 兼 内科チェアマン
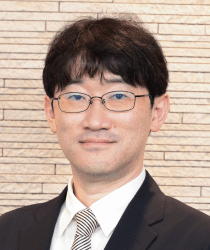
森本 耕三 先生
公益財団法人結核予防会
複十字病院 呼吸器センター 医長

出雲 雄大 先生
日本赤十字社医療センター 呼吸器
内科部長

宮本 篤 先生
国家公務員共済組合連合会
虎の門病院 呼吸器センター内科
医長

中原 善朗 先生
北里大学病院 呼吸器内科
診療准教授/外来主任
近年、本邦では肺MAC症患者が急増しており、診療を担う医師の育成と連携が重要な課題になっています。ときにむずかしい判断を伴うこともある肺MAC症診療において、診断・治療の質を担保しつつ診療の担い手を増やすには、どのような対策が必要でしょうか。今回、臨床呼吸器の教育に注力されている呼吸器専門医の先生方をお招きし、近年の肺MAC症診療の動向をふまえたうえで、さらなる向上のための課題と対策、また、近年使用が広まりつつあるアリケイスの導入などについて伺いました。
開催日:2024年8月30日
開催場所:ステーションコンファレンス東京
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです
01|近年の肺MAC症の動向
司会本日は呼吸器専門医の先生方に、肺MAC症診療について伺います。まず近年の動向として、本邦ではNTM症の罹患率(図1)1)と死亡者数2)の増加が報告されていますが、先生方はこの影響をどう感じていますか。
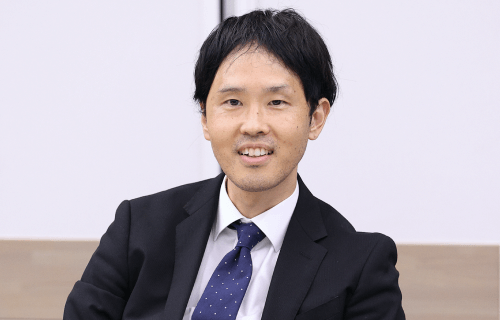
中島MACの主要な感染経路に土壌がありますが、私が勤務する亀田総合病院は千葉県の農業人口が比較的多い地域に位置する関係からか、以前から肺MAC症が多い印象がありました。それに加え、近年は肺MAC症の疾患認知度が向上したことで、肺MAC症を積極的に診断する施設が増えて、当院への肺MAC症紹介例が増加しています。
森本近年は関節リウマチや慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、肺癌などに肺MAC症を合併するケースが多いです。また、現在はさまざまな領域で免疫抑制薬が使われており、肺MAC症が発症・悪化しやすい素因がある方が増えていることも、患者数増加に関係していると思われます。死亡者数については、肺MAC症による死亡の割合は低いものの、肺MAC症患者の増加に伴い死亡者数も増えています。
出雲肺MAC症は合併症を有することが多いですが3)、死因となった疾患を判定する際、以前は肺MAC症が見逃されていたケースが少なくなかったと推測されます。肺MAC症が診断されるようになったことも、死亡者数の増加に関わっていると思います。
司会近年の肺MAC症診療に関わる重要な変化に、森本先生も委員として携わられた2023年の「成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」の改訂がありますが4)、こちらはどう評価されていますか。
中原この見解により、肺MAC症の国内の新たな治療方針(表1)4)が公に示された意義は大きいです。とくに、アジスロマイシンが選択肢に加わったこと、クラリスロマイシン(アジスロマイシン)+エタンブトール+リファンピシンの標準的な3剤併用療法からリファンピシンを除外した2剤併用療法が選択肢に加わったことで、治療しやすくなったと感じています。3剤併用療法は継続できない患者さんが一定数いますが、2剤併用療法ならば継続できるケースは少なくありません。また、外科治療の適応が追記されたことも、肺MAC症診療によい変化を及ぼしたと感じています。
02|肺MAC症診療における課題
司会見解改訂による進展があったものの、肺MAC症診療は今も決して容易ではないとのことですが、とくにどのような点に課題を感じていますか。
宮本まず診断のむずかしさが挙げられます。肺MAC症の確定診断では、喀痰検体の培養陽性が基準の一つになっていますが5)、肺MAC症は無症状例が多く、喀痰採取には難渋しがちです。
出雲とくに、健診から発見される無症状例は、新規肺MAC症患者の3分の1くらいを占めると思われますが、こうした方々に対して診断を目的とした気管支鏡検査を行うのはむずかしいのではないでしょうか。
宮本そうですね。患者さんの多くは実施に難色を示します。しかしそこで諦めるわけにはいかないので、半年~1年間はこまめにフォローアップし、悪化がみられたところで再び打診すると、患者さんも同意しやすいようです。ただし、治療が必要と判断した場合は、はじめから気管支鏡検査を勧めて早期診断を試みます。とくに合併症のある方は早急な治療を要することが多いので、より積極的に気管支鏡検査を行っています。
中島たしかに気管支鏡検査のハードルは高いのですが、私は患者さんに粘り強く勧めており、その結果として、最近は比較的早期の診断・治療介入が可能になってきたと実感しています。

森本肺MAC症の経過は個人差が大きく、治療開始の判断(図2)6-8)がむずかしい点も課題です。空洞のない結節・気管支拡張型であっても、およそ6割は3年以内に治療が必要になり、残りの4割は安定した経過となるものの、安定した状態が長期的に継続するのは1割以下ではないでしょうか。
中島長期に変化がないとそのまま安定すると予想されがちですが、なかには急激に進行する例もあります。また、空洞がある場合は難治化リスクが高いものの、意外にも初期は無症状であることが少なくないなど、経過には多様性があります。
喀痰塗抹陽性は治療開始のタイミングになりえますが、実際には空洞ができる前に治療開始することが重要です。そうなるとやはり、喀痰検査を繰り返し実施し、陽性となれば即治療することが望ましいでしょう。ただ、先のお話にあった通り、この喀痰採取が容易でないところが問題です。
出雲空洞のない無症状例の場合、喀痰採取がむずかしいことに加えて、早期治療の有用性もまだ確立されていませんので、治療方針の決定に悩むことが少なくないですね。
03|肺MAC症診療における連携と教育
司会患者数増加に伴い、肺MAC症診療においても院内や病診の連携、医師育成の重要性が増してきているようですが、その状況はいかがでしょうか。
中原先述の見解4)が発表されたことで、とくに若い先生方が肺MAC症を診療するハードルが下がり、連携しやすくなったと感じています。私は呼吸器内科の外来室に肺MAC症治療レジメンの表(表1)4)を貼っており、診療に携わる先生方にも確認してもらっています。
宮本病診連携については、虎の門病院呼吸器センターでは、おもに健診から発見された症例を逆紹介しています。ただし、逆紹介も見極めが重要です。治療が必要になる可能性が高い症例を逆紹介すると、進行してしまうリスクもあるため、ある程度の期間はフォローアップして治療の必要性を見極め、できるだけ逆紹介は呼吸器専門医にするようにしています。
中原北里大学病院は大学病院ゆえにさまざまな経験値の医師がいますが、肺MAC症診療の経験をなるべく共有するようにしています。入院例については、週1回のカンファレンスの際に経過を最初から振り返り、時間も長めに確保してディスカッションしています。
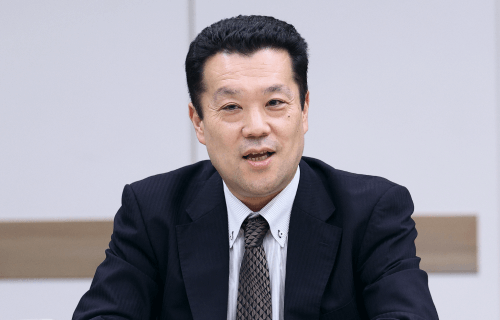
出雲先にお話があったように、肺MAC症診療に関わる見解改訂4)があったことは大きな意義があるのですが、これがさらに発展してガイドラインとして確立されると、専門医以外の先生方も肺MAC症診療により携わりやすくなるのではないかと期待しています。
森本さまざまな経験値の先生方が見落としなく肺MAC症を診療できるように、私はチェックリストを作成しており、ブログや総説で公開しています。より多くの先生方が診療に携われるように、また、主治医が代わっても適切な治療が維持される連携を築くために、わかりやすい基準を共有することは重要と考えています。
04|アリケイスの導入状況と課題
司会近年の肺MAC症治療の大きな変化の一つに、2021年のアミカシン吸入薬アリケイス(図3)の登場が挙げられますが、導入状況はいかがですか。
森本複十字病院では、入院指導でアリケイスを導入しています。アリケイスは薬価が高く貴重な薬剤ですので、吸入手技に誤りがあり十分に吸入されないという状況は避けたく、入院時に、確実に吸入できているかをスタッフが実際に確認してから使用開始しています。
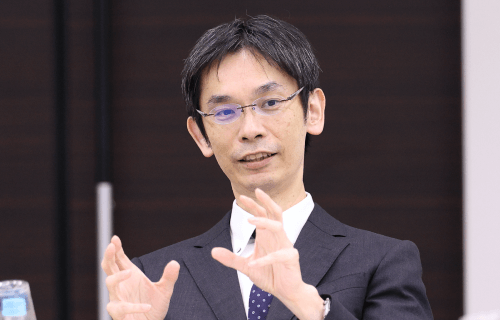
宮本虎の門病院呼吸器センターでも、アリケイスは入院指導で導入しています。喘息などの呼吸器疾患では、患者さんが手技を誤ったまま吸入を続けているというケースが意外にあります。アリケイスは吸入手技が複雑で、より確実に習得していただく必要があるので、吸入指導に精通した看護師の主導により入院指導を行っています。
森本若い患者さんは仕事で入院はむずかしいことがありますが、手技の習得が早いので、病院側の負担が大きいという問題はあるものの、外来でも導入できるようになればと考えています。
司会アリケイスの導入が困難なのはどのようなケースでしょうか。
宮本関節リウマチで手の動きに制限がある方などは、ご家族の支援がないと導入はむずかしいです。
中原ある程度症状が出ていたり、既存の治療に不満があったり、日常生活に支障があるなど、患者さんが現状に問題を感じていれば導入はスムーズですが、無症状で疾病による影響をとくに感じていないケースでは同意が得にくいです。本来は症状が顕著になる前にアリケイスを導入したいのですが、同意を得るための患者説明が課題となっています。
中島空洞がある方に対しては、空洞のリスクを詳細に説明し、できるだけ進行を抑えるためにはアリケイスの導入が勧められますとお伝えすると、前向きに捉えてくださることが多いようです。
宮本アリケイスを導入するには、やはり患者さんが納得することが重要ですね。十分に納得しないまま導入すると、後から金銭面に対する不満が出てきたり、吸入器具を雑に扱い誤って使用したり、副作用が出現した際に医師に不信感を抱いたり、さまざまな弊害が出やすくなります。長期に正しく継続してもらうには、前提として肺MAC症の病態をきちんと理解できる方を対象にする必要があります。
中島特殊な試みなのですが、亀田総合病院の呼吸器内科には、外来や病棟に所属しない、呼吸器内科専属の看護師が1名配置されています。アリケイスの患者説明はこの専属看護師が担っており、30分~1時間かけて詳細に説明しています。専属看護師はソーシャルワーカーの役割も兼ねており、患者さんと十分に対話して、生活環境なども伺い、不安や金銭的な相談にも対応してもらっています。この制度を取り入れてから、アリケイス導入の成功率は2~3倍上昇しました。
出雲アリケイスの導入のタイミングはどうされていますか。
森本標準治療を6ヵ月以上行っても排菌が陰性化しない場合には難治例と判断し、アリケイスあるいはアミノグリコシド注射薬の追加が推奨されています4)。当院で診療機会の多いマクロライド耐性例に対しては、私はまずはアミノグリコシド注射薬を追加し、3~4ヵ月後にアリケイスに切り替える形で導入しています。なお、アミノグリコシド注射薬は週3回投与が基本になりますが、患者さんが通いやすい地域の先生方に連携をお願いしています。
05|今後の展望
司会肺MAC症診療について、先生方が取り組みたい課題や改善が望まれることなど、今後の展望をお話しください。
中島肺MAC症と診断されても適切に治療されずに悪化していく患者さんが一部にいらっしゃいますが、そうした事態を防ぐために、今後、啓発活動にさらに力を入れたいと考えています。私は、研修医・若手医師を対象に呼吸器診療に関する医学教育を行う臨床呼吸器教育研究会CREATE9)の活動などを介して、先生方の肺MAC症診療への興味を引き出していければと考えています。
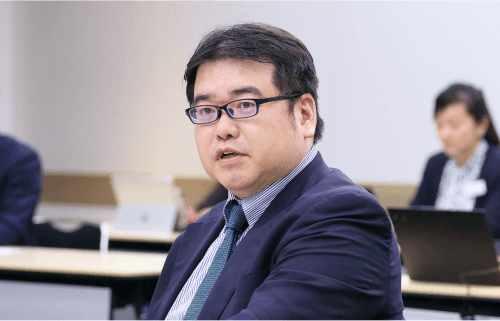
中原肺MAC症診療の魅力を知ってもらい、興味を持ってもらうことは重要ですね。研修医の先生方には、彼らが他科を選択した後にも知識が役立てられるように、積極的に肺MAC症症例を共有しておけば、将来的に彼らからの肺MAC症例の紹介や連携も期待できます。そうした未来への期待も込めて、教育・啓発活動に取り組んでいきたいと考えています。
宮本啓発活動を進めていくうえでは、まずは人の興味を引くことが重要です。若手医師への啓発はCREATEがかなり後押ししており、セミナーに参加してくれる医師は年々増えています。一方、地域医療への啓発は、まだ私たち専門医が自ら働きかけて興味を持ってもらえるように誘導しなければならない段階です。少しずつでも疾患認知度を上げて、「肺MAC症は専門医との連携が必要な疾患」という認識を広めていきたいと考えています。
また、クリニックとの連携については、再紹介の基準やフォローアップの方法を明確にすることで、協力可能な医師を増やしていきたいと考えています。
出雲啓発活動の一環として、本日話題に上った診断や治療介入のタイミングのむずかしさなど、肺MAC症診療の課題を克服するための情報発信もしていけたらと思います。喀痰採取の必要性や、重症化しやすく早期治療が必要な患者の特徴などを、将来的にはエビデンスをもって示せるようになれば、一般内科医の肺MAC症診療のハードルが下がると期待されます。基準が明確でないゆえに、漫然とした治療を続けて難治化させてしまうケースを減らしていきたいと思います。また、喀痰による診断だけではなく、マーカーが確立されて、専門医以外でも肺MAC症を容易に診断できるようになればと願っています。
森本本邦では肺NTM症の専門医が少なく、この状況を改善するには、やはり若手医師の参入が鍵になります。最近は、肺NTM症の後遺症としての気管支拡張症や、NTMとアスペルギルスとの併発感染が問題になっていることから、慢性感染症という大きなくくりとして興味を持ってくれるように、若手医師に働きかけていこうと考えています。肺NTM症診療に多くの先生方が携わるようになり、日本全体の肺NTM症診療を底上げできればと思っています。
司会本日は、示唆に富んだご意見をありがとうございました。
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。
Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
ラミラ® is registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.