座談会

原 丈介 先生
金沢大学呼吸器内科
地域連携呼吸器内科学講座
特任准教授

西 耕一 先生
にし内科・呼吸器クリニック 院長

古荘 志保 先生
金沢市立病院 呼吸器内科 科長

片山 伸幸 先生
特定医療法人社団勝木会
やわたメディカルセンター 副院長

北 俊之 先生
独立行政法人 国立病院機構
金沢医療センター 呼吸器内科 部長

野村 智 先生
富山市民病院 病棟診療部主任部長
呼吸器内科部長
腫瘍内科部長 内科医長
本邦では肺MAC症の疾患啓発が徐々に進んでおり、医療者の意識も変わりつつありますが、年々増え続ける患者数に対し、医療体制は十分に整っていない状況です。また、新薬の登場や治療に関する見解の改訂など、大きな進展があったものの、疾患の複雑さや治療開始基準の不明瞭さなどから、肺MAC症診療にはいまだむずかしい側面があります。今回は北陸地方の呼吸器専門医の先生方をお招きし、近年の動向を踏まえて、肺MAC症診療の現状と課題、また、もう一つの選択肢として近年使用が広まりつつあるアリケイスの導入、今後の展望などについて伺いました。
開催日:2024年10月10日
開催場所:ANAクラウンプラザホテル金沢
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです
01|近年の肺MAC症患者の動向
司会本日は北陸地方の先生方に、近年の肺MAC症診療の動向、現状と課題などについて伺います。まず、近年、本邦では肺MAC症の患者数が増加しておりますが(図1)1)、先生方は肺MAC症のどのような特徴や変化、診療への影響をお感じでしょうか。

西私の経験では、結核菌やMACのPCR検査の普及に伴い、肺MAC症と診断される症例が増加してきたと感じています。診療する肺MAC症の患者数が年々増えている実感があります。
片山肺MAC症の疾患認知度の向上に伴い、近年は医療者のみならず患者さんのなかにも、肺MAC症診断に積極的な方が増えてきた印象があります。画像検査で異常が指摘された患者さんが自らネット検索し情報を得て、「私は肺MAC症でしょうか? 治療が必要でしょうか?」と相談に来られるケースが、この数年で増えています。
野村肺MAC症患者さんは、以前は咳や痰などの自覚症状で来院されることが多かったのですが、近年は画像検査で肺抗酸菌症が疑われ紹介される方が増えてきています。
また、富山市では二次救急輪番制を採用しており、当番日には富山医療圏の全患者が搬送されてきます。救急患者さんではCTを撮影する機会が多いため、胸部異常影が偶然見つかることも少なくありません。このCTが契機となって、後日に肺MAC症と診断されるケースも比較的多いのが当院の特徴です。
北肺MAC症は無症状であることが多く、金沢医療センターでも無症状例が大半ですが、一方で、近年においても血痰や喀痰を主訴に来院される方が少なくないと感じています。肺MAC症の病変は肺の中葉や舌区といった心臓近傍に発現することが多く、軽症例の場合、胸部X線検査では異常陰影が心臓に隠れて検出されないことがよくあります。早期診断が進んでいる一方で、かなり進行してから診断される方もいまだ少なくありません。
野村肺MAC症は一般的に進行が緩徐なため、診療の緊急度が増している実感はありません。ただ、フレイルやサルコペニアを併発し全身状態が悪化して対応に苦慮する症例が少しずつ増えており、近年、その影響を感じています。
02|肺MAC症診療における課題
司会肺MAC症診療は容易ではないという声を聞きますが、先生方は実際にどのような点を課題と感じていらっしゃいますか。
北2023年に「成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」が改訂され2)、この臨床的意義は大きいと思います。しかし、診療指針が十分に確立されるにはまだ至っておらず、とくに治療開始基準が明確でない点が課題だと思います。また、無症状の患者さんでは治療に積極的でない方が多い点も課題の一つです。

原そのような患者さんへの対策として、私は経過観察の初期から「まずは経過を見ますが、いずれ悪化した場合には薬を使う必要があります」と伝えています。また、患者さんの判断で通院を中止しないように、経過観察の重要性も併せて伝えるようにしています。
片山肺MAC症治療はいったん開始すると治療が長期に及びます。心理的な影響もあって、とくに無症状の若年女性患者さんでは治療を拒否されることが多く、定期的な画像検査による経過観察を継続するケースが増えています。
ただし、今後の悪化が予想される場合は、時間をかけて十分な説明を行い、積極的に治療を勧めています。たとえば、空洞を有する症例は、無症状であっても、その後に喀血などの症状が出たり、難治化して肺構造が壊れたり、炎症反応が強く疲労感が重くなったりするなど、リスクが高いです。そのような患者さんには、無症状でも病変が限局性のうちに治療介入し、拡大させないことが重要と考えています。
北ほかには、喀痰検査で抗酸菌塗抹陽性の方や免疫抑制薬を使用している方なども、無症状のうちから積極的な治療が必要と考えます。
また、病変が限局性であれば手術も選択肢になりますが(表1)3-4)、無症状の方では、手術も拒否されがちです。とくに薬物療法を行っても排菌が停止しない若年者では、将来を考えて外科的治療介入を早めに行いたいのですが、現実的には難しいケースがあります。
片山肺MAC症の手術は合併症を起こしやすいため、医師側もあまり積極的でないことがあり、漫然と薬物治療を行ううちに進行して難治化、重症化するケースがあります。
西医師側も肺MAC症は良性疾患という意識が強いようで、良性疾患の手術で合併症を起こしてトラブルになるのは避けたいという気持ちから、手術には消極的な傾向があるのかもしれません。積極的な手術により、その後の治療成績が向上するケースは少なくありませんので、薬物治療に限界があるなかで、手術の有用性を検討することは重要と考えられます。
北肺MAC症は治療開始時期を逃して空洞病変が形成されてしまうと、その後の治癒はむずかしくなります。肺MAC症の治療ゴールは、排菌があれば菌陰性化が一つの目安になりますが、空洞を有する場合はQOL改善を目指すのが現実的になるのではないでしょうか。
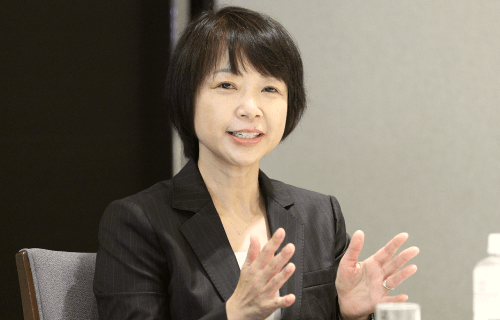
古荘治療や手術を行うかどうかは、患者さんの年齢によっても判断が異なりますが、時期を逃すと選択肢がなくなる可能性があることには注意したいですね。将来の長い若年者では、病変が軽度でも、治療開始したほうがよいのではないでしょうか。
司会空洞化のほかには、どのようなケースが難治化しやすいのでしょうか。
古荘炎症反応が強いケースや、真菌(アスペルギルス)や緑膿菌など、ほかの菌と共感染を起こしたケースなども難治化しやすい傾向があります。共感染例は、相互作用の問題で併用できない薬剤もあり、どちらの感染症を優先して治療すべきか判断がむずかしいことがあります。また、結節・気管支拡張型の肺MAC症であっても、気管支拡張が著しく進行して肺葉全体に広がると、空洞がある症例と同様の対応が必要になります。
原炎症反応については、疾患進行に伴い炎症反応が著しく上昇し38℃近くの発熱を認めるケースを経験したことがあります。CRPが10mg/dLくらいまで上昇し、肺MAC症だけでこれほど上昇するものかと疑問に感じることもありましたが、肺MAC症治療を強化すると炎症反応はおおむね低下しています。
司会こうした肺MAC症の疾患の複雑さや、また、先にお話に出たような患者数増加に伴い、近年は肺MAC症診療においても院内の多科連携や病診連携の強化が求められていますが、このような連携の状況はいかがでしょうか。
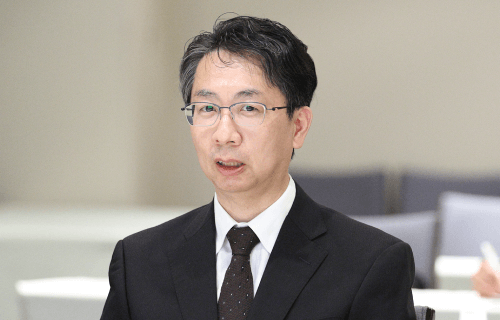
片山肺MAC症はリウマチ性疾患の患者さんに併発していることも多いため、やわたメディカルセンターではリウマチ科と呼吸器内科が協働で肺MAC症診療を担っています。地域の診療所から肺MAC症の疑い例を紹介されることが多いですが、当センターでいったん治療を開始してからの逆紹介は難しく、結果的にそのまま診療継続する患者さんが累積している状況です。病態が安定した経過観察中であれば、併診という形で常時は診療所が診療を担い、当センターでは半年に1回程度のCT検査を行っていますが、残念ながらまだ十分な病診連携の構築には至っていません。
原院内の連携については、私は若手医師の教育に課題を感じています。閉塞性肺疾患や肺がんなどのメジャーな疾患に対しては、呼吸器内科の研修医に個別に講義をするなど、教育に力を入れていますが、肺MAC症については十分に手が回っていない状況です。研修医の肺MAC症の疾患知識は教科書や医師国家試験レベルで留まっているケースが多い印象で、今後は症例カンファレンスを行うだけでなく、教育の機会を設けたり最新情報を定期的に発信したりするなどの対策を講じたいと考えています。
西先に述べたように、薬物療法に限界があるなかで外科手術が必要な症例に速やかに対応するために、呼吸器内科と外科との連携も今後はより強化が必要と感じています。
表1
肺MAC症における
外科的治療の適応3-4)
03|アリケイスの導入状況と課題
司会肺MAC症診療にはまださまざまな課題がある一方、近年は一定の進展もみられています。アミカシン吸入薬であるアリケイス注)は難治例の治療選択肢として改訂見解に記載されましたが(表2)2)、この導入状況や、導入時の課題についてはいかがでしょうか。
原軽症例へのアリケイス導入は、慎重に経過を見極めれば、適切な導入時期を逃すことはあまりないように感じています。私は導入時期を必ずしも統一する必要はないと考えており、経過、症状・画像所見の進行、多剤併用療法の効果などから、症例ごとに柔軟に判断しています。
野村広範な気管支拡張や空洞形成がみられると、治療しても元通りになることはむずかしく、構造が破壊された部位では吸入薬の組織移行が十分でないことが予想され、より早期からの導入が重要だと考えています。
西治療期間がすでに7~8年と長期に及んでいる場合や、クラリスロマイシン耐性、複数の空洞が形成されている場合など、疾患が進行してしまうと、アリケイスを追加しても十分な効果は得にくいと考えています。
古荘肺MAC症では、病変が軽度である場合の治療強化が臨床転帰にどうつながるのかまだ確実にはなっていませんが、臨床研究からそこが明確になると、長期に進行を防げる症例が増えることが期待できるかもしれませんね。
野村導入の課題については、高齢患者のエビデンス不足が挙げられます。アリケイスの有効性を検証した国際共同第Ⅲ相試験(CONVERT試験)の日本人患者の平均年齢は65歳ですが5)、肺MAC症は70代超のより高齢の患者さんも多く、エビデンスが少ないこの年代への導入にはためらいがちなのではないでしょうか。
また、高齢者はすでに他疾患で複数の薬剤を服用していることが多いですが、肺MAC症治療で新たな薬剤がさらに追加されるとなると、患者さんがアリケイス導入に後ろ向きになってしまうことがあります。
古荘一方、吸入薬は局所的な治療が可能で血中濃度の上昇を抑えられるというメリットがあります。アリケイスとアミカシン注射薬が選択肢になった場合、双方のメリット・デメリットを考慮すると、アリケイスの方が勧めやすいケースもあります。

北そのほかに、アリケイス導入の課題には、吸入器の準備や吸入手技の煩雑さ、高額な薬剤費なども挙げられます。金沢医療センターでは、こうした課題に対応するために、アリケイスの説明を担う専門の薬剤師やケースワーカーを含めたチーム医療で導入指導を行っています。
表2
成人肺非結核性抗酸菌症
化学療法に関する見解
― 2023年改訂 ―2)
04|今後の展望
司会肺MAC症診療について、先生方が取り組みたい課題や改善が望まれることなど、今後の展望をお話しください。

野村肺MAC症の病診連携はまだ十分に広がっていない状況ですが、将来的には、十分な連携のもとに、内科医であれば誰でも肺MAC症の検査や経過観察が可能になることが理想的です。私は、そのための啓発活動に力を入れたいと考えています。
古荘そうした啓発活動の一環で、私はクラリスロマイシン(CAM)耐性を回避するための抗菌薬の使用方法なども訴求したいと考えています。ほかの呼吸器疾患の治療で低用量CAMを長期に使用していたところに肺MAC症を併発し、肺MAC症診断時にはCAM耐性となっている症例が一定の割合で認められます。内科の先生方への啓発を通して、こうした状況も改善していければと考えています。
西本日の議論でも挙げられた通り、肺MAC症の薬物治療にはまだ多くの課題があります。薬物治療に限界があるなかで、必要な症例には速やかに外科手術を施行できるよう、私は内科だけでなく、外科と呼吸器内科との連携強化についても、今後推し進めていきたいと考えています。
北近年は、さまざまな関連学会や講演会などで、肺MAC症の早期治療の有用性について耳にするようになりましたが、まだ十分なデータは示されていません。今後、このエビデンスが構築されて治療開始の基準がより明確になれば、肺MAC症治療もだいぶハードルが下がるのではないかと期待しています。
片山私は、今後、薬物治療の発展とともに、環境因子への介入方法も確立されることを願っています。MACを含むNTMは水場や土壌などに生息する環境常在菌(図2)6-7)で再感染のリスクが高いですが、環境への介入方法のエビデンスが構築されて、肺MAC症に再感染しないための具体的な方法を患者さんに提案できるようになればと思っています。
原私は、肺MAC症を発症・悪化しやすい宿主側の因子をより明らかにしたいと思っています。今、私がとくに興味を持っているのは、咳の抑制と肺MAC症の関連です。咳を我慢したり抑制したりすることで肺MAC症の発症・悪化を促進する可能性があると示唆されていることは非常に興味深いです。また、将来的には、抗菌薬による治療とともに、宿主因子や環境への介入も併用することで、予後改善につなげていければと考えています。
司会先生方、示唆に富んだご意見をいただき、本日はありがとうございました。
図2
NTMの生息環境6-7)
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。
Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.