座談会
(左から)
| 佐々木 結花 先生 | 独立行政法人 国立病院機構東京病院 呼吸器センター 呼吸器内科・副院長・臨床研修センター長 |
|---|---|
| 木田 博 先生 | 独立行政法人 国立病院機構 大阪刀根山医療センター 呼吸器内科部長・臨床研究部抗酸菌研究室室長 |
| 山本 和子 先生 | 国立大学法人 琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座 教授 |
| 中川 拓 先生 | 独立行政法人 国立病院機構 東名古屋病院 副院長 呼吸器内科 |
| 森本 耕三 先生 | 公益財団法人 結核予防会 複十字病院 呼吸器センター 医長 |
| 長谷川 直樹 先生 | 慶應義塾大学医学部 感染症学教室 |
本邦の肺NTM症は診療の指針・見解に長らく大きな進展がなく、保険診療で使用できる薬剤も限られていましたが、近年、そうした状況にも変化が訪れました。アミカシンが2019年、アジスロマイシンが2020年、イミペネムとクロファジミンが2021年に審査事例として承認され、さらに治療の見解・診断の指針改訂が2023年と2024年に続けて行われました。今回、これらの進展に尽力された先生方をお招きし、改訂の背景および実臨床への影響についてお話しいただきました。
開催日:2025年2月6日
開催場所:東京ドームホテル
アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
01|治療の見解改訂の経緯
長谷川本邦では2008年に肺非結核性抗酸菌症診断基準が発表されて以降、診断の指針に長らく進展がありませんでした。しかし、2020年に国際ガイドライン(ATS/ERS/ESCMID/IDSAガイドライン2020)が改訂されたことを受けて、これに追随する形で2023年に成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解(以下、治療の見解)が改訂され、さらに2024年には肺非結核性抗酸菌症診断に関する指針(以下、診断の指針)が改訂されました(図1)1-5)。本日は、私を含めこれらの改訂に携わった先生方に参加いただいておりますので、改訂の背景なども含めてお話を伺いたいと思います。
まず、治療の見解改訂の大きなポイントとして、肺MAC症の治療方針が病型ごとに示された点があります(表1)4)。そのなかでアミカシンとアジスロマイシン(AZM)が新たな治療選択肢として記されましたが、この背景として、アミカシンが2019年に、AZMが2020年に審査事例として承認を受けていたことが大きな後押しになったと考えられます6)。まず、この審査事例の承認に尽力された佐々木先生に、その経緯をお伺いします。
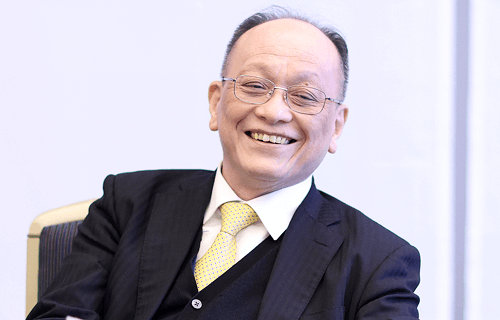
佐々木当時、アミカシンとAZMは、欧米では肺NTM症への使用が認められていたものの、本邦では肺NTM症への保険適用がなく、医療者のみならず患者さんからも疑問や要望が挙がっていました。審査事例の承認を受けるには、その疾患に対する薬剤の有効性、安全性、使用方法などを詳細に示す必要があります。幸い、英国胸部疾患学会(BTS)による肺NTM症ガイドラインにそれらを網羅する記載があり7)、これを参照することで基準をクリアすることができました。
長谷川薬剤は公費でカバーされていないと、使用を推奨するような記載を公の指針に入れることは困難ですので、審査事例として承認を受けたことは非常に意義がありました。先生方は改訂のコアメンバーとして参加されていましたが、どのように感じていらっしゃいますか。
森本アミカシンとAZMが治療選択肢に加わり6)、さらに国際ガイドラインも発表されて機が熟し3)、本邦でも指針を確立しなければならないという機運が高まったなかで治療の見解を改訂できたのは、とてもよいタイミングだったと感じています。
中川治療の見解改訂の前から、実は肺NTM症の実臨床は変化しつつあったのですが、それがエビデンスをもって見解や指針に反映されたことは意義深いと考えています。
山本欧米のガイドラインとのギャップが少し解消され、とくにAZMを第一選択薬の1つとして使用できるようになったことは4)大きな進展だといえるのではないでしょうか。
長谷川こうした変遷を経て、現在、アミカシンとAZMは肺NTM症治療のキードラッグとして使用できるようになりました。米国、英国、EU、オーストラリアでも肺NTM症に対するアミカシンに保険が適用されることはなく6)、現在、日本は肺NTM症の治療薬の選択肢が世界に比べると充実しているといえます。なお、アミカシン注射薬は審査事例としての承認ですが、アミカシン吸入薬であるアリケイスは2021年に難治性肺MAC症を適応症として承認されています注)。
図1
肺NTM症に関する本邦の
見解および指針の変遷
表1
成人肺非結核性抗酸菌症
化学療法に関する見解
―2023年改訂―4)
02|治療の見解改訂が
実臨床に及ぼす影響
長谷川治療の見解改訂(表1)4)による実臨床への影響については、どのように感じていますか。
木田難治性肺MAC症例について、多剤併用療法を6ヵ月以上実施しても細菌学的効果が不十分な患者と定義された4)ことは、非常に意義があると考えます。従来は漫然と治療が継続される例が少なからずありましたが、「6ヵ月」という基準が明示されたことにより、いわゆるTreat to Targetのような意識が生まれ、6ヵ月間で治療目標を達成することが1つの目標になってきたと感じます。標準治療を6ヵ月行っても菌陰性化しない場合には難治例と判断し、アミカシンなどの追加を考慮するタイミングとなります4)。
中川実際、治療の見解改訂後から、標準治療を6ヵ月間行い菌陰性化しなかった時点で、難治例として紹介される肺MAC症患者さんが増えたように感じています。
長谷川とくにマクロライドへの感受性が保たれているうちに次の治療に移行する必要がありますし、なかでも難治化する可能性のある人では重要です。明らかに治療困難になってから次の手を考えるのではなく、時期を区切って治療法を検討・再考することが大切なポイントですね。
佐々木後手にならない期間の目安として6ヵ月が妥当なのかどうかを、今後検討する必要があるのではないかとも考えています。
森本ほかには、週3日投与およびマクロライド+エタンブトール(EB)による2剤併用療法が肺MAC症の治療選択肢として新たに記載されたことも、影響を及ぼしています。これは国際ガイドラインと異なる日本独自の方針ですが4)、超高齢化社会の本邦では理に適っており有用と感じています。実臨床では、こうした選択肢が増えたことで治療継続しやすくなったという声が聞かれます。
中川私は、空洞のない結節・気管支拡張型の場合、AZM+EB+リファンピシンによる3剤併用療法の週3日の間欠的投与を用いることが多いのですが、高齢患者さんに連日投与する場合は、AZM+EBによる2剤併用療法をしばしば選択しています。
山本私は3剤併用療法を用いることが多いのですが、高齢者の場合はとくに注意してモニタリングし、副作用が懸念されたら2剤併用療法への切り替えを検討しています。
佐々木多剤併用療法では服用する薬剤数(錠剤・カプセル数)が多いという問題もありますが、AZMは500mgの製剤が発売されています。従来よりも、AZMを含むレジメンでは錠数を減らせますので、この点でも、AZMを含むレジメンが治療の見解に記載されたのは、患者さんにとっての現実的なメリットと感じています。

森本AZMの注意点として、最小発育阻止濃度(MIC)が高く出ても実際には感受性が保たれていることがあります。CSLIに記載されているように、MICの評価法はまだ確立していないため、MICの数値で感受性を評価すると判断を誤る可能性がある点には注意が必要です。AZMの感受性評価法については、今後のさらなる研究が望まれます。
長谷川アミカシンの点滴と吸入の使い分けについては、どうされていますか。
山本入院患者さんにはアミカシンの点滴を用いています。進行性で空洞を有する患者さんの場合も、私はなるべく点滴治療を行うようにしています。
森本ただ、末梢からの点滴治療の継続期間は3~4ヵ月ではないでしょうか。点滴治療の継続がむずかしくなってきたと感じたら、私はアリケイスに切り替えています。
山本外来治療に移行すると点滴治療は困難なことが多く、現実的な治療継続は1~2ヵ月が目安であるように感じています。また、全例が頻繁に外来通院できるわけではありません。そのため、病状がある程度安定してきた時点、具体的には外来治療に移行するタイミングで、アリケイスへの切り替えを検討するのがよいのではないかと考えています。
木田アミカシンを点滴投与する場合は、詳細なモニタリングが必要なこともあり、私は基本的にはアミカシンを追加する当初からアリケイスを導入することが多いです。
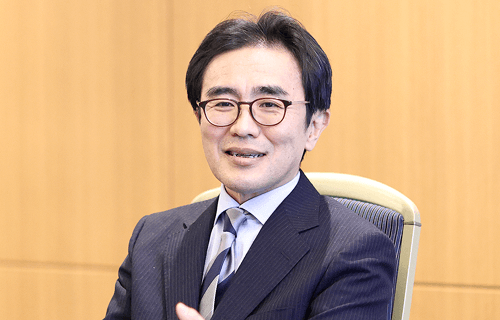
中川アリケイスの導入に同意していただけない場合は、まずはアミカシンの点滴を導入しています。アリケイスは理論上、高濃度アミカシンが肺末梢に届くという作用機序を有することもあり、吸入薬のほうが望ましい症例であれば後日にていねいに説明し、切り替えを勧める場合もあります。
佐々木菌陰性化とは別の観点ですが、吸入薬は症状の改善について患者さんの満足度が高い印象があります。吸入薬に切り替えて排菌陽性は継続していても、咳や痰の症状が改善して活動できるようになったと患者さんから聞くことがたびたびあります。
03|診断の指針改訂が
実臨床に及ぼす影響
長谷川次に、診断の指針改訂について話を進めます。本改訂の重要なポイントに、従来の診断基準に加えて、暫定的診断基準が採用された点が挙げられます(表2)5)。肺NTM症の診断に喀痰検査を用いる場合、2回以上の異なった喀痰検体での培養陽性が診断基準とされています。新たに加わった暫定的診断基準は、①肺MAC症の初回診断時に限り、臨床的基準を満たし、1回の喀痰検体で培養陽性かつ抗Glycopeptidolipid-core IgA抗体陽性、または②臨床的基準を満たし、胃液検体で培養陽性の場合、喀痰検体で1回以上の培養陽性を満たすこととされました5)。この暫定基準は日本独自のものであり、MACの細胞壁成分であるGlycopeptidolipid(GPL)を抗原とする抗GPL-core IgA抗体を評価する血清診断法は本邦で開発されたものです5)。この抗GPL-core IgA抗体の評価を取り入れるエビデンスとなったデータには木田先生のグループからの報告が含まれていますが8)、木田先生はこの抗体評価についてどうお考えでしょうか。
木田日本で開発された技術を診断基準に取り入れることができた点は大変喜ばしく、これが今後、日本の診断基準がより発展していくきっかけになればと願っています。また、肺NTM症の診断では、それが単にNTMの定着なのか、感染なのかをいかに見分けるべきかという議論があります。血清抗体を暫定的診断基準に取り入れたことで、血清抗体が生成されたら感染であるという一定のコンセンサスができたと考えており、この点も評価できるのではないかと思っています。
長谷川今後は、画像検査で肺NTM症が疑われたら抗GPL-core IgA抗体を評価し、そこで陽性であれば喀痰検査を行い、培養陽性が1回認められたら基本的には暫定的診断により肺NTM症として対応するのが一般的になりそうですね。抗GPL-core IgA抗体は非常に有用なスクリーニングになると思います。ただし、抗GPL-core IgA抗体陽性であればただちに肺MAC症と診断されるわけではなく、また、抗GPL-core IgA抗体が陰性であれば肺MAC症を否定できるわけではない点には注意が必要です。
中川M. abscessusをはじめとする、MACのGPLと構造が類似するGPLを細胞壁に保有する迅速発育菌では抗GPL-core IgA抗体陽性になりうるため、抗GPL-core IgA抗体を用いて暫定的に診断された肺MAC症では、それらの菌種による感染症の可能性があることにも注意が必要です9)。また、抗GPL-core IgA抗体は一般に抗MAC抗体と呼ばれていますので、患者さんがその意味合いを勘違いしやすく、ここは医師が正しく説明する必要があります。
長谷川胃液検体の評価についてはいかがですか。
森本胃液検体は結核症診断では広く用いられてきましたが、NTMは消化管液に常在している可能性があるため、肺NTM症診断には不適とされてきました2)。しかし、実際に私たちがデータを集積し解析したところ有用なことが明らかになり10-11)、暫定的診断基準に組み入れることになりました5)。
木田胃液検体を用いた暫定的診断では、喀痰から検出されるNTMと、胃液から検出されるNTMが同一ということが前提となっている点が重要なポイントです。
長谷川国際ガイドラインの肺NTM症診断基準3)には症状の有無がありますが、本邦の診断基準、暫定的診断基準には症状の有無は組み込まれていません。症状に指標を置くと進行を見逃しかねないので、私は症状にかかわらず診断できる本邦の方針を支持しますが、先生方はどのようにお考えでしょうか。
佐々木無症状例の診断・治療に関して、肺NTM症を疑いながら症状の発現を待って治療開始する欧米のスタイルに対し、本邦では早期に診断して治療を開始することで進行を予防し、最小限の治療に留めることを目指すという、医療に対する考え方の違いといえるのではないでしょうか。

山本現在の肺NTM症患者さんは健診から発見される無症状例がかなりの割合を占めていると思います。そのため、本邦独自の診断および暫定的診断の基準は国内の状況に適しているのではないでしょうか。本邦の肺NTM症診療は、今後、欧米とは異なる独自の発展をしていく可能性もあると期待しています。
中川日本はCTを手軽に撮れる環境にありますので、他疾患に対しCT検査を行い、そこから肺NTM症の診断へとつながるケースも多いです。
森本私たちは2014年の全国調査で、肺NTM症の罹患率(10万人あたり)は14.7、2017年には19.2であったことを過日報告しました(図2)12)。この患者数の増加には、全国調査で医師の意識が高まって積極的に検査するようになったことをはじめ、複合的な要因があるようです。
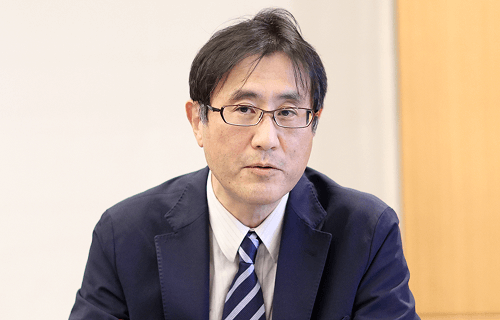
木田森本先生のデータを大阪府豊中市の人口約40万人に当てはめると肺NTM症患者数は年間80人くらいということですが、当院で肺NTM症と診断されるのもほぼ同じ割合です。新規に診断された肺NTM症に占める無症状例の割合を、全国的に調べてみてもよいかもしれません。
佐々木今回、暫定的診断基準が取り入れられたことで、無症状例の治療開始の目安が科学的な裏付けをもって判断しやすくなったことは大きな進歩と感じています。ただ、健診から肺NTM症が明らかになった無症状の患者さんは、受診されても、そこで医師から危機感のない説明を受けると、症状が出るまで受診しなくなってしまうことがあるようです。それは非常にもったいないことですので、経過観察や治療の意義が正しく認知されるように、若手の先生方とも一緒に啓発していきたいですね。
山本残念ながら沖縄県では肺NTM症の受診率が低く、県民や医療者への啓発が十分ではありません。また、専門医に紹介すべきタイミングや基準がまだ明確に示されていない点も課題と感じています。これらを明確にすることで肺NTM症の病診連携を促進できればと願っています。
長谷川治療の見解、診断の指針の普及を進めるとともに、それらが適切に活用されるように努めてゆくことが、病診連携を推し進める鍵になりそうですね。
先生方、本日はありがとうございました。
表2
肺非結核性抗酸菌症診断に
関する指針(2024年改訂)5)
図2
本邦における肺NTM症
罹患率の年次推移
(1971~2017年)12)
アリケイスの有効性・安全性情報については、電子化された添付文書をご参照ください。
Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.